2009年09月08日
・駒ヶ根市の事業はコンサル任せ
駒ヶ根市地域公共交通協議会というものがあるのだが、駒ヶ根市民でもその存在を知っている人はごくわずかだろうと思う。
協議会設置の目的は、『バス事業を根本的に見直し、地域ニーズに沿ったわかりやすい公共交通へ再編し、安定して持続可能な駒ヶ根市らしい仕組みづくりを目指して調査事業を推進します。』
調査内容は、
○社会状況、施設立地状況、道路状況等の基礎調査
○現況公共交通実態調査
○利用者ニーズ把握調査(アンケート調査、乗り込み調査等)
○福祉、学校、観光等の関係機関ヒアリング
○公共交通事業者ヒアリング
○住民説明会
下部組織としてワーキンググループが組織されていて、実際の調査や検討を担当するのだと思っていた。
ところが、ワーキンググループのメンバー構成が事務局の思惑とは違ってしまっているというのだ。
駒ヶ根市の交通弱者を思いやり、地域の足を考える上で、我田引水は絶対に避けなければならない。
「うちの地域のバス停を、もうちょっとこっちへ動かしてくれないかな」的な提案はご法度なはずだ。
しかし、そのご法度が公然と語られているようでは、公共交通を検討する組織として機能しない。
やはりというか、この事業には国庫補助金が投入されている。
補助金が投入されれば、コンサルタントが介入する。
補助金のほとんどはコンサルタント料として費やされ、協議会の資料もコンサルが調達した「それなりの」データーが並ぶことになる。
地域の実情が必ずしも反映された事業にならない理由がここにある。
本来ならコンサルタントなどには頼らずに、市役所の職員が事務局になって有能な市民を集めて有意義に補助金を使うことが求められている。
しかし、「楽をしたい」職員が担当すると、安易にコンサルタントに頼ることになる。
コンサルタントに頼めば、見栄えの良い、落ち度のない報告書が出来上がるので、職員の手間も省けて評価も上がる。
事業の中身よりも補助金が上手に消化できるかどうかというのが、ポイントになるのだそうだ。
職員の資質によるところが大きいので、やる気があり能力が高い担当者に恵まれた事業は、コンサルまかせでなくても市民協働で実のある成果を達成できる。
反面、やる気がなく、能力のないものが担当した事業は、補助金が生かされないばかりか、事業も市民の目線とはかけ離れて市民サービスにつながらない。
ひとえに、市職員の人事権を持つ市長の能力が成否を左右するのだ。
今回の事業がおざなりになるかどうかで、担当の課長の手腕が問われる。
コンサルに任せて、形だけの会議を数回開いた程度で報告書を作成するようでは、効果的な検討などできるはずがない。
協議会のメンバーが現場に出向いて、現地の住民の生の声を聞き、喧々諤々(けんけんがくがく)の論議を多数重ねてこそ、市民サービスの向上につながる。
杉本・駒ヶ根市長は、協議会の開催回数をちゃんと把握しているかな。
2、3回の会議でまとめようとしているのではないかな。
コンサル任せではなく、協議会のメンバーが主体的に行動するように、市長の責任で指示しなさい。
市民はちゃんと見ているよ。
協議会設置の目的は、『バス事業を根本的に見直し、地域ニーズに沿ったわかりやすい公共交通へ再編し、安定して持続可能な駒ヶ根市らしい仕組みづくりを目指して調査事業を推進します。』
調査内容は、
○社会状況、施設立地状況、道路状況等の基礎調査
○現況公共交通実態調査
○利用者ニーズ把握調査(アンケート調査、乗り込み調査等)
○福祉、学校、観光等の関係機関ヒアリング
○公共交通事業者ヒアリング
○住民説明会
下部組織としてワーキンググループが組織されていて、実際の調査や検討を担当するのだと思っていた。
ところが、ワーキンググループのメンバー構成が事務局の思惑とは違ってしまっているというのだ。
駒ヶ根市の交通弱者を思いやり、地域の足を考える上で、我田引水は絶対に避けなければならない。
「うちの地域のバス停を、もうちょっとこっちへ動かしてくれないかな」的な提案はご法度なはずだ。
しかし、そのご法度が公然と語られているようでは、公共交通を検討する組織として機能しない。
やはりというか、この事業には国庫補助金が投入されている。
補助金が投入されれば、コンサルタントが介入する。
補助金のほとんどはコンサルタント料として費やされ、協議会の資料もコンサルが調達した「それなりの」データーが並ぶことになる。
地域の実情が必ずしも反映された事業にならない理由がここにある。
本来ならコンサルタントなどには頼らずに、市役所の職員が事務局になって有能な市民を集めて有意義に補助金を使うことが求められている。
しかし、「楽をしたい」職員が担当すると、安易にコンサルタントに頼ることになる。
コンサルタントに頼めば、見栄えの良い、落ち度のない報告書が出来上がるので、職員の手間も省けて評価も上がる。
事業の中身よりも補助金が上手に消化できるかどうかというのが、ポイントになるのだそうだ。
職員の資質によるところが大きいので、やる気があり能力が高い担当者に恵まれた事業は、コンサルまかせでなくても市民協働で実のある成果を達成できる。
反面、やる気がなく、能力のないものが担当した事業は、補助金が生かされないばかりか、事業も市民の目線とはかけ離れて市民サービスにつながらない。
ひとえに、市職員の人事権を持つ市長の能力が成否を左右するのだ。
今回の事業がおざなりになるかどうかで、担当の課長の手腕が問われる。
コンサルに任せて、形だけの会議を数回開いた程度で報告書を作成するようでは、効果的な検討などできるはずがない。
協議会のメンバーが現場に出向いて、現地の住民の生の声を聞き、喧々諤々(けんけんがくがく)の論議を多数重ねてこそ、市民サービスの向上につながる。
杉本・駒ヶ根市長は、協議会の開催回数をちゃんと把握しているかな。
2、3回の会議でまとめようとしているのではないかな。
コンサル任せではなく、協議会のメンバーが主体的に行動するように、市長の責任で指示しなさい。
市民はちゃんと見ているよ。
2009年05月20日
・下水道をやめて33億節減、飯田市
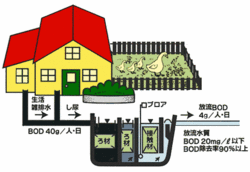 飯田市が下水道事業の見直しに着手しました。
飯田市が下水道事業の見直しに着手しました。下水道管を延々と敷設するこれまでのやり方をやめて、離れた場所は合併浄化槽で処理する合理的な方針転換です。
日本全国で下水道が完備されつつありますが、本来の目的は衛生状態の向上にあったものが、いつの間にか土木・建設としての事業規模を目的としたものにすり替えられてしまいました。
駒ヶ根市を例に挙げると、環境リスク学の権威である中西準子氏に依頼して、下水道施設の効果的な事業案を数十年前に計画しています。
集約されていて下水管網が効果的に配置できる地域と、離散していて合併浄化槽を単独で配置した方が有効な地域が明確に分離されました。
しかし、実現された計画は、どこまでも下水管でつなぐでたらめなものに換えられてしまいました。
なぜかというと、下水管を敷設すると道路掘り下げ、埋め戻すという単純で高収益な土木事業が発生するからです。
人家が離れている田舎ほど穴掘りの延長が無意味に長くなります。
土建屋にはおいしいの一言です。
飯田市では遅ればせながら無意味な穴掘りをやめることで33億円の事業費が圧縮されます。
地方の自治体で計画終了間際に見直しただけでこれだけの削減効果があるんですから、日本全国で計画当初からの無駄は天文学的な金額になると予想されます。
少なくとも20年ほど前から、下水道や集落排水事業は住宅密集地に限って採用するべきで、それ以外は小集落単位や個別単位の浄化槽対応が合理的であると専門家が訴えていました。
これを無視したのが土木利権に後押しされた国であります。
快適な生活を夢見ている市民には、下水道は何の抵抗もなく受け入れられる。
多少の負担は伴っても水洗便所を手に入れたいと願う大多数の庶民の願いに支えられて、下水道事業は闇に触れられぬままに終焉を迎えようとしています。
作ることが目的ですから、今後の維持管理と水質浄化のコストバランスなどは当初から考慮されていません。
本当に必要な下水処理場は多額の維持費を投じてでも永続させることが求められますが、意味もなく作られた施設は廃止されるところがすくなからず出てくると思われます。
下水道普及率が90%を越えたあたりから作るものには、そういった可能性が高いものが含まれます。
下水処理場が本当に必要なのか。
下水が完備していなくても流域の水質が保たれている場所に作られた、説得力のない施設が駒ヶ根市にもあります。
流域ごとに自然浄化力と排水の汚濁度をバランスよく考慮して、無駄な下水処理場をこれ以上増やさないことが求められていると思います。





