2016年07月06日
日向、日陰、木陰の違い

強い日差しを避けるためにすだれなどの日除けを使うと暑さは和らぐが涼しくはならない。
ところが同じ日陰でも樹木の陰に入ると涼しい。
どれくらい違うのか測定しました。
測定したのは家の壁から30センチの空気。
画像の左から木陰、日陰、日向です。
同種の温度計を三か所に配置して測定しました。
見事に5℃ずつ温度差が生じています。
涼むなら人工的な日陰ではなくて自然の樹木が作る木陰がいい。
家の日除けも同じです。
2013年01月27日
・adware win32/fastsaveappを再発させない
Microsoftの Windows 8にあるWindows Defenderが『adware win32/fastsaveapp』を検出するようになりました。
何度クリーンアップ(削除)しても、その都度復活します。
ネットで調べても英文だったり、英文の対策ソフトを勧める内容しかないので、自己流に対策してみました。
結果としてうまくいったのは、次の方法です。
C:ドライブのProgramDataフォルダにある『SaveByclick』というフォルダを削除。
コントロールパネルのプログラムの削除にリストアップされていないから直接削除しました。
並行してWindows Defenderでクリーンアップして、再起動。
これで、再発しなくなりました。
理由は判りませんが、結果は成功です(^_^)
何度クリーンアップ(削除)しても、その都度復活します。
ネットで調べても英文だったり、英文の対策ソフトを勧める内容しかないので、自己流に対策してみました。
結果としてうまくいったのは、次の方法です。
C:ドライブのProgramDataフォルダにある『SaveByclick』というフォルダを削除。
コントロールパネルのプログラムの削除にリストアップされていないから直接削除しました。
並行してWindows Defenderでクリーンアップして、再起動。
これで、再発しなくなりました。
理由は判りませんが、結果は成功です(^_^)
2011年01月09日
・押入れが蓄熱暖房機になる
 蓄熱暖房というと深夜電力を利用した温風暖房機が代表格だろう。
蓄熱暖房というと深夜電力を利用した温風暖房機が代表格だろう。しかし、この暖房機が思いのほか役に立たないことは知られていない。
新築住宅の見学会などでたまに見かけることがあるが、多くの場合、室温の風を噴出しているだけだ。
巨大な蓄熱材を備えた特殊な設備は別として、一般的に売られている蓄熱暖房機は、暖房の立ち上がりを補助する程度の性能しかないと思っていたほうがよい代物です。
蓄熱容量を確認してみれば、判りますよ。
そんな役立たずに多額の出費をするよりも、もっと手軽で効果的な蓄熱暖房の方法があります。
押入れが一番効果が高いのですが、日中の室温の高い時間帯に戸を少しあけておくんです。
こうすると、中の冷たい空気が外に流れ出し、部屋の暖かい空気が押入れに入ります。
すると、押入れの中の布団を暖めます。
夜になって布団を敷くときにほんのりと暖かい。
敷かない布団は、押入れの中で蓄熱材として押入れの裏側からの冷気をやわらげてくれる。
さらに、押入れの内部の結露を無くすという二次効果もあります。
押入れだけでなく、普段は締め切っている収納スペースがあれば、蓄熱暖房の有力な候補になるかもしれません。
暖房が効いている部屋で、収納スペースとの仕切りを開けたときに「ヒヤ~」とした空気が出てくるようなら、有望です。
収納の中身が見えるのがいやだというなら、戸を開ける隙間を少しにしてもいいと思います。
我が家では10cmから15cmほど開けています。
24時間暖房している家庭は除いて、寝ている間に室温の低下がかなり抑えられますよ。
押入れなどの収納が外壁に接しているなら、さらに効果が上がります。
押入れ一箇所で、小型の蓄熱暖房機一台に匹敵するんじゃないでしょうか。
もちろん、暖房を止めたら戸を閉めましょうね。
*今日の太陽光発電量 25.5kwh
・第一発電所 12.5kwh
・第二発電所 13.0kwh
今年に入って最低の発電量でした。
2010年12月30日
・ワイヤーインジェクター
 この画像を見て、何だか分かる人はかなりのメカ通といって差し支えないでしょう。
この画像を見て、何だか分かる人はかなりのメカ通といって差し支えないでしょう。とっても重宝する整備工具ですからね。
『ワイヤーインジェクター』という名称です。
ワイヤー内にオイルを浸透させるためのツールです。
本体にワイヤーを通し、本体穴に潤滑スプレーノズルを差し込んで注入するだけで、さび付いていたワイヤーがスルスルと動きがよくなります。
これからの雪に備えて、除雪に活躍するバックホーのアクセルワイヤーの整備に使いました。
ワイヤー内の油が固まったりさび付いたりで、ワイヤーの動きがものすごく固くなっていました。
アクセルレバーを分解してワイヤーを取り出し、ワイヤーインジェクターを装着します。
オイルを注入したい場合はグリーススプレーを使い、内部を洗浄したい場合はCRC-556のような洗浄作用のある潤滑スプレーを使います。
今回は、ワイヤー内部の洗浄が主目的なので、CRC-556を使いました。
ワイヤーインジェクターにノズルを差し込んで、ワイヤーの反対側から漏れ出してくるまで吹き続けると、錆と古いオイルが溶け出して流れ出てきます。
今まで、固くて動かなかったワイヤーが、スルスルと軽く動くようになりました。
我が家は、舗装された道路から玄関まで70mほどあるので、除雪がかなり手間です。
ほとんどは『私道』ではなくて『市道』ですが、専用に使っているので自力で除雪します。
人力で除雪できる量ではないので、バックホーとフォークリフトで除雪します。
倉庫から市道まで、フォークリフトが出られるように道を作るのがバックホーの役目です。
積雪が厚いとフォークリフトが動き出せないからです。
平地に出てしまえば、ヒンジにバケットをつけたフォークリフトの除雪能力は高く、数分で70mの除雪を終えてしまいます。
年末年始は、全国的に天候が荒れ模様だそうです。
大雪に見舞われるところもあるでしょうが、駒ヶ根の明日の天気予報は『晴れのち曇り』です。
除雪の準備は整いましたが、除雪不要な程度に降ってくれるとありがたいんですがね。
2009年09月22日
・草刈の8枚刃を24枚の笹刃に
 草刈には再生8枚刃を使っています。
草刈には再生8枚刃を使っています。チップソーのチップが飛んで使えなくなった台金を研磨して、8枚刃に形成する。
以前にも紹介したが、その再研磨について新たな方法を考えたので、ふたたび登場です。
8枚刃を草刈機に取り付けたまま正確に研磨するのはかなり難しい。
バランスが崩れて、重心が偏って、振動が増えてしまうからだ。
そこで、8枚刃をディスクグラインダーで、草刈機に取り付けたまま再研磨してもバランスが崩れないし、切れ味も復活する都合のいい方法はないかと試行錯誤してみた。
8枚刃の切れ味は、8枚の刃の先端にある。
石などに当たって先端が丸くなってくると途端に切れが悪くなる。
ならば、刃の先端だけ研磨してみたらどうだろうと考えた。
丸くなった刃の先端を3cmほど長さで研磨してみる。
削った先には小さな刃が新たにできる。(冒頭の画像中央の刃)
この形を見て、ハタッと気がついた。
この小さな刃を全周につけると24枚刃の笹刃になる。
八枚刃は、一枚の刃が大きいので研磨すると誤差も大きくなってバランスが狂う原因になる。
しかし、笹刃は、一枚の刃が小さいので誤差も小さくなってバランスの狂いが最小限に抑えられる。
初めから笹刃を削りだすのは大変だが、八枚刃をディスクグラインダーで研磨すれば出来上がってしまうなら手軽だ。
アサリを付けたり、棒やすりできれいな刃に仕上げるとさらに切れ味は良くなるが、家の周りや田畑の草刈だと石がたくさんあるので、そこまでする必要もない。
ディスクグラインダーで荒く削り出した、なんちゃって笹刃で十分だ。
24枚刃があるといっても、ディスクグラインダーを軽く当てるだけだから、8枚刃を削り込むよりもグンと作業速度が速くなる。
刃の数が多い方が研磨が楽だというのは目から鱗だった。
2009年01月26日
・すきま風はファンヒーター3時間分
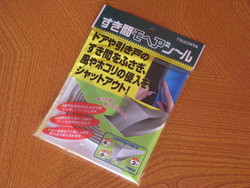 冷え込みが厳しくなってきました。
冷え込みが厳しくなってきました。今朝の気温は氷点下6度。
でも、居間はそんなに室温が下がっていなかった。
昨日、居間の仕切り戸に隙間テープを貼り廻らしたからです。
『すきまモヘアシール』というポリプロピレン製の毛が生えた幅4mm、毛足は4~6mmのテープです。
これを廊下との境の襖と、台所の仕切りのガラス戸に貼り付けました。
ガラス戸は戸車で動くために敷居との間にも6mm程度の隙間があって、ここから冷気がどんどん入ってきていました。
隙間風による冷気は隙間風負荷といい、暖房には大敵です。
標準的な和室では、隙間風は一時間で部屋の容積に匹敵する空気量が外気と入れ替わります。(換気回数といいます)
居間は八畳なので、一時間で64立方メートルの外気が隙間風として入り込んでいる計算になる。
外気との温度差を20度と仮定すると、24時間で8500キロカロリーの隙間風負荷が発生していることになる。
八畳用のファンヒーターの暖房能力(3.2kw)の3時間分に相当します。
高気密高断熱の最新住宅ではそんなに問題になりませんが、少し前の在来工法の住宅は隙間風による暖房負荷はかなり大きい。
戸の立て付けを調整して隙間をなくすことと並行して、優れものの隙間テープを併用すると、かなりの隙間風を防止できる。
ファンヒーターやエアコンのように空気を暖める暖房機を使っている家庭では、隙間風による冷気は暖房効果を特に悪くします。
いわゆる『頭熱足寒』になるからです。
古民家に薪ストーブが似合うのは、雰囲気だけではなくて暖房効果としても一理あるんですよ。
隙間風だらけの古民家では、ファンヒーターでは力不足。
オール電化でエアコン暖房などもってのほか。
お勧めは床暖房(ほっとカーペットも)や薪ストーブなどで遠赤外線暖房。
最低でも昔ながらの反射型ストーブを使いましょうね。
2009年01月19日
・こどもの急な発熱にも慌てないで
 冬はインフルエンザを筆頭に感染症の危険がウヨウヨです。
冬はインフルエンザを筆頭に感染症の危険がウヨウヨです。子どものいる家庭では、突然の発熱でオロオロすることも。
信州に引っ越してきた当日、引越しの荷物も届いていない新しい住処で、深夜に長女が発熱しました。
主な荷物は翌朝に届く予定で、手荷物しかもっていない状態ですから体温計すら持ち合わせていませんでした。
かぜ薬も無い、緊急当番医もわからない、インターネットもない、当時は携帯も無い。
ないない尽くしでできることといったら、子どもの様子を見続けて、適切な対応は何かを考えること。
幸い、うちの奥さんは保母さんなので最低限の子どもの病気への対処法は身につけている。
しかし、パニックになりかけているので落ち着かせるのがわたしの役割。
あの時は本当に困った・・・。
その点今は、いろんな面でサポートが手厚くなってきた。
子どもの様子がおかしくても、困ったときに助けになるサイトが用意されている。 ⇒ 子どもの救急 日本小児科学会
緊急なのか様子を見ていいのかが判断できます。
分からないからとりあえず救急病院へといったコンビニ感覚が小児科救急の現場を苦しめていることを考えると、医療を受ける側が適切な選択をすることは当然求められます。
子どもが大変なんだからといった親側の主張もごもっともだが、不要不急の患者で医者も大変なことを知っておくべき。
大変なのはお互い様なんだから、本当に大変なのか、大変だと思い込んでいるのか、自己判断することも大事です。
『こどもの救急』のはじめの言葉が重い。
このホームページには大きな目的があります。
それは、「小児救急医療受診者を減少させる」ことです。
おかあさん方にしてみれば、「こどもが病気になったとき、いつでもどこの病院でも適切な診断・治療が受けられるようにして欲しい」という思いがあり、この目的を疑問視する方もいるかもしれません。
しかし、小児救急医療は現在厳しい状況におかれており、ぜひとも、今すぐにおかあさん方にご協力いただきたいのです。
まずは現状を知ってください。そして、おかあさんご自身にできることを考えてください。
2008年12月26日
・インフルエンザにナガイモが効く
 ナガイモがスーパーの店頭から姿を消す日が近いかもしれない。
ナガイモがスーパーの店頭から姿を消す日が近いかもしれない。つい先ごろ、朝バナナダイエットでバナナが店先からなくなってしまったが、次はナガイモか。
ナガイモに含まれるタンパク質にインフルエンザウイルスの感染を抑制する働きがある、という研究成果が発表され、長いも業界に衝撃が走りました。
研究は青森県環境保健センター、県工業総合研究センター、弘前大が合同で進めたもの。
ウイルス抑制の働きがあるのは、ナガイモに含まれるタンパク質「ディオスコリン」。
ナガイモの抽出液で動物細胞への感染を調べた結果、Aソ連型、A香港型、B型のいずれにも感染しなかったという。
感染抑制機能は煮沸すると失われるようなので、生でおろしでいただくか、刺身にして醤油をかけていただこうかな。
煮沸するほどの熱を加えなければ、とろろ汁もいけそうだ。
うまくて栄養があり、インフルエンザにも効果があるとなれば、今年の冬は長いもが引っ張りだこになる可能性が高い。
ただし、臨床実験も済んでいないので、弘前大の加藤陽治副学長は「滋養強壮に効くとされるナガイモがインフルエンザに効果があると分かったのは素晴らしいことだが、さらに多様な研究が必要だ」と話している。
まあ、薬と違って副作用の心配がないんだから、予防接種するつもりでどんどん食べようかな。
2008年12月17日
・太陽熱温水器の凍結防止パート2
 先日、太陽熱温水器の水抜きを簡便にする工夫を紹介しました。
先日、太陽熱温水器の水抜きを簡便にする工夫を紹介しました。本体の水抜きはこれで簡単になったんですが、まだ不十分なところを見つけました。
給水管に入ったままの水が凍ってしまうからです。
この管も水抜きできるようにはなっていたんですが、屋外に設置したバルブを閉めなければならなかった。
厳冬期は雪が積もった屋外に出るのがおっくうなので、改良しました。
太陽熱温水器へ給水するバルブと水抜きバルブを、浴室内ですべて操作できるように集約しました。
画像の右側下から給水管が来ているので、右側のバルブを開けると太陽熱温水器へ給水します。
本体にはボールタップがついているので満水になると給水が止まりますが、ボールタップから給水管までは水が入ったままです。
これを抜くには、画像左側のバルブを開けますが、下にバケツを置いておけば水抜きされた水も無駄になりません。
分岐の下にわずかに水が残りますが、浴室内が氷点下になることはないので大丈夫。
お正月などで長期間留守にする際には、屋外の凍結防止栓を閉めれば、ここの水も抜くことができるようになっているから安心です。
この改良で、太陽熱温水器の水をお風呂に入れる一連の動作が、すべて浴室内だけでできるようになりました。
家族には絶賛されました。(この作業は子供と奥さんの役割だからです。)
ちなみに工事費はタダ。
ステンレスの継ぎ手やバルブはかなり高価で、今回使ったバルブ、ニップル、チーズなどで1万円近くしてしまう。
昔の会社勤めで実験に使った廃材をもらってきて、ストックしてあるもので済ませてしまったので費用がかからないんです。
2008年12月15日
・太陽熱温水器の凍結防止を簡便に
 太陽熱温水器の使い勝手を向上させてみました。
太陽熱温水器の使い勝手を向上させてみました。寒冷地である駒ヶ根では、冬季間は太陽熱温水器の内部が凍結する危険があります。
凍結しても直ちに故障するわけではありませんが、装置の寿命は縮まっていると思います。
そこで、冬季は水抜きをすればいいのですが、本体下部の水抜き栓は屋根に上らなければ取り外せないので、面倒だというので放置されることが多いようです。
ここ伊那谷では、一時期大量に設置された太陽熱温水器が不用品となってしまった原因に、水抜きせずに壊れてしまったものが多いと聞いています。
設置した業者のレベルが低いのが一番の原因なんですが、水抜き口から配管をつないで、手元で操作できるようにすればいいことを知らないんです。
寒冷地の太陽熱温水器には、水道の行き管と温水の返り管、それに水抜き管の三本が施工されていなければ、施工業者が無知だと示しているようなものです。
うちの太陽熱温水器も一昨日まではそうしてあったんですが、昨日になって温水の返り管を撤去しました。
水抜き口から給湯するように換えたからです。
この変更によって、給湯すると全量の水が抜けてしまうので水抜きの操作が不要になります。
氷点下まで気温が下がる夜間から早朝は空にしておいて、寒さが和らいだ日中に水を入れます。
本体に水を供給する時の気温に気をつけていれば、凍結する危険はありません。
給湯は始めに低温の水が供給されますが、だんだんと温かくなり、通常のパターンとは逆になります。
全量風呂に入れてしまうので、温かい湯が出てくる順番は関係ない。
給湯器と連結している場合はこの手は使えませんが、風呂の給湯だけに使っている場合は、手間が省かれて凍結防止できるので、とってもいい方法だと思いますよ。






