2009年12月12日
・氷点下10度までは結露しない窓
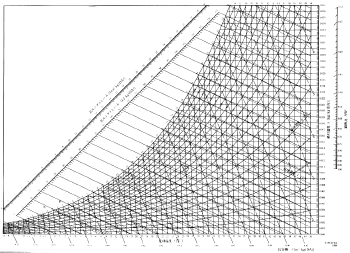 暖かい一日だった今日は、サッシを外して断熱パネルを取り付けた。
暖かい一日だった今日は、サッシを外して断熱パネルを取り付けた。「ポリカ プラダン」という商品名だが、中空のポリカーボネート板のことだ。
掃き出し窓の3か所が今日の作業範囲。
幅3.6mで高さが2.2mの大きな窓が3か所だから、ここだけで冬季の熱損失は5700wに達する。
家全体の熱損失の約2割を占めていた。
冬は結露が激しかった。
中空のポリカーボネート板は全体の厚さが4mmだが、空気層が3.5mmある。
熱貫流率は約4W/(m2・K)で、単体の熱伝導抵抗は0.034(m2・K/W)で試算している。
アルミサッシに張り付けるだけで、複層ガラスよりも優れた断熱性能を発揮する。
当然、結露を防ぐ効果も飛躍的に向上する。
話は変わって、結露を防ぐには高性能の窓に換える派と換気が重要だという理論派がいる。
換気派は飽和水蒸気圧の話を持ち出して、室温が下がれば飽和点を超えた水蒸気は水になるから絶対に結露するという。
しかし、これはまやかしで室内の壁や畳などが湿気を吸い込んである程度は調整してしまうから、計算通りには結露しない。
窓が結露するのは、窓の室内側表面温度と室内の水蒸気飽和温度との関係に尽きる。
簡単に言ってしまうと、窓の表面温度を下げなければ結露しないのだ。
だから窓の断熱で結露が防げる。
部屋の断熱性を上げると結露が悪化することもある。
良くある例では、窓に厚手のカーテンをつけると、外部へ逃げる熱を遮ってくれる。
ところが、カーテンの外側にある窓への熱を遮るから、窓の表面が低温になって結露しやすくなってしまう。
結露を防ぐには、結露している外側で断熱しなければならないことが分かると思う。
さて、大きな窓の断熱が終わって結露もある程度防げる目途が付いた。
しかし、結露がなくなるわけではない。
就寝中を想定して、室温が10度で湿度が60%の場合、外気温が氷点下10度までは結露しないといった条件が付く。
真空ガラスだと氷点下30度くらいまで結露しないようだ。
駒ヶ根が氷点下10度の最低気温になるのは年に一回あるかどうかだから、これくらいの断熱性能があれば十分に結露がなくなる。
ホームセンターで結露防止グッズがいろいろと売られているが、ほとんどが費用倒れに終わる。
結露を止めるには、一通りの自然科学の知識があったほうがいい。
冒頭の空気線図が使えれば、言うことなしだ。





