2009年04月29日
・最高裁が体罰を教育的指導と認定
 教育現場では、子供に対して過剰なまでに気を配っているようです。
教育現場では、子供に対して過剰なまでに気を配っているようです。特に、子供の体に触れる行為は、すぐさま「体罰だ!」とされて、モンスターペアレントによって犯罪者に仕立て上げられてしまうことがある。
そんな現状に待ったを掛けたのが、28日の最高裁判所の判断。
小学校2年の時の「体罰」をめぐって熊本県天草市の男子生徒(14)が同市に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷は28日、「体罰」があったと認定して市に賠償を命じた一、二審判決を破棄し、生徒の請求を棄却した。
第三小法廷は、臨時講師が注意を聞かない生徒の胸をつかんで体を壁に押し当てて怒ったことを「許される教育的指導の範囲を逸脱せず、体罰にはあたらない」と判断した。
判決によると、生徒は小2だった02年、休み時間中に廊下で友達と一緒に通りかかった女児をけり、さらに、注意した講師の尻をけった。
講師は追いかけて捕まえ、洋服をつかんで壁に押しつけ、「もう、すんなよ」としかった。
悪いのは生徒の方ですね。
ところが、生徒は講師から怒られた後に食欲が低下するなどして通学できず、03年2月に病院で心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断された。
その後、回復して元気に学校に通うようになったが、生徒の母親は学校側の説明に納得せず、学校や市教育委員会に極めて激しく抗議を続け、05年に提訴に踏み切った。
典型的なモンスターペアレントだ。
一審と二審は講師の行為が体罰に当たるとし、市が「教育的指導の範囲内だ」として上告していた。
悪ガキにげんこつの一つもできない教育現場の閉塞感は、子供たちを歪めていると思います。
過度な暴力は戒められるべきだが、「身にしみる指導」のすべてを体罰として処罰していたこれまでの流れは見直すべきだ。
子供はほめて育てるものだから、身体へ及ぶ行為そのものが不要とする考え方がある。
それができる人はそうすればいいが、できない人にも押し付けるのは行き過ぎだ。
嫌いだが好例なのが、アントニオ猪木のビンタだろう。
猪木にひっぱたかれても刑事告訴した人は一人もいない。
体罰をされる側が受け入れれば行為としては傷害であっても暴力ではなくなる。(※末尾の事件のようなものは論外)
体罰を敵視する親は、我が家の教育方針を先生に伝えておくべきだろう。
その上で、先生の指導を素直に受け入れられる子育てをしておくべきだ。
教師の指導に従わない子供を学校に送り込んでおきながら、きつい指導に体罰だと抗議するのは本末転倒だからだ。
のびのびとした子育てと放任を履き違えている。
小学校の家庭訪問が一段落したところですが、訪問される先生にかならず告げる一言がある。
「うちの子には、遠慮なく『ゲンコツ』してくれていいですよ」
先生の顔が、ニコッと微笑む。
◇ ◇
くれぐれも、こういう悪質な体罰と混同して論議されないことを願います。
【西淀川女児遺棄】 聖香さんはなぜ死ななくてはならかったのか
2009年02月07日
・福岡の中1自殺に学校は無関係
 福岡で中学一年男子が飛び降り自殺した事故は、学校生活とは無縁と決定付けられました。
福岡で中学一年男子が飛び降り自殺した事故は、学校生活とは無縁と決定付けられました。学校側は6日、「学校生活とのつながりは考えにくい」とする報告書を遺族に提出したという。
遺族は学校側の対応を批判しているようです。
当事者が亡くなっているので真相は闇の中です。
しかし、一人の命が失われた原因を探求することは、教育の質の向上につながるのではないかと思います。
因果関係として念頭に置くのはいいとして、家庭に問題があったと決め付けたり、学校の責任だとして教師に負担を押し付けていては、悲しい教訓が生かされません。
これだけ大きく報道された事故ですから、うやむやにしてしまうというのは難しい。
さりとて、家庭に問題があったと遺族の感情を逆なでするような検証はできないだろう。
だったら、市と県の教育委員会が第三者機関にお願いして、事故に至った経過を客観的に検証してみてはどうだろうか。
家庭に問題があったとすれば、一般論として広く世間に警鐘を発せられるような形に変えて教訓として生かしてもらいたい。
学校にも落ち度があるとわかれば、改善すればいい。
担任や被害者の両親を責めても、事故の教訓は生かされないと思う。
2009年01月30日
・福岡の中1男子自殺に想う
 福岡市で中学一年生が飛び降り自殺しました。
福岡市で中学一年生が飛び降り自殺しました。原因として教師による体罰が取りざたされています。
朝のニュース解説で状況を報道していましたが、なんとなく違和感がある事故です。
最も引っかかったのが、登校する直前に勤務中の母親に10回以上したあたり。
母親の携帯電話におえつのような声を残していたという。
しかし、この時点では父親と一緒に家にいたとなっています。
報道でも、教師である母親だけが登場し、子供が置かれていた状況をつぶさに報道陣に公開するなど、普通ではない様子が伺えます。
教師による体罰は、原則的に禁止されている。
しかし、自殺に結びついたとされる体罰とは、クラスのルールとして定められていた「一週間に二回以上忘れ物をしたらゲンコツ」というものだったそうです。
体罰といえるものかどうか疑問に思います。
事故の背景には、母親と事故に遭われた男子との親子関係が少なからずあるように思います。
報道でも、母親に対し年齢にそぐわない密接な思いが伝えられていた。
専門家も、精神的に弱い子供であったと分析している。
ゲンコツが原因で自殺されたのでは教師も立場がないだろう。
報道は、一方的に教師を犯罪者扱いしているように流れているが、状況をしっかりと把握しないと事実を捻じ曲げてしまうかもしれない。
私も教師を親にもつ身だからなんとなく分かるのだが、社会性に乏しい教師の子育ては偏りが生じやすい。
遺族に鞭打つことは避けたほうがいいと思うが、体罰で犯罪者扱いされる教師の立場を擁護しようとすれば、母子関係や子に与えた母親の教師観なども加味することも必要だろう。
体罰を一切拒否する勢力があるが、現状では極端になりすぎていると思う。
そんな状況の犠牲になった側面も伺えるような気がする。
周囲に翻弄されて短い人生に終止符を打ってしまった中学一年生の男子のご冥福をお祈りします。
※受け取り方には千差万別があると思うので、批判的に読まれた方は無視してください。
ナイーブな問題なので批判的なコメントはなしでお願いします。
2009年01月23日
・メディア漬けのこどもたち
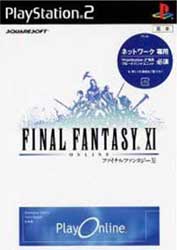 昨日、駒ヶ根市の小中学生を対象にした教育講演会が開催されました。
昨日、駒ヶ根市の小中学生を対象にした教育講演会が開催されました。メディア漬けになっている子供たちに向けたメッセージだったそうです。
参加したのは市内の小学5年生と中学2年生。
たまたま我が家からも二人参加していました。
テレビや携帯電話の弊害について、専門家の話を聞いてきたそうです。
感想はというと、「眠かった・・・。」
話は一生懸命に聞こうと努力したが、ビデオ映像になるとほとんどの子供が眠っていたという。
眠る子も悪いが、子供の興味を引けない講師の話し方にも問題があったようです。
会場に来た子供たちにその場アンケートが実施され、携帯を持っているとかゲームを何時間やっているとか、手を上げて答える。
中学生の半数程度が携帯を持っていると答え、6時間以上テレビを見ている小学生もいたという。
テレビ漬けの子供は、完全に親がそうさせているとしか思えませんね。
一日にテレビを見る時間は二時間に抑えましょうと言われて帰ってきた末娘が言うことに、「二時間も見てもいいの・・・。」
彼女は一週間に一時間見るかどうかです。
姉たちもそれに毛が生えた程度。
一日のうち、学校、部活、家の手伝い、入浴、宿題、睡眠を除くとほとんど時間の余裕が無い。
テレビを見ようと思ったら睡眠時間を削るしかない。
もしくは録画しておいて休日にまとめて見るんですが、これとて休日にも部活が忙しくてできそうでできない。
親が『見せない』と決めてやったほうが、子供たちは安心して生活できるようです。
塾に通って、習い事をし、テレビゲームもやるような家庭の子は、どうやってその時間を作っているんだろうか?
2008年11月23日
・5兆円あれば教育格差がなくなる
5兆円あれば日本の家庭の教育負担がなくなるのだそうです。
家庭の経済力で教育格差が生じている弊害が一気に解消できる。
日本の国力を向上させるために大変に有効なお金の使い方だと思います。
国と地方が支出している教育予算は23兆円。
家庭が負担している分が5兆円。
締めて28兆円が日本の教育に必要となっている。
今、この5兆円の使われ方に偏りがあって、お金持ちは十分な教育を受けさせることができるが、経済的に困窮する家庭では子どもの教育に障害が生じている。
次代を担う子どもたちの教育は、国の重要政策です。
公平で必要十分な教育環境を与えることは、日本の未来に希望を持たせるためにも不可欠です。
個々の家庭に十分な余裕があって、教育環境に偏りがなければ国の関与は限定的であっても良かった。
しかし、現実問題として教育格差が拡大した現時点では、子どもの教育は公共事業として税金で賄うことを決断すべきです。
もちろん納税額は増えるけれども、ほとんどの子育て家庭では実質的な支出額は減少するはず。
出生率の減少を改善するにはうってつけの政策だと思います。
子育ての不安の最たるものは、子どもの教育費だからです。
家庭の経済力に関係なく、子どもの可能性に応じて学力が向上することで、日本の将来の国力が必ず向上すると思います。
「塾に行かなければいい学校に入れない」
こんなことを言う人もいますが、公教育でもまじめに勉強していれば、公立の優れた学校に進めるはず。
そこんところは個人の努力が反映されるので、家庭の経済力の問題とは切り離して考える必要がある。
身近なこととして考えれば、地域で一番学力が高い高等学校と捉えられている伊那北高校に、塾へ通わずに合格した子どもたちが必ずいます。
金で学力を買う塾通いと違って、地道な努力で自力をつける。
教育費が公的負担になれば、求められるのは経済力ではなくて家庭の教育力に変わる。
親も一生懸命に勉強することで日本人全体の考える力が向上すれば、これほどいいことはないと思います。
家庭の経済力で教育格差が生じている弊害が一気に解消できる。
日本の国力を向上させるために大変に有効なお金の使い方だと思います。
国と地方が支出している教育予算は23兆円。
家庭が負担している分が5兆円。
締めて28兆円が日本の教育に必要となっている。
今、この5兆円の使われ方に偏りがあって、お金持ちは十分な教育を受けさせることができるが、経済的に困窮する家庭では子どもの教育に障害が生じている。
次代を担う子どもたちの教育は、国の重要政策です。
公平で必要十分な教育環境を与えることは、日本の未来に希望を持たせるためにも不可欠です。
個々の家庭に十分な余裕があって、教育環境に偏りがなければ国の関与は限定的であっても良かった。
しかし、現実問題として教育格差が拡大した現時点では、子どもの教育は公共事業として税金で賄うことを決断すべきです。
もちろん納税額は増えるけれども、ほとんどの子育て家庭では実質的な支出額は減少するはず。
出生率の減少を改善するにはうってつけの政策だと思います。
子育ての不安の最たるものは、子どもの教育費だからです。
家庭の経済力に関係なく、子どもの可能性に応じて学力が向上することで、日本の将来の国力が必ず向上すると思います。
「塾に行かなければいい学校に入れない」
こんなことを言う人もいますが、公教育でもまじめに勉強していれば、公立の優れた学校に進めるはず。
そこんところは個人の努力が反映されるので、家庭の経済力の問題とは切り離して考える必要がある。
身近なこととして考えれば、地域で一番学力が高い高等学校と捉えられている伊那北高校に、塾へ通わずに合格した子どもたちが必ずいます。
金で学力を買う塾通いと違って、地道な努力で自力をつける。
教育費が公的負担になれば、求められるのは経済力ではなくて家庭の教育力に変わる。
親も一生懸命に勉強することで日本人全体の考える力が向上すれば、これほどいいことはないと思います。
2008年09月05日
・大分教員汚職、親族家族に真犯人
 大分県の教員採用汚職事件で県教委から不正合格とされた教員は20人。
大分県の教員採用汚職事件で県教委から不正合格とされた教員は20人。本年度に限っているところが、腐敗した大分県教育委員会らしい対応ですね。
法的に時効が認められているなら別ですが、確たる証拠が得られないからというのでは、関係者の怠慢でしかありません。
不正採用された教員も、潔く退職するのは14人にとどまる。
臨時雇用の道も残されていますが、投げやりになっている人もいるようです。
同県中部の小学校の男性教員(20代)は西日本新聞の取材に「今は人間が信じられない」とも語った。
この20代の男性教員は、新学期になってから学校に通っていない。ただ「自主退職するつもりはない」。
男性教員によると、8月30日に呼び出され、県教委担当者から「不正があった。合格取り消しです」と告げられ、とにかく驚いた。「県教委の責任について明確にされず、謝罪の言葉もなかった。許せないと思った」と振り返る。
5日の期限になれば、採用取り消し処分になるが、臨時講師の道も残されている。だが、男性教員は「腐りきった大分県の教育界が変わるまで、もうかかわりたくない。取り消しするなら、すればいい。臨時講師にもならない」と話した。 =西日本新聞 9月4日=
さらに同紙の伝えるところによると、
一連の事件を受けて、不正の実態を調べた県教委のプロジェクトチームの調査報告書に、口利きを依頼した者についての詳細な記述はない。このため、県内自治体の教育担当者は「もし親が口利き依頼をしていても、決して子には伝えないだろう。子は親を一生疑うことになる。今回の県教委の対応は、親子のきずなにまで傷を付けたのではないか」と批判した。
最も罪を問われなければならない不正採用を依頼した悪人が明らかにならずに、受動的に不正採用された教員だけが罪をかぶることになってしまっている。
この罪人が家族であり、親族であることがこの事件の不幸な点の一つです。
しかしもっとも不幸なのは、何の落ち度もないのに教育環境を貶められた子どもたち。
たまたま大分県の小中学校の分だけが顕在化しましたが、高校教員を含めて、どこの県でも似たような不正が横行していると専門家は指摘します。
不正を働いた教育委員会が全国各地に少なからずあることで、これからの教育問題の解決に暗雲が立ち込めます。
腐敗した体質を刷新するためには、罪を認めてやり直すことが求められていますが、全国どこの教育委員会も不正を隠蔽することだけに勢力を注いで懺悔する気配は微塵もうかがえません。
一国の最高指導者が責任を全うせずに投げ出すような無責任がはびこった日本ですから、教育者が聖職者であると信ずる楽観論者も小数になってきたと思います。
しかし、このような状況が子どもたちに与える悪影響は甚大です。
不正や腐敗が蔓延する中で育った子どもたちが、正義や倫理をないがしろにすることに無頓着になるのは見えています。
権力者(教育委員会もそのひとつ)たちが腐敗した今の世の中を改めるには、政治権力の構造を抜本的に変えるしかない。
それができるのは、選挙権を有する日本国民以外の何者でもない。
2008年07月17日
・不正採用者の自首を望む
 やっぱりあった。
やっぱりあった。長野県教育委員会による教育採用試験の不正。
長野県の教員採用試験の合否結果について、県教委の山口利幸教育長は16日、事前に要請のあった県議や知人らに対し、受験者本人が知る前に、結果を電話で伝えていることを明らかにしました。
山口教育長は「慣例で長年続いてきた」とし、要請は自身やほかの県教委幹部にそれぞれ年に数件程度あると証言している。
さらに、毎年、県議を含む10人ほどの関係者から、合格発表前に特定の受験者について「よろしく頼む」「何とかならないか」といった依頼を電話などで受けているとも明らかにした。
ただ、「駄目なものは駄目だとはっきり断っている」とし、選考に反映させたことはないと言明している。
虚実を交えた証言ですが、不正の一端が明らかになったことは重要です。
一方、口利きを行った県議側は、田中前県政で口利きが記録として残されることになったので、吉村県政の時代まではやったがその後はやっていないと述べています。
教育長の証言と食い違うが、やっていないという方が嘘をついているのは明らかですね。
そうなると、記録に残らない口利きが横行している実態もあるわけで、その場合はカネも動いている可能性が考えられます。
大分では、不正で昇格した校長たちが自首して問題解明が進みつつあります。
長野県の不正もやがて暴かれ、教育長たちの証言も徐々に崩れていくと思われます。
不正で教師となったものたちは、それまで隠れて身分を保つことが教育者として許されるのか、本人たちの自責の念はないのか。
自首して子供たちに不正を謝罪してこそ教育者としての面目が立つのではないか。
大分県の不正合格者は、失職させられる見込みですが、早くも保護者たちによる救済の嘆願活動が始まっているようです。
心情的には理解できますが、犯罪によって不正に得た身分を保証することは法治国家としては許されざることです。
例えば、不正に取得した実質無免許の優良タクシー運転手の営業継続は絶対にありえません。
似たようなケースで、今回ほど悪質ではないにもかかわらず不正に教師の身分を得たとして解雇された北九州の私立真颯館の調理師教諭→実習無効と未履修救済の不公平
不正によって教員となったものは全員資格剥奪され、解雇されて当然です。
良い教師だからと存続を願うなら、再度教員採用試験を受けて汚名を返上すればいい。
再チャレンジの道は残されていなければならないと思うし、再チャレンジしなければ「悪いことをしても普通にしていれば罰せられないんだ」と、子供たちが犯罪行為を間違って受け止める実例として存在し続けることになる。
反面教師といいますが、犯罪教師が居座り続けることは子供たちにとって、モラルの欠如を刷り込む危険性が高いので決してあってはならないと思います。
長野県や駒ヶ根市にいると思われる「不正採用者」の皆さん。
大分で起きていることを見て、「自分はばれなければいいな」と思ってますか、「悪いことはダメだ。不正は明らかにしよう」と思いますか。
どちらが公職にあるものとしてとるべき道か、よくよく考えて行動に移してください。
2008年07月16日
・子供の個性と学校の特色
 駒ヶ根市内の二中学校が大規模と小規模なのは、問題ではなくて特色だと考える人が少ないのが残念です。
駒ヶ根市内の二中学校が大規模と小規模なのは、問題ではなくて特色だと考える人が少ないのが残念です。平地に点在する立地条件なら規模均衡を目的に通学区をいじって生徒数のバランスをとることも大事だと思います。
しかし、河岸段丘による起伏があり、天竜川という大きな川を挟んで、文化も歴史も地形も異なる地域環境を無視して、数合わせだけの机上の空論では困ります。
10年前から続いている通学路の見直し論議は、生徒の利益は横に置かれ、地元感情や大人たちの意地の張り合いでまともな進展を見てきませんでした。
本来なら中立を保ち、適切な教育環境を作り上げるために調整役となるべき教育委員会も、教育長と教育次長(当時)の恣意的戦略の手先となって、地域懇談で火に油を注いでいたのですからまとまらないのも当然でした。
教育委員会の偽善性は、大分県の一件でやっと周知されるようになってきましたが、少し前までは「教育長がああ言ってるんだからその通りにしないと・・・。」と、絶対視する雰囲気が強かった。
教育長が間違った発言を繰り返しても、「教育長が間違うはずはないから、言っていることは正しい」と、妄信する市民がほとんどでした。
一昨日と昨日、市内の両中学校を通学対象とされる小学生が見学しました。
赤穂小学校の規模の大きさに驚き、東中学校の小ささに救いを求める声が少なくなかったようです。
だからといって小さすぎては困りますから、小規模校としての特色を維持するためにはどういった改革が望ましいのか検討されるべきです。
見学した児童は、自分の個性が生かされる教育環境はどちらなのか、考える機会が与えられて幸せだと思います。
通学区が自由化されている長所が出た結果です。
しかし、新たな通学区が線引きされれば、通学区の選択は出来なくなるはずです。
通学区が全域で自由化されているわけではないので、選択の自由が制限されるのは仕方がないことですが、学校の特色を生かし、それに符合する生徒が集まる機会が奪われるのも、教育機会の平等の点からすると望ましくない。
通学区を考えるときには人数や区域割りにばかり気をとられていますが、忘れてはならないのが子供の特性を生かす教育環境の提供です。
かつて、学校の適正配置を論議する会議で、一部通学区を自由化して生徒数のアンバランスの解消に取り組むべきだと提案したことがあります。
この提案に対して教育長は「絶対にやらない!」と否定しました。
教育長がそう言うならと、会議の流れは通学区の自由化は問題解決の手段としてふさわしくないと否決されます。
しかし、合併に失敗して金の目処がつかなくなると手のひらを返すように、通学区を自由化した対症療法に切り替えました。
なぜ、かたくなに通学区自由化を拒んできたのかは聡明な方ならお分かりだと思いますが、教育長は小規模校を低学力校だと嘘を流布してまで廃校に追い込むつもりでしたから、自由化して東中の良さが赤穂地区に広まっては目算が狂います。
東中学校の良さに惹かれて通う生徒が増えては、廃校に追い込めずに新設校の存在意義が危うくなる。
教育長を妄信している方々は、「教育長は悪いことをしないからそんなことはない」、と思い込んでいますが、不都合な事実から目を逸らしているだけのことです。
当時の教育次長が仕組んで、教育長はそれに乗った形で策略は進められたのですが、状況から察すれば後ろで操っていたのは中原・前市長ということになりますね。
中学校をめぐる負の歴史を抱えたままで、子供たちのためを考えた検討が進むとは思えません。
どこかで膿を出し切らないと。
2008年07月11日
・教職員不正採用はどこにでもある
 大分教育委員会で明らかになりつつある教員採用不正は、教育界全体の腐敗をあぶりだすかもしれません。
大分教育委員会で明らかになりつつある教員採用不正は、教育界全体の腐敗をあぶりだすかもしれません。各地の教育委員会は「わが県(市町村)では、ありません」と断言しているところもありますが、多くは『出てこないと信じたい』。
多かれ少なかれ、どこでも教員採用の不正は行われていると考えるのが普通で、それが表ざたにならないと信じているのが教育委員会の本音でしょう。
大分は余りにも大掛かりだったために、不正システムの制度疲労が進み、隠し切れなくなったのだと思います。
不正システムが『健全に』稼動しているところでは、国会議員の口利きを頂点に、県議、市議、市町村長、有力者、金持ち、・・・、などによる不適格な人材の押し付けが機能しているのだと思うと、教育の崩壊もうなづけます。
文部科学省の幹部が、収賄で懲戒免職になるご時世ですからなおのことです。
どこにでもあるとなると程度の違いはあれ、長野県にもあるし駒ヶ根市にあると思われます。
教育関係者は「ない」と言うでしょうが、あっても無いというのが決まりですからまったく信用できません。
信用されるためには、「当教育委員会の不正の実態はこの程度です」と正直に出すことが求められます。
今回は教員の採用試験ですが、市職員の採用もまったく同じ不正の背景を抱えているはずです。
駒ヶ根市でカネが動いたかどうかは知りませんが、コネがものを言うとはもっぱらの噂ですから。
採用試験を100%情報公開し、採用者の【裁量】が及ばない透明性の高い採用システムに改めるべきです。
公務員は、不正のおかげで公職についているのではないことを証明する義務があると思います。
**関連ニュース検索
大分県教委の教員採用汚職 google
2008年07月10日
・学校の良さは部活動の数ではない
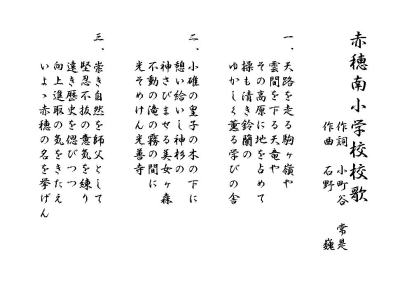 学校の良さは部活動の数ではない。
学校の良さは部活動の数ではない。駒ヶ根市の中学校通学区をめぐる問題を考えるときに、大事なポイントだと思います。
駒ヶ根市に2校ある中学校は過大規模校と小規模校との違いがあり、過大規模校の赤穂中学校で教室の不足や校風が荒れるなどの問題が深刻化していました。
そこで、通学区を変更して、一方の東中学校に通う生徒を増やそうと検討が進められています。
最も重要なのは、赤穂中学校の過大規模解消です。
次に考えなければならないのは、小規模校から過小規模校へと生徒数の減少が予想される東中学校の生徒数増加策です。
ところが、駒ヶ根市教育委員会は、すぐに問題をすりかえてしまい「東中学校の過小規模化を食い止めるための通学区変更」に論点を移そうとします。
これは、頭である教育長の偏見がそうさせているのだと思いますが、緊急の課題と短期的な将来の課題の区別がついていません。
赤穂中学校の生徒数を減らすためには、思い切った通学区の変更が必要であり、地元にも問題の深刻さを伝えて論議してもらう必要があります。
ところが、赤穂地区には通学区変更に根強い反対があるので、『東中学校が困っているから助けてやろう』と目先を変える戦術に出ます。
以前の通学区変更が失敗したときも同じことをやりました。
問題の本質を理解せず、根本的な解決策を見出せない駒ヶ根市教育委員会の無能振りにはほとほと困り果てています。
さらに問題の本質は、通学区もさることながら市内の住宅開発に何の計画性も見出せない駒ヶ根市の街づくりの無策が影響しています。
生徒数のアンバランスは、過疎が進む中沢地域と住宅開発が多い赤穂の一部地域の人口変化からもたらされています。
過疎を食い止めるには良好な住宅開発が不可欠ですが、駒ヶ根市は何の対策も打ってきませんでした。
生徒数減少の根本的な原因がまちづくりの失敗にあることを隠し通学区の問題にすりかえるのは、教育委員会の偏見と失政を認めようとしない駒ヶ根市の理事者が責任転嫁するためです。
「東中学校に行くと部活動が少なくなるからいやだ」、こんな声があるそうです。
大きい学校になればなるほど部活動の数も増えますが、その大きい学校に問題が多発しているから今回の問題が発生しました。
小さな学校は部活動は少ないけれど、それを補って余りある教育環境のよさが売り物です。
大きい学校の部活動の多さを『既得権』と考えるのは止めて、より良い教育環境とは何かを真剣に見つめなおせば、部活動の数など何の障害にならないことに気が付くはずです。
それと、もうひとつの根本的な課題に校歌があります。
駒ヶ根市にある「赤穂学校」(赤穂小学校、赤穂東小学校、赤穂中学校、そして赤穂南小学校)すべてで同じ校歌が使われています。
こんな馬鹿げたことやってしまう駒ヶ根市の教育行政のあり方そのものが、一般的(駒ヶ根以外の)社会から異質となっているのだと思います。
駒ヶ根の教育常識は社会の非常識だということに、市民が気が付くことが先決です。







