2008年05月31日
・駒ヶ根市長の公約がやぶられる
 杉本市長の選挙公約がまたひとつ破られました。
杉本市長の選挙公約がまたひとつ破られました。駅前にあるアルパ子育て交流支援室を、公約では「無料化する」としていましたが果たされませんでした。
これまで日額制だったものが、月額もしくは年額に変更されるとともに値下げされたことはいえ、これでは「無料」には程遠い。
新聞報道などを拝見すると「利用料を廃止」「使用料を無料化」といった記述が目立ちますが、これは市長がマスコミを通じて『無料を印象づけさせたい』との思いが反映されたものだと思います。
「日額の利用料は廃止して無料にしたから『無料化の公約』は達成された」とするならば、杉本市政は『ごまかし市政』とのレッテルを貼られることになります。
月額100円の利用料を取ることにどれだけの意味があるのか疑問です。
アルパの施設は無料だったときには多くの親子で毎日大賑わいでした。
中原前市長が子育て切捨て政策に踏み切った影響で有料化された途端に、利用者は急激に減少したことが明らかになっています。
正確な実績は不明ですが、アルパの子育て交流支援室の利用者は10~20人/日程度なので、延べで600人/月と見込まれます。
半分が入れ替わると見積もっても月額3万円、年額36万円の収入を得ることの効果と、無料にして誰でも気兼ねなく利用できる安心感と、どちらが市民のためになるのか。
駒ヶ根市の教育行政は、先日も紹介した中原教育長がトップに君臨したままの状態であり、偏った考え方が目立ちます。
子育て10か条を決めて市民に押し付けたり、給食費滞納を根絶するためだとして連帯保証人を強制するなど、頭ごなしの高圧的なやり方が増えてきました。
アルパの施設を無料化せず、相応の負担は続けるべきとした背景にもこうした駒ヶ根市の教育行政の暗い影があるのだと感じます。
市長は代わったが、教育長は中原前市長の時代のまま、副市長は市の職員も驚愕したという市役所内部からの登用に終わってしまった。
杉本市長が、長いお役所勤めの経験から「嘘も方便」で行政を操れると考えているとしたら大間違いです。
役人のトップと市民のリーダーはまったく責任の重さが違う。
口で言っていることと本音が異なる今の杉本市政では、行き詰る日は遠くない。
情報公開の必要性を熱弁し、市民に本音を語ることの必要性を説いていた『市長候補 杉本幸治』はどこへ行ってしまったのだろうか。
それとも、今が本当の杉本幸治市長の実態なのか。
田中前知事の失敗を教訓に『正直すぎるのはだめだ』とばかりに、村井県政を真似た『ごまかし行政』を目指しているとしたら、市民協働はお題目で終わると言っておきたい。
2008年05月30日
・地域のエネルギー資源を捨てずに
 上伊那のごみを焼却する施設の建設候補地が近く決定します。
上伊那のごみを焼却する施設の建設候補地が近く決定します。伊那市に建設することは、ほぼ確定しているようですが、用地の絞込みの段階では地元の強い反対もあり、今後の紆余曲折が考えられます。
一見すると民主的な手法で進められている今回の論議も、点数化していることがすなわち科学的とは至らない問題点を含んでいます。
さらに、問題なのは、建設されようとしている施設があくまでも「ごみ焼却」を念頭の置いていることです。
時代を先取りするセンスを取り入れるならば、「ゴミ」という固定概念から解き放たれ『エネルギー資源』の活用施設の建設へと、視点を変えることが可能となります。
ゴミを減らす努力がもっとも必要ですが、市民一人一人の意識が低い現状では「ごみゼロ」はまだ先の目標とせざるを得ません。
近い将来にはゴミはなくなり、資源の二次利用方法として社会に受け入れられる日が来ると思いますが、それまでの”つなぎ”も必要です。
単なるごみ焼却施設でなく、次代へのつなぎに相応しいテクノロジーを取り入れるとしたら・・・。
ヒントになる技術はすでに実用化されています。
バイオマス発電施設を公開──国内最大規模
現在のように一次利用で終えたら「ゴミ」とされる社会から、このような資源の二次利用施設との連携を考慮した社会へとスムーズに移行させることが求められていると思います。
ごみ焼却場に隣接して廃熱利用の温水プールを作ったから二次利用だといって勘違いしているものも多く見受けられます。
処理施設のエネルギーが余っているからつくり足した温水施設と、エネルギー需要がある施設に隣接して処理施設を作るのでは、違いがはっきりしないかもしれませんが、効果はまったく違います。
上伊那に建設が予定されているごみ焼却施設が作り出すエネルギーを効率的に利用できる施設が伊那市にあります。
しかし、その場所は建設予定地から意図的に排除されました。
用地選定委員でもある伊那市議の強い意向が働いています。
「自分の地元には絶対持って来させない」
もっとも適切な場所に施設を作るとの理念は、最初からゆがめられています。
そもそも、市民主体となるはずの用地選定委員会で市議が1/3を占めていることが、伊那市以外の一般常識からすれば異常です。
市議会の力で用地を決定しても、市議会の責任で決定したことにはならないのですから、責任逃れの方策としては良く考えられていると感服します。
2008年05月29日
・駒ヶ根市の中学校は振り出しに
 駒ヶ根市の中学校問題がやっと振り出しに戻りました。
駒ヶ根市の中学校問題がやっと振り出しに戻りました。通学区が適切でないために、二校ある中学校の生徒数に大きな違いが出ていました。
かつて駒ヶ根市では赤穂中学校が荒れ放題となり、過大規模校による弊害だとして「赤穂中学校の生徒を東中学校に受け入れてもらおう」という機運が高まりました。
子供たちのためならばと、東中学校PTAも前向きの意向を示していたところへ、赤穂中学校側の一部から「通学区を変えるのはいやだから東中学校本体を赤穂に近づけてしまえ」という、驚天動地の意見が出されました。
荒唐無稽な意見と排除されるかと思いきや、当時の市長や教育長は大乗り気。
(注記:市長は代わったが教育長は現在も居座ったままです。)
一気に、東中学校を移転させるための市民啓蒙活動がスタートしました。
市民に向けた懇談会では、教育長が先頭になって現在の東中学校には問題があり、移転新築しか解決の道はないと洗脳します。
挙句の果てには根拠のないデマを発言します。
市民からの質問
「過小規模校になると、教員が非免許の教科を教えることになるが、非免許の教員から教科を教えてもらった場合、生徒の学力はやはり落ちるのか。」
教育長が応える
『統計的にでます。技術家庭科や美術などは、才能のある子供たちも、専門の先生に教わらないために、伸びないことは当然起こりえます。』
県の教育委員会にも問い合わせましたが、統計的なデータはなく、教育長の個人的な先入観であることが裏付けられています。
(その当時に問い合わせたのは現在駒ヶ根市長となった杉本氏)
さて、紆余曲折あって駒ヶ根市を中心とした合併工作が失敗すると、「道路を作るだけで手一杯なので新中学校は無理です。」と白旗を揚げる始末。
子供たちの教育のためだといってきたのは真っ赤なうそで、合併特例債という「旨い話」に乗るための手段の一つに過ぎなかった。
子供たちを出汁に使った心を病んだ教育長も、前市長と共に葬り去られると期待したのですが、杉本市長は何も考えているのか留任させた。
教育者としてあるまじき行為をもみ消しにせず、むしろその矢面に立たせ続けることで、教育長として犯した罪を背負わせたまま茨の道を歩ませることを選択したようです。
やるじゃないか杉本市長。
2008年05月28日
・モラル低下を促進するdocomo
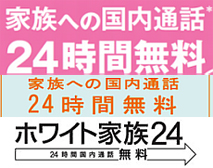 今朝の朝刊、docomoの新聞広告に強い違和感を覚えました。
今朝の朝刊、docomoの新聞広告に強い違和感を覚えました。堤真一演じる社長が女子社員と並んで椅子に腰掛け、携帯で会話する設定です。
「社長、どうして直接話さないんですか?」
「いいじゃない、タダなんだし」
携帯電話の害悪が社会問題となっているこの時期に、携帯の弊害のひとつとして槍玉に上がる「直接会話の減少」を逆手に取った企業モラルが問われる広告です。
さらに付け加えれば、機械を通じて話をすれば、無駄なエネルギーを消費することで温暖化防止に逆行する。
NTTに潜在する社会モラルの低さが顕在化した一例で、携帯を売り込むためには手段を選ばなくなった、かつての巨大企業の崩落の前兆のような気がします。
社会モラルの低下は、この「いいじゃない、○○なんだし」に由るところが大きい
快楽、快適のためにはモラルや責任といったものが軽んじられる。
情報機器の売り込みにモラルが低下すると、加速度的に波及効果が現れると思われ、危機意識を高める必要を感じます。
2008年05月27日
・松くい虫防除で子供に健康被害
 松くい虫を防除するための薬剤散布で470人超の児童が健康被害を訴えました。
松くい虫を防除するための薬剤散布で470人超の児童が健康被害を訴えました。出雲市内の児童や生徒473人がマツクイムシ防止の農薬空中散布が原因とみられる目のかゆみなどを訴えた問題で、市内の15の小中高校と市は26日、子供たちを病院に連れていくなどの対応に追われた。
県内ではほとんどの市町村が農薬の空中散布を取りやめる中、出雲市の散布量は突出して多く、市民からは「これを契機に空中散布をとりやめるべきだ」との声が出ている。=5/27読売新聞=
松くい虫防除の空中散布は、長野県でも中止されています。
一定の効果があるとされているものの、二次被害の甚大さを考えれば中止は当然です。
しかし、ヘリコプターによる広域の空中散布は取りやめになっているものの、無線ヘリを使った限定的な空中散布や、地上から空中に向けての薬剤散布は続けられています。
松くい虫の被害は、マツノザイセンチュウが寄生することに起因し、マツノマダラカミキリが媒介主とされて駆除の対象になっています。
詳細はネットで調べていただくとして、結論としては「防除に成功した例はない」というのが定説です。
そのため、重点的に保護する必要があると認められた「貴重な松」のみが薬剤で防御しているのが現状です。
松くい虫防除の薬剤が松くい虫のみに働くことはなく、今回の事故(事件?)のように人体に影響が出て初めて顕在化しました。
体の比較的大きな人体にも影響があるのですから、さらに小型の小動物や昆虫には甚大な被害が生じていると予想されます。
目先の利益に目を奪われて自然界に大きな被害を生じている恐れがあるのです。
駒ヶ根市でも防除に毎年3千万程度の費用をかけて防除しています。
しかし、将来的な防除効果を高める樹種転換は2006年度で途絶えてしまっています。
事業評価も「対策を講じなかった場合どうなったかは正確には分からないが、間違いなく被害が拡大していると思われる。」
正確にわからないのに「間違いなく」被害を防いでいると断じているあたりにお役人体質が現れています。
松林の将来像を市民と共有し、いかにして樹種転換を実行するのか、ビジョンなしの現状は役所の怠慢の側面があります。
「よく分からないけどこれしかできません」では、大事な地域の自然環境を任せるには力不足です。
5年後、10年後、20年後、50年後、100年後の構想を示し、的確な対策がとられるように、市長のリーダーシップが問われます。
今回の出雲市の事例があったことで、学校から数キロ以内の薬剤散布は当面見合わせるのが妥当でしょう。
少なくとも風下に学校が存在する場所や時期には絶対にやってはいけませんよ。
2008年05月26日
・裁判の責任能力否定は人権無視
 裁判官による刑事責任の判断で、犯罪者(被告)が無罪になることがあります。
裁判官による刑事責任の判断で、犯罪者(被告)が無罪になることがあります。今月22日にも、横浜地裁が、傷害罪などに問われた男性被告(40)の判決で、刑事責任能力を認めた2件の精神鑑定を退け、覚せい剤使用以外の起訴事実を無罪としました。
公判前と公判中に実施された精神鑑定で、医師は責任能力を一部または完全に肯定しているにもかかわらず。
横浜地裁の永井秀明裁判官は判決で「妄想や意識障害の程度は著しい」と判断し、判決は3つの罪を無罪とする一方、覚せい剤取締法違反罪について有罪を言い渡しています。
一方、東京都渋谷区の会社員、三橋祐輔さん(当時30)殺害事件で、殺人と死体損壊・遺棄の罪に問われた妻、歌織被告(33)の判決公判で、東京地裁(河本雅也裁判長)は、「犯行時に責任能力はあった」と判断し懲役15年(求刑同20年)を言い渡しています。
公判で鑑定医2人が「犯行時は心神喪失状態」と報告、責任能力が争点になったが、裁判所は証拠を総合判断し、有罪と結論付けた。
判決理由で河本裁判長は、2人の鑑定医の鑑定結果を「被告は矛盾なく幻覚体験を語っており、犯行時に幻覚症状があったとする報告は信用できる」と認めた。
しかし、公判で示された他の証拠から、歌織被告が離婚を望み、夫との生活に絶望的になるなど犯行動機が明確なこと、犯行状況も殺害目的で頭だけを狙っていること、犯行後に遺体を切断して証拠隠滅を図ったことを指摘。
「殺害行為は被告の意思に基づいていた。犯行時の精神障害は現実感の喪失など犯行の実現に影響を与えたが、責任能力を否定する程度ではなかった」と述べている。
この二つの異なる裁判所の判決は、『罪と罰』の違いにあるように思えます。
前者は、法律の適用に主眼を置き、罪が問える責任能力の有無を法解釈した法律家としての判断です。
後者は、犯した行為の重大さを社会通念と照らし合わせ、それ相応の罰を与えた裁判官としての判断。
責任能力が裁判の駆け引きに使われることを疑問に思う人は少なくないと思います。
責任能力の有無にかかわらず犯罪行為があり、犯罪被害者は存在する。
被告が無罪とされた場合に、悪行の報いを受ける対象がいなくなってしまう矛盾。
法律学的に犯罪者の責任能力を判断することは大事だと思いますが、それとは別に犯した行為の報いは受ける仕組みが必要だと思います。
責任能力のない犯罪者にも再犯の危険があることを考慮すると、罰を与えつつ地道に「犯罪を犯してはいけないよ」と頭に焼きつかせる必要がある。
犯罪被害者の立場からすれば、責任能力がある場合の刑事罰に相当する、責任能力が問えない被告に対する『懲罰』が併設されていて当然だと思います。
罪の意識はなくても犯した罪に応じた罰は与えられるのが当然だと思うのですが。
因果応報は良くも悪くも平等に、善因善果・悪因悪果・自因自果としてかえってくるべきもののはずでは。
責任能力がないから無罪といわれたら、それは一面では責任ある人間として認められなかったことになる。
犯した行為で責任を負わされることも、大事な人権だと思いますよ。
2008年05月25日
・凶悪犯逮捕よりもパトカー検挙
 緊急走行中のパトカーが速度違反で摘発される。
緊急走行中のパトカーが速度違反で摘発される。こんな、うそのような本当の話が多発しているというから、縦割り行政の弊害というのはどこにでもあるものだと思う。
警視庁の機動捜査隊員が「指名手配犯が現れた」と通報を受け、隣県に急行した際、速度違反自動監視装置(オービス)に撮影されて違反切符を切られた。
「外国人が連れ去られた」という一報で、捜査1課の捜査員が、犯人グループが向かった隣県に捜査車両で急行した。このとき、緊急走行した捜査車両のほとんどが違反とされたこともある。
緊急自動車の最高速度規定は昭和35年の施行令制定以来、一度も改正されていない。
逃走を阻み、自分で手錠をかけるという刑事魂はよく分かるが、道路事情は変わっておらず、安全面からは今も妥当な規定」というのが交通サイドの言い分だ。
一方、捜査サイドは「車の性能が上がり、逃走車両の速度も速くなっており、時代に即したものに」と規定速度の引き上げを求める。
警察内部で足並みはそろわないが、「仮に規定を20キロ引き上げたところで、150キロで逃走する車両は追跡できず、根本的な解決にはならない。
隣県に逃走するケースも考えれば、迅速に包囲網を敷けるよう各警察間の連携などを強化するべきではないか」(ベテラン捜査員)という声も根強いという。=5/24 産経新聞の記事抜粋=
『杓子定規』 : 一定の標準で強いて他を律しようとすること。形式にとらわれて応用や融通のきかないこと。」(広辞苑)
警察に課せられた使命の重さに照らして運用すればなんてことないのに、社会の利益より自分たちの部署の面目を立てることに熱心なお役人体質があるんですね。
2008年05月24日
・2050年の70%削減を前倒しする
 2050年に日本の二酸化炭素(CO2)排出を90年比で70%削減するために進めるべき12の提案を、国立環境研究所などの研究チームが22日発表しました。
2050年に日本の二酸化炭素(CO2)排出を90年比で70%削減するために進めるべき12の提案を、国立環境研究所などの研究チームが22日発表しました。太陽光や風力などの地域エネルギーを最大限に活用することや、歩いて暮らせる街づくり、低炭素型製品を開発・販売する企業経営などを挙げ、産業など部門ごとの削減分担も示しています。
長野県は、村井知事が地球温暖化を目指していることもあって、削減の努力は放棄しています。
マイナス6%の目標は捨て去り、京都議定書の約束期間である2012年に3.5%の増加という、とんでもない目標を掲げています。
足りない分は、森林税を徴収するから森が吸収するとした破天荒な論法でごまかしています。
村井知事はやらなくても、村井を選ばなかった賢明な県民は自助努力を続けます。
我が家は、すでに一般家庭(5人家族)の90年比で58%の削減を達成しています。
2050年に70%削減というさらに高いハードルが示されましたが、この先42年で12%の上積みですから簡単なことだと思っています。
しかし、先延ばしするのではなくできる限り前倒ししようとする努力が大切なので、今後のスケジュールを考えてみます。
12%の上積みは、CO2にすると500kg弱に相当します。
削減のターゲットは、電気(720kg)とガソリン(740kg)に絞り込まれます。
解決策はズバリ、太陽光発電と電気自動車。
今すぐにでもやろうと思えばできますが、数百万円の投資が必要となり、「誰もが気軽にできる」金額ではありません。
我が家の温暖化防止策の特徴は、『普通の家に暮らし、最小限の投資で最大限の効果を得る』にあります。
先日取り付けた太陽熱温水器は、40万円のシステムを4千円で取り付けたから、市価の99%offでした。
太陽光発電が低価格となって普及が進み、頻繁な更新時期を迎えるのは10~20年後だと思うので、その頃になれば低価格で太陽光で発電した電気を動力源にして自動車を走らせることが可能になると思います。
冒頭の画像のような太陽電池パネルを搭載した自動車が普及する可能性もある。
「外食に出かける回数を一回我慢した」程度で、温暖化防止の効果をあげるためには、知恵と工夫が必要です。
さらに、それを後押しする政治の先見性が求められます。
自民党の利益だけを考えて、「総選挙はできるだけ先延ばしにするぞ」と、使い古しの小泉元首相が檄を飛ばすような政党に任せておけるはずがありません。
地球の未来を壊すも救うも、今の私たちにゆだねられています。
2050年の目標である70%削減を前倒しするために一番必要なことは、自民党を政権から引きずりおろすことだと思います。
2008年05月23日
・金が知恵を阻害する
 先日、杉並区の公立中学校で塾の講師による特別授業の問題を取り上げました。
先日、杉並区の公立中学校で塾の講師による特別授業の問題を取り上げました。私立なら経営戦略として認められても、公立となれば税金の使い方として適切かどうかが問われます。
そもそも、公立校には適正な教員配置がされているはずです。
杉並区の特定の中学校だけ教員の配置が不足しているということはないと思います。
では、塾講師の存在は何を意味するのかというと、教員の資質が不足しているのことを示します。
教員の資質が不足しているので、外部から塾講師を雇い入れるのはひとつの解決策として考えられると思います。
しかし、塾講師は営利事業ですから、その費用をどの財源で支払うのかが問われます。
適正に配置された教員が「お手上げ」な分を塾講師がカバーするのですから、教員の給与を減額して塾講師の費用に充当するのが当然ですね。(そうなってるとは思いませんが)
一方、北区の神谷中学校では教員の隠れた資質を引き出すことで、外部に頼らない補習授業を実現しています。
「土曜パワーアップ教室」といわれていますが、教員が担当科目以外のものも指導し、個別指導が必要な「落ちこぼれ」には、地域の高校生に助力を願う、画期的なシステムです。
画一化された授業だけに安住していた教師が、他教科を教える必要に迫られたことで新たな学習意欲に目覚め、高校生も教えることで自分の学ぶ姿勢を振り返る機会が得られます。
教える側も教えられる側も、実りある成果が期待できます。
これぞ、知恵を使った教育の見本だと思います。
金の力で解決する杉並の中学校と、知恵で克服する北区の中学校の差は、学んだ中学生の人間性に現れてくるでしょう。
金が知恵を阻害する典型として、教育関係者は真摯に自分たちのこととして受け止める事態だと思います。
2008年05月22日
・紫外線の害、プールにも日よけ
 紫外線の悪影響がやっと社会に認知されてきたのだな~と思います。
紫外線の悪影響がやっと社会に認知されてきたのだな~と思います。◇ ◇
男も日傘の夏が来る お肌の大敵UV対策
5月から8月は1年で紫外線が最も強い時期。気になる紫外線から肌を守るにはUV対策グッズが欠かせない。今年のUV対策グッズの傾向を探った。
この時期は日傘や帽子などが百貨店などに勢ぞろい。中村区の名鉄百貨店では「涼感」をキーワードに売り場を展開。
(中略)
人気商品は日傘。有名ブランド「バーバリー」の晴雨兼用タイプ(1万5750円)、「ボルサリーノ」の同タイプは3万6750円と高価だが「50代以上で帽子をかぶるのは嫌という方が購入されます」と売り場担当者。
メンズコスメ売り場では「クラランス」「クリニーク」など5ブランドのUVカット効果があるローションやリップクリームを取り扱う。報道などで紫外線の弊害が広く知られるようになり、ゴルフや海などのアウトドアだけでなく、普段の生活でも使用する男性が増えているという。=5/19名古屋タイムズ=
長女が保育園に通っていた10年前に、「紫外線は子供の皮膚には危険だから園庭に日よけを作って守りましょう」と保護者会で提案したら、
「何バカな事言っているんだ。日光浴は医者だって勧めてるくらい必要なものだぞ」と相手にされず、さらに「自分たちだけでやってらいいじゃん」と小ばかにされたものでした。
ごく一部の保護者は先進地のオーストラリアの取り組みなどから学習して、長袖を常時着させたり、帽子に工夫したりと我が子を守っていましたが、保育園では「さあ皆さん、裸になって目いっぱい太陽を浴びて元気になってね」とやる始末。
年月が過ぎて末娘が保育園の年長の頃には、徐々に紫外線の害が理解されてきたので、一斉に砂場に日よけを作りました。
(行政の理解はまだなので保護者が自腹で)
まだ、プールに日よけを作るまでには至りませんが、市役所の職員が日よけ傘をさして通勤するようになれば、「自分だけ紫外線から守っているが、子供たちを紫外線にさらしていて申し訳ない」と気がつく日も近いでしょう。






