2009年10月09日
・A3プリンターを買い替えた
プリンターが壊れてしまった。
正確に言うと、プリンターのカートリッジ(インクヘッド)の故障だ。
古い機械なので、そろそろ買い替え時だから修理するよりも買い替えることにした。
A4用のBJF660VとA3用のBJF6100を併用していたが、カートリッジは兼用していた。
発売から9年と10年経過しているから、なかなかよく使った方だと思う。
BJF660Vは新製品で買ってずっと使って、BJF6100は仕事でA3が必要になったので数年前にオークションで確か1万円くらいで手に入れた。
さて、修理しようと思うとカートリッジにはカラーとブラックとフォトの3種類あって、一個4000円くらいだから全部換えると1万2千円だ。
最近はA3プリンターが2万円台で買えるから、プラス10000円で新型が手に入る。
さらに、カートリッジは数ヶ月前に交換したばかりで、修理してもまたすぐに故障する危険性が高い。
プリンターは文章や図面を印刷するのがほとんだから、適した機種は何がいいかなと調べたところCANONのix5000が最有力だ。
EPSONにもよさそうなものはあるが使い慣れたCANONの方が安心して使えるかな。
安く手に入れるならオークションだが、手元に来るまでに時間がかかるし、大きいものだから送料が高い。
そこで、amazonで購入することにした。送料無料だしね。
22,590円だった。
さて、今まで使っていたプリンターの処分はどうしよう。
捨てるには、粗大ごみの手数料が必要になる。
ダメもとでオークションに「ジャンク品」として出品してみた。
結果は、両機ともに引き取り手が現れました。
付属パーツなども含めると6000円が手元に入ってきました。
金額はたいした問題じゃなくて、何がしかの用途に使い続けてもらえることがうれしいですね。
正確に言うと、プリンターのカートリッジ(インクヘッド)の故障だ。
古い機械なので、そろそろ買い替え時だから修理するよりも買い替えることにした。
A4用のBJF660VとA3用のBJF6100を併用していたが、カートリッジは兼用していた。
発売から9年と10年経過しているから、なかなかよく使った方だと思う。
BJF660Vは新製品で買ってずっと使って、BJF6100は仕事でA3が必要になったので数年前にオークションで確か1万円くらいで手に入れた。
さて、修理しようと思うとカートリッジにはカラーとブラックとフォトの3種類あって、一個4000円くらいだから全部換えると1万2千円だ。
最近はA3プリンターが2万円台で買えるから、プラス10000円で新型が手に入る。
さらに、カートリッジは数ヶ月前に交換したばかりで、修理してもまたすぐに故障する危険性が高い。
プリンターは文章や図面を印刷するのがほとんだから、適した機種は何がいいかなと調べたところCANONのix5000が最有力だ。
EPSONにもよさそうなものはあるが使い慣れたCANONの方が安心して使えるかな。
安く手に入れるならオークションだが、手元に来るまでに時間がかかるし、大きいものだから送料が高い。
そこで、amazonで購入することにした。送料無料だしね。
22,590円だった。
さて、今まで使っていたプリンターの処分はどうしよう。
捨てるには、粗大ごみの手数料が必要になる。
ダメもとでオークションに「ジャンク品」として出品してみた。
結果は、両機ともに引き取り手が現れました。
付属パーツなども含めると6000円が手元に入ってきました。
金額はたいした問題じゃなくて、何がしかの用途に使い続けてもらえることがうれしいですね。
2009年09月21日
・価格対効能に優れた虫さされ薬
 家の南側の庭は、草ぼうぼうだ。
家の南側の庭は、草ぼうぼうだ。草取りが面倒だから、というわけではなくて、庭を通り抜けて縁側から涼しい風を取り込むためです。
樹木と草の間を吹き抜けた風は、家の中に涼しさを取り込み、夏の暑さから解放してくれる。
ただし、良いことばかりではなくて「やぶ蚊」も発生する。
蚊取り線香やベープは体に良くないので使わないから、夜は蚊帳のお世話になっていた。
ところが、最近は蚊帳を張るのが面倒になってきたので、蚊に刺されることが時々ある。
そこで虫さされ薬の出番だ。
これまでは、医者で処方された薬を使っていましたが、在庫が底をついたので市販の薬を試すことにしました。
とりあえず定番の「ムヒS」(池田模範堂)をサンロードにて398円で購入して使ってみたが、効き目は今一つ。
カインズホームセンターに買物に行ったついでに店内の薬局で見つけたのが「スキンロックS」(雪の元本店)。
ムヒと同じく、かゆみを抑えるジフェンヒドラミンが1%配合されていますが、ムヒが18gで398円だったところがスキンロックSは20gで398円とちょっとお得でした。
使った感じは、ムヒよりはかゆみが抑えられるが医院で処方されるオイラックスHよりも効きが悪いようだ。
アメリカンドラッグやツルハドラッグにも行ってみたが、安くて効きの良い薬は見つからない。
残るはファミリードラッグだということで、仕事のついでに農道沿いの店舗に寄ってみた。
すると、オイラックスHと同等のクロタミトンという成分が10%配合された塗り薬が20gで398円で特売されていた。
タクトクリーム(佐藤製薬)という名称で、第二医薬品に指定されている。
これはなかなか効きがよい。
ところで、効きがよい薬と今一つの薬では何が違うのか。
かゆみを抑える成分がジフェンヒドラミンとクロタミトンと異なる。
前者は抗ヒスタミン剤だが、後者はよくわからない。
しかし、ほかに配合された成分に特徴があることに気がついた。
効きの良いと感じる薬にはヒドロコルチゾンやデキサメタゾンが含まれている。
これはステロイド剤だ。
医者に処方された虫さされの薬には知らされずにステロイドが含まれていたのだ。
私は子供の時から「じんましん」で、末娘は小さなころからアトピー性皮膚炎でステロイド剤のお世話になってきた。
だから、その効能も身に染みて知っているが、副作用の怖さも併せ持つことに敏感だ。
たかが虫さされの薬、されど頻繁に使う常備薬だ。
ステロイドが含まれているなら、頻繁な長期使用は避けなければならない。
そういえば、ネットでタクトクリームを調べているときに、
[用法] 大人及び2才以上の小児:1日3~4回限度として、患部に適量を塗布してください。3才未満の小児:使用せず、医師にご相談ください。
というのが目についた。
薬の効能書には1日数回患部に適量を塗布、としか書かれていない。
ステロイド剤は「ステロイドを含みます」と、はっきりと分かるように表示してほしいですね。
2009年09月19日
・運動会でギブスをした子が目について
 秋晴れの休日でしたね。
秋晴れの休日でしたね。地元の小学校では運動会が開かれました。
最近、太鼓の奏でる音が頻繁に聞こえてくるので、神社のお祭りの練習でもしているのかと思っていました。
ところが、今日、小学校の運動会を見物に行ったところ、太鼓の音はここから聞こえていたのだとわかりました。
風にのって運ばれてきた太鼓の音が、すぐ近くで鳴っているように聞こえていたのでした。
周囲に騒音の発生源がない田園風景ですから、いろんな音が聞こえてきます。
穏やかな日には、数キロも離れているJRの鉄橋の音が聞こえてくることもあります。
街中だと当たり前に聞こえてくる「暗騒音」が非常に小さいので、微細な音でも耳まで届くようです。
運動会を見ていて気になったのが、腕の骨を折るけがをしている子供が目立ったこと。
けがの理由はいろいろあるのでしょうが、か細い腕を見ていると、体を張った遊びが不足しているように思えます。
幼少時から家庭の手伝いなどで労働に勤しんでいると、筋力はつくし骨も丈夫に育つ。
塾通いやゲームで体を目いっぱい使っていない子供は、比較的にひ弱に育つと考えてよろしいかと思います。
学校に子供の肉体増強のことまで負わせるわけにはいかないので、やはり家庭の働きかけが重要になるでしょう。
家庭の手伝いをさせれば骨を折ることがないとは言いませんが、丈夫な骨を作るには疲れて倒れるほどに体を使う経験が必要だと思います。
田んぼや畑を見回しても、子供が手伝いをしている姿はなかなかお目にかかれません。
せっかく、子供の体を作るために役に立つ機会があるのに、もったいないなと思います。
不登校の児童が長野県が全国トップで、駒ヶ根市も長野県内でトップクラスという不名誉なデーターが公表されました。
この問題を子供と話していると、「学校よりも家のほうが居心地がいいからってこともあるよ」と、子供の視点での鋭い分析がありました。
裏を返すと、「うちだと不登校になると毎日の手伝いの作業が大変だから学校に行ってた方が楽だよ」ということらしい。
不登校の原因にもいろいろあって、一筋縄では解決の糸口は見つけられないと思うが、家よりも学校のほうが楽というのは、昔の農家なら当たり前のことだったと思うので、もしかすると昔の方が不登校になる要因が少なかったのかもしれない。
うちの子も、いじめにあったり、友達の関係がこじれて悩んだ時期があったようだ。
幸いにも、それでも学校の方が楽だと思っていたから不登校にはならなかったと言っている。
親として喜んでいいのか・・・。
2009年06月07日
・一駅族
 通勤中に“一駅分”歩く人のことを「一駅族」と言うらしいです。
通勤中に“一駅分”歩く人のことを「一駅族」と言うらしいです。運動靴など健康関連グッズを販売するビーウェルが、東京23区内に勤務する20代から50代までのビジネスマン600人を対象に、『平日の運動に関する意識調査』を実施した。
平日「ウォーキング」をしているという人を対象に、どの時間帯にウォーキングしているかを聞いたところ【通勤時】が最も多く30.5%、続いて【帰宅時】が17.0%という結果に。
【通勤前】(10.6%)の早朝や【帰宅後】(15.2%)よりも多いことがわかった。
同社は、この調査結果を踏まえて「仕事後に皇居周辺などでランニングをする人も増えてきているといわれていますが、“通勤・帰宅時に、いつも利用する駅のひとつ隣の駅から一駅分歩く”というような、効率的で気軽な運動をするビジネスマンが増えている傾向にあるのでは?」と“一駅族”という言葉を使いながら解説している。
◇ ◇
東京でサラリーマン生活を送っていた頃は、この「一駅族」の先鞭をつけていました。
毎日の帰り道、一駅前で下車して1.3kmを徒歩で。
その頃住んでいた団地が駅前だったので、ほとんど歩けないことがネックだったからです。
会社も地下鉄駅の真上にあって、駅入り口と会社のドアとの距離は5mほどしか離れていない。
だからと行って運動不足ではなかったです。
会社帰りには一日おきに公営のスポーツジムに通ってました。
バイクのサンデーレーサーだったこともあって、基礎体力つくりには熱心でした。
ジムでの運動前と後では体重が1~2kgは落ちていましたから、かなりハードなトレーニングでした。
その帰りに一駅歩いたのは、電車内で固まった筋肉をほぐすクールダウンの意味合いが強かったです。
あのころに比べて、今は歩きませんね。
毎朝、田んぼの水を見に行くのと、畑の様子を見に出かけるくらいです。
ぐるっと一周しても500mもないから大した運動にはならない。
日常の運動量は、都会にいたころに比べたら雲泥の差があるように感じます。
ただし、草刈りの時だけは過酷な労働ですね。
運動と違って体に負担がかかるばかりで、健全な負荷にはなかなかなりません。
根をつめて何日も刈りつづけていると、腰が悲鳴をあげてしまってぎっくり腰と同様の状態になったこともありました。
作業と運動を兼ねた、田舎に適したものは何かないですかね。
2009年05月03日
・日本タンポポ化計画2009
 日本全国で、繁殖力に勝る西洋タンポポが勢力を拡大している。
日本全国で、繁殖力に勝る西洋タンポポが勢力を拡大している。都市部ではその傾向が顕著になっているという。
2005年に関西で調査されたデータによると、外来種の比率は6割を超えている。
大阪や兵庫では7割を超えるというから、都市緑地(公園など)では西洋タンポポが大きな顔をしているようです。
一方で、池の土手・林や林縁では在来種が過半数を占め、里山的な環境に在来種が多く分布していることになっている。
里山的な田舎に暮らすものの実感としては、外来種の存在は、関西のデータよりも多いように思えます。
特に、繁殖域の拡大は外来種のほうが早い。
家の周りでも、見る見る在来種が劣勢に立たされてしまっていく。
そこで昨年から、庭(30坪ほど)に限って西洋タンポポをすべて駆除してきました。
この効果は目覚しく、庭に自生するタンポポの9割以上が在来の日本タンポポに変化しました。
両者の繁殖力は大きくは違わないので、ちょっと力を貸してやれば日本タンポポも繁殖力を復活させる。
しかし、庭以外では圧倒的に西洋タンポポばかりが目に付く。
こちらは感覚的に9割以上が外来種だ。
2009年02月12日
・運がいいのも考えもの
 子どもとバドミントンをやってみた。
子どもとバドミントンをやってみた。あいにく風が強かったので、機械を外に出して広くした倉庫の中でプレーしようとしました。
ところが、ラケットのガットが緩んでいて、シャフトがラケットにくっついてしまう。
競技用のラケットではなく、遊び用に作られたものだから直してまで使う価値はないかもしれませんが、フレームは壊れていないので、つい、直してしまう。
今のものは、子どもたちが一日がかりで張り直したものだが、直してからしばらく経っているのでやり直しの時期に来たようです。
プレーはあきらめて、早速直すことにしました。
張られていた糸をすべて取り除き、新しく釣り糸を使って張りなおします。
でも、張り方を知らないので試行錯誤の時間のほうがかかってしまいます。
何とか、一本がものになったのは一時間後。
子どもが受け持ったもう一本は、時間切れで翌日以降に先送りです。
ところが、半分程度張った子ども担当の一本に、重大な欠陥が判明しました。
糸が交互になっていないところがあったんです。
うちの子曰く、「えっ!交互にやるの?知らなかった・・・。」
交互になっていなかったのは一本だけなんですが、それ以外の十数本は偶然に交互になっていたというんです。
こんなところで運を使うなよ。
2009年02月11日
・火は怖い
 最近、火災発生の緊急放送が頻繁に入ってくる。
最近、火災発生の緊急放送が頻繁に入ってくる。それに呼応して、火の取り扱いに注意する放送も増えている。
ひどいときには、注意の放送が入ったすぐ後に火災が発生することもある。
オーストラリアでは同国史上最悪の山林火災が発生している。
車で逃げ遅れた被災者が発生するほどの猛威を振るっている。
自動車の速度で逃げ切れないほどのスピードとは、いったいどれほどの勢いなのだろうか。
昨日、千曲市で発生した林野火災は、伐採した竹を野焼きしていた火が飛び火したことが原因という。
竹は油分を含んでいるので火力が強い。
薪ストーブにたくさん入れて燃やすとストーブを痛めることもあるそうだ。
その竹を大量に燃やしたら延焼すると想像できないから、林野火災につながるのだろう。
火の動きを侮って、自らも犠牲になる悲惨な事故も少なくない。
火遊びをする機会が減った今の子どもたちでは、さらに危険度が増しているように思う。
子どもは遊びから学ぶことが多いので、大人の監視下で適度に火遊びさせることも大切だと思います。
幸い、海で育った私は、頻繁に火遊びができたので、火の特性や動きを身をもって感じた。
延焼の恐れがないので、子どものすることとは思えないほどの大焚き火を楽しんだ。
もちろん怖い思いも数え切れないほど体験している。
だから、今は土手焼きでも恐々と慎重の上にも慎重になる。
火事は恐ろしい。
我が家の身内も火事で亡くなっている。
火を侮ることのないようにお互い注意しましょう。
2009年01月21日
・おもちゃ図書館が閉館
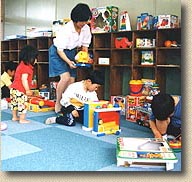 駒ヶ根市の『おもちゃ図書館』が閉館した。
駒ヶ根市の『おもちゃ図書館』が閉館した。ボランティアで運営され、25年間こどもたちにおもちゃと戯れる楽しさを提供してきた同会の活動に敬意を払いたい。
駒ケ根市赤須東の市障がい者センター高砂園で、母親の子育て支援として毎月第1、第3火曜日の2回開いてきた「おもちゃ図書館」。
住まいが手狭な家庭には大変に重宝されていたようです。
最終日に3歳の子どもと訪れた母親は、昨年から通っているといい、「アパート住まいで、あまりおもちゃを買うと置く場所がなかったので助かっていた。子どももいろんなおもちゃで遊べてよかったのに―」と閉館を残念がっていたという(長野日報より)。
子どもと保護者の交流の場として、市が2003年に駒ケ根駅前ビルアルパに子育て交流支援室「きっずらんど」を設けたことで、同図書館以外に公的な母親の交流の場ができ、利用者が減少してきた。
しかし、同施設が05年度に有料化されてからは同図書館は増加傾向にあった。最近では平均10組が利用していたという。
中原前市政の「ハコモノ行政」の不備を補ってきた子どもたちへのソフト事業は、民間の有志がしっかりと支えてきた。
行政の不備を補ってきた有志の活動は、大変に有意義なものでした。
おもちゃ図書館には、少しばかり協力させていただいていたので、活動が終わってしまうことに一抹の寂しさがある。
駒ヶ根の子どもたちに、おもちゃを通じて楽しみを与えたいという活動の一端に寄与できたことを誇りに思います。
2009年01月20日
・薪ストーブと災害の備え
 薪ストーブって楽だなと思うこの頃です。
薪ストーブって楽だなと思うこの頃です。薪が十分に用意できているからなんですが・・・。
部屋の暖房は薪ストーブだけです。
朝、火を入れると、後は時々薪を足すだけで暖め続けてくれる。
薪を無造作にストーブの中に放り込むだけで暖かくなるところが、タンクを持ってきてポンプを使って継ぎ足す灯油ファンヒーターなどと比べて楽だなと感じます。
灯油ファンヒーターの弱点は、電気がないと使えないところにあります。
昔ながらの反射型や円筒型の直接燃焼させるものを除いて、現在主流となっている暖房機はほとんどが電気に頼っている。
オール電化の住宅は、冬季の災害時には悲惨だろうな。
家を建てるときに、災害に遭遇した場合の対応力を考える人は多いと思います。
しかし、考える対象が家の耐震基準だったり、防火性だったりと、災害そのものへの住宅の耐久力に限られる。
震災で停電し、断水し、ガスも止まった状態で数日間を生き延びるための備えは対象外。
まあ、いつ起こるか分からない災害に備えなくても、来たときはあきらめると言われてしまえばそれまでです。
こういう考えの方が圧倒的に多いでしょう。
でも、そうやって無責任にしていると、結局は行政に頼ることになって、その負担がめぐりめぐって自分の懐に響いてくる。
それだったら、ロハスとも言われる自然に共存した生き方をしたほうが、気持ちも懐も豊かになるのではないだろうか。
災害に遭遇してガスや電気が無くなっても外で煮炊きできるようにするには、年末の餅つきが予行練習になる。
冬だったら暖房に困るので、薪ストーブがあれば田舎なら燃料の調達も何とかなる。
灯油は、田舎ほど入ってこないので当てにならない。
ストーブに薪を入れながら、災害のときに足りないものは何かあるかなと、時々シミュレーションしてみる。
唯一困るのが飲み水の長期的な確保だ。
短期間なら雨水が貯めてあるし、サバイバル用の浄水器でたいていの水は「ろ過」できる。
長引いたときのためには、太陽光発電と風力発電の電力で地下水を汲み上げるのがいいかな、なんて考えてみる。
2008年12月31日
・年末は大忙し
 年末は家中の大掃除と、設備の総点検で大忙し。
年末は家中の大掃除と、設備の総点検で大忙し。女性陣はおせち料理を作りつつ、大掃除に専念。
男性陣といってもわたし一人ですが、家中の建具のたてつけ、家具金物への注油、コンセントのほこり除去など、これまた猫の手も借りたいくらい。
中でもコンセントのほこり除去は、火災予防としても重要です。
留守宅で火災が発生する原因の第一は漏電で、コンセントプラグにたまった埃が発火することが多いそうです。
差し込んだままになっているプラグの刃に埃がまたがって導電して火が出るらしい。
家中のコンセントを抜き差し、掃除して回ります。
次に動きや、立て付けの悪くなった建具の調整です。
隙間が生じた障子や襖は、下端を削って隙間をなくす。
戸車がついているガラス戸は戸車に注油するとともに、戸車の取り付け高さを変えて隙間がなくなるように調整します。
注油といえば、動きが渋くなったドアノブも分解して油を差します。
ついでにキコキコ音がするようになった蝶番にも油を。
機械ものと違って油が残っていると生活で手が汚れてしまうので拭き取りには気を使います。
暖かい日中には、帰省で活躍する車の手入れ。
タイヤの空気圧は適正値に。
また、豪雪地域を抜けるのでワイパーが硬くなっていたりすると視界不良で困る。
ウィンドウォッシャー液も凍結しないようにたっぷりと原液を入れる。
やり残したことはないかな・・・。
心配しつつも今年も今日で終わりです。
みなさん、来年もよろしくお願いします!!
良いお年を。







