2017年10月27日
JCNの充電アプリは高速道路で重宝する
ジャパンチャージネットワーク(JCN)が良いアプリを作ってくれた。
10月10日よりリリースされた「高速充電なび」。
高速道の急速充電器が使われているか否か(満空情報)はリーフの車載ナビでも判るが、あとどれくらいで終わるのかまでは分からない。
JCNのアプリは地図の経路上に充電器の満空情報を表示するとともに、使用開始時刻も表示されるので待ち時間の目安がつけられる。
到着までの時間と予想される残りの充電時間を見比べて充電のために立ち寄るかどうかを判断できる。
ただし、充電待ちしているEVが控えているかどうかまでは分からない。
比較的空いている充電施設はアプリの利用価値は高いが、混雑する充電施設だと実態を把握できるとは限らない。
そこで役立つのが、過去3ヶ月の利用実績に基づく時間・曜日(平日/祝休日)別の混雑状況や点検や故障による休止情報を充電スポット毎に参照できるところだ。
バッテリー容量が増えたEVは、空いている充電器で「ついでに充電」すればどんどん遠くへ行けるようになる。
充電器の利用先が分散することで。充電器の全体としての利用率も向上する。
ぜひ使いたいアプリだ。
「高速道路の充電スポットに特化したナビアプリ『高速充電なび』のリリースについて」
http://www.charge-net.co.jp/news/20171010_01_appli.html

10月10日よりリリースされた「高速充電なび」。
高速道の急速充電器が使われているか否か(満空情報)はリーフの車載ナビでも判るが、あとどれくらいで終わるのかまでは分からない。
JCNのアプリは地図の経路上に充電器の満空情報を表示するとともに、使用開始時刻も表示されるので待ち時間の目安がつけられる。
到着までの時間と予想される残りの充電時間を見比べて充電のために立ち寄るかどうかを判断できる。
ただし、充電待ちしているEVが控えているかどうかまでは分からない。
比較的空いている充電施設はアプリの利用価値は高いが、混雑する充電施設だと実態を把握できるとは限らない。
そこで役立つのが、過去3ヶ月の利用実績に基づく時間・曜日(平日/祝休日)別の混雑状況や点検や故障による休止情報を充電スポット毎に参照できるところだ。
バッテリー容量が増えたEVは、空いている充電器で「ついでに充電」すればどんどん遠くへ行けるようになる。
充電器の利用先が分散することで。充電器の全体としての利用率も向上する。
ぜひ使いたいアプリだ。
「高速道路の充電スポットに特化したナビアプリ『高速充電なび』のリリースについて」
http://www.charge-net.co.jp/news/20171010_01_appli.html

2017年08月20日
EVへのネガティブキャンペーンが必死
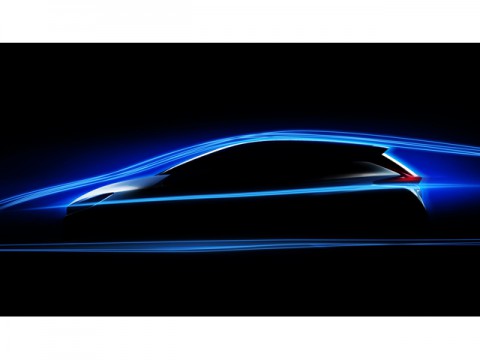
電気自動車を巡る話題は国際的に“花ざかり” だが、コトはそれほど簡単ではない
世界的に内燃機関車から脱却して電気自動車に移行する流れが加速している。
その流れに逆行して一部の報道や論評は電気自動車の粗さがしに必死だ。
背後にいるのは苦境に立たされる内燃機関自動車産業だろう。
《賑やかな電気自動車の話題だが、課題は極めて多い》
には突っ込みどころが満載だ。
「自動車の走行段階でCO2排出がゼロであっても、発電によってCO2を大量排出するのでは何の意味も無い。」
⇒日本に限っても少なくとも再生可能エネルギーによる14%は多いなる意味を持っている。
近い将来、再生可能エネルギーは消極的な安倍政権でも20%以上に増やし、実際は30%を超えるだろう。
加えて、家庭用電気自動車は屋根に載せた太陽光発電との親和性が高く、ZEHの一端を担う存在として電気自動車のバッテリーは存在価値が高まることは必然だ。
EU諸国における再生可能エネルギーの比率はさらに高く「何の意味もない」の根拠はまったく存在しない。
「満充電からの走行距離の問題、バッテリー寿命などの技術的問題、給電施設などインフラの問題などだ。まだまだ普及段階に入ったとはいえない。」
⇒確かに現時点では課題が完全に解決されたとは言えないが、解決までに必要な時間はかなり短いと考えていいだろう。
2020年ごろに到来する電気自動車の隆盛期には走行距離の問題、バッテリー寿命などの技術的問題は課題では無くなり、インフラの問題は需要の高まりに応じて整備されるはずだ。
「化学に依存する電池は半導体などと異なり、急速な性能向上は難しい」とする専門家の意見もある。
⇒これはひどすぎて、返す言葉もない・・・。
内燃機関産業は電気自動車の足を引っ張ることで延命を図るのではなく、産業構造の変化に順応することの方が重要だ。
それができなければ淘汰されるのは産業の歴史が物語っている。
2016年10月12日
2030年で内燃機関エンジン車は淘汰
 ドイツ、2030年までに内燃エンジンを搭載したクルマの販売禁止を要求
ドイツ、2030年までに内燃エンジンを搭載したクルマの販売禁止を要求2030年以降、ドイツではEVかFCV以外の自動車は販売できなくなる。
EU全体に広がると予想されることから、日本の自動車メーカーも対応を余儀なくされるだろう。
14年も余裕があると考えるのは浅はかで、日産リーフを除くすべての国産メーカー車が欧州販売できない状況が14年後に迫っていると捉えるべき。
EVに後ろ向きだった国産車メーカーの開発姿勢が急変すると予想される。
ユーザーとしては選択肢が増えることは大歓迎だが、悲惨なのはガソリンスタンドの経営者だろう。
EV充電では採算が取れるとは思えないし、水素ステーションになるには莫大な資金が必要になる。
日本政府はエネルギーインフラの革新に向けて本気で取り組む必要に迫られる。
歴史に自動車革命と記されるであろう2030年をどうやって迎えるか。
エネルギー産業の変貌に注目だ。
2016年09月29日
電気自動車は今がお買い得

充電インフラが拡充された割には世の中を走っているEVが少ない現状は、EVユーザーにとって恵まれた環境だ。
確かに、黎明期の自動車だからバッテリーの劣化など扱いづらい側面はあるが、不足する機能をユーザーが補って乗りこなす楽しみがある。
EVを乗りこなせなければPHV(PHEV)という選択肢もあるが、でかいガソリンエンジンを積んだ車をEVというのは無理がある。
BMW i3(レンジエクステンダー)は補充電専用の小さなエンジンを積んでいるだけだからEVの仲間と言えるが、エンジンの出力で直接間接を問わず走行可能な車はEVではないというのが日本のお役所(国土交通省)の認識だ。
でも、統計上は混ぜこぜにされてしまうところがおかしいと思う。
そんなEVは事業者にとっては、違う使い道があるという。
リンク先は高級車のテスラを会社の経費で乗ればお得感が出るという話。
「電気自動車が実は今こそ買い時と言える理由」
零細な自営業者にはできない芸当だが、リーフに乗ってからEV関連の調査事業を請け負うことがある関係で、これまで乗っていた車(ガソリン車)以上に経費へ計上できる比率が増えて、やっぱりお得になっている。
出来の悪いEVでもお得感があるのだから、これから世に出る優れたEVを買わない理由は無くなってくる。
2016年09月18日
各社2017モデルEVは横並び
 シボレーのコンパクトEV『新型ボルト』の航続距離が383kmに! 日産リーフを210kmも上回る
シボレーのコンパクトEV『新型ボルト』の航続距離が383kmに! 日産リーフを210kmも上回るシボレーの新型EV「ボルト」が発表された。
航続距離は386kmで日本円で383万円だという。
先に予約販売が始まったテスラのモデル3は350km以上で400万円。
こちらはオートパイロットが標準装備されるようだ。
現行の30kWhリーフで迎え撃たなければならない日産に勝ち目はない。
劣勢を挽回するための40kWhリーフの販売は2018年だというし、後発なのに性能上の優位は伝えられていない。
このままだとEVメーカーの勢力図は2017年に大きく塗り替えられそうだ。
日産が手をこまねいていれば三番手に下がることが予想される。
世界各地に累計で35万台走っているリーフは数年で鉄くずと廃バッテリーになってしまう。
新型の走行用リチウムイオンバッテリーの載せ換えサービスが始まれば、2018年以降まで乗り続けることも可能だが、サービス開始の発表が遅くなるほどに現リーフユーザーが他車に乗り替えてしまうだろう。
日産は万全を期してギリギリまで新しい情報を提供しない。
失敗を恐れているのだろうが、リスクがあってもテスラが支持されているEV市場の実情を分かっていない。
新型EVは、これこれの性能を目指して何年何月に発売する予定で、それまで現車に乗り続けられるように、何月からバッテリー載せ換えサービスを始める予定という感じで、不確定な「予定」でいいのだから期待をいだかせることが重要だと思う。
2016年04月18日
東北道にも急速充電
東北の高速道路をEVで連続走行できるようになります。
菅生PAよりも北は充電施設が未整備だったが、2016年内には津軽SAまで完備される。
NEXCO東日本はEVへのサービスに消極的だったが、やっと重い腰を上げたようだ。
まだ十分とは言えないが、北日本の高速道路でも何とかEVで移動できる環境が整い始めた。
これで終わりではなく、すべてのSA・PAに充電施設を完備し、さらに可能な限り二台以上の急速充電器、難しい場合でも滞在用中速充電と経路用急速充電の併設にも着手してもらいたい。
ユーザーの声が大きいほどNEXCOの動きが良くなる。
「NEXCO東日本 お問い合わせ先」
http://www.e-nexco.co.jp/contact/
菅生PAよりも北は充電施設が未整備だったが、2016年内には津軽SAまで完備される。
NEXCO東日本はEVへのサービスに消極的だったが、やっと重い腰を上げたようだ。
まだ十分とは言えないが、北日本の高速道路でも何とかEVで移動できる環境が整い始めた。
これで終わりではなく、すべてのSA・PAに充電施設を完備し、さらに可能な限り二台以上の急速充電器、難しい場合でも滞在用中速充電と経路用急速充電の併設にも着手してもらいたい。
ユーザーの声が大きいほどNEXCOの動きが良くなる。
「NEXCO東日本 お問い合わせ先」
http://www.e-nexco.co.jp/contact/
2016年03月16日
30分充電の無駄を検証
彦根まで400kmを往復した時のこと、帰りの恵那峡SAは冬のEVにとって鬼門だからたっぷりと充電したくなる。
だが、阿智PAに急速充電器が設置されたことで充電環境は劇的に改善した。
ところが、充電環境の特性を理解できないと充電に無駄な時間を浪費し、他のEVにも迷惑をかけてしまう。
その一例が今回のグラフ。

恵那峡SAでSOC40%から30分きっちり充電しても8kWhに満たないが、恵那峡SAでSOC30%から20分、次の阿智PAで10分の合計30分だと13kWh以上充電できる。
その差は5kWh以上。
同じ充電量なら15分も充電時間が短くできる。
恵那峡SAで10分、阿智PAで5分充電すると恵那峡SAで30分粘ったと同じだけ充電できる。
自分も早いし、充電待ちが短くなり他車の時間も短縮できる。
夏と冬で代表的な車種の消費電力例を掲示して欲しいと要望している理由はここにある。
残念ながらNEXCOは理解を示さない。
高速道路を利用するEVの利便性向上に寄与するはずなのだが。
だが、阿智PAに急速充電器が設置されたことで充電環境は劇的に改善した。
ところが、充電環境の特性を理解できないと充電に無駄な時間を浪費し、他のEVにも迷惑をかけてしまう。
その一例が今回のグラフ。

恵那峡SAでSOC40%から30分きっちり充電しても8kWhに満たないが、恵那峡SAでSOC30%から20分、次の阿智PAで10分の合計30分だと13kWh以上充電できる。
その差は5kWh以上。
同じ充電量なら15分も充電時間が短くできる。
恵那峡SAで10分、阿智PAで5分充電すると恵那峡SAで30分粘ったと同じだけ充電できる。
自分も早いし、充電待ちが短くなり他車の時間も短縮できる。
夏と冬で代表的な車種の消費電力例を掲示して欲しいと要望している理由はここにある。
残念ながらNEXCOは理解を示さない。
高速道路を利用するEVの利便性向上に寄与するはずなのだが。
2016年03月05日
生ごみがEV用電気に
新潟県長岡市に設置された急速充電器の電源は生ごみだ。
生ごみがEV用電気に 充電器設置
長岡市が設置 発酵ガス利用し発電
生ごみを発酵させてメタンガスを作り、これを燃料に発電する。
施設の電力と充電器で消費した残りは電力会社に売電している。
身近な資源の有効活用でエネルギーの自給自足が成り立っている。
多くの自治体で採用されている生ごみ処理方法は減量のための焼却だが、資源である生ごみを化石燃料を注入して燃やし、二酸化炭素にして大気に放出している公害施設だ。
一部は熱を回収しているものの処分を優先して、貴重な資源を無駄にしていることが多い。
急速充電施設の数が充足してくると、ユーザーが選べるようになって来る。
選択肢の一つにエネルギー源がある。
ナビや充電器検索サイトの施設情報に「電源」が追加されることを期待している。
生ごみがEV用電気に 充電器設置
長岡市が設置 発酵ガス利用し発電
生ごみを発酵させてメタンガスを作り、これを燃料に発電する。
施設の電力と充電器で消費した残りは電力会社に売電している。
身近な資源の有効活用でエネルギーの自給自足が成り立っている。
多くの自治体で採用されている生ごみ処理方法は減量のための焼却だが、資源である生ごみを化石燃料を注入して燃やし、二酸化炭素にして大気に放出している公害施設だ。
一部は熱を回収しているものの処分を優先して、貴重な資源を無駄にしていることが多い。
急速充電施設の数が充足してくると、ユーザーが選べるようになって来る。
選択肢の一つにエネルギー源がある。
ナビや充電器検索サイトの施設情報に「電源」が追加されることを期待している。
2016年02月17日
NEXCOの上から目線
EVが連続して高速道路を走れない区間は東北を中心に全国に点在するが、季節限定で電欠する区間は判りにくいので厄介だ。
NEXCO中日本だと駒ヶ岳SA~梓川SA区間が危ない。
冬以外なら何とかなるが、暖房や曇り取りに電力を使う寒い時期はかなり厳しい。
さらに、バッテリーが劣化したEVだと、過去には通り抜けられたはずだったのに現状は困難だったりする。
NEXCO中日本に、EVが置かれた現状を報告し、対策を依頼した。
その返事が
「現時点で駒ケ岳SA~梓川SA間の急速充電器設置計画はございません。」
にべもない。
十分なバッテリー残量を確保するための目安に消費電力の掲示を進言したのだが、それについても
「EVの車両側の条件として、それぞれの車種で電費が異なりますので、どれだけの電池残量(充電量)があればいいといったものを一律的に掲示することは適切でないと考えています。
ユーザーそれぞれのニーズに応じて、お出かけ前に経路充電計画の立案をお願いしています。
その上で充電量が80%で次の給電可能エリアまでの間で電欠の可能性が予期されるのであれば、「おかわり充電」をするなど、ドライブの際の気象状況などによって臨機に対応されることをお薦めします。」
社としてできることをせずに、ユーザーにはできないことをやれと言う。
あきれた対応だ。
特に、コレ!
「ユーザーそれぞれのニーズに応じて、お出かけ前に経路充電計画の立案をお願いしています。」
お願いされた経験もないし、お願いする文面を見かけたこともない。
ICへ入る前に十分充電してくれというのは見かけたことはあるが
http://sapa.c-nexco.co.jp/guide/i-stop
コレ↓ができないから目安の消費電力を掲示しましょうと勧めているのに。
「充電量が80%で次の給電可能エリアまでの間で電欠の可能性が予期されるのであれば、「おかわり充電」をするなど、ドライブの際の気象状況などによって臨機に対応されることをお薦めします。」
・バッテリー温度が低いと80%まで充電することすらできない。
・電欠の可能性を予期することはほとんどのユーザーにはできない
・気象条件に臨機応変に対応するための情報がない
無理なことを要求してきました。
電費シミュレーターを有している特定のユーザーに対する回答だからこその無理難題なのかもしれないが。
最後に念押しもいただけない。
「EVの車両側の電池容量が拡大している事例もありますので、一概に電欠の蓋然性が高まっている状況にないとも考えています。」
30kWhリーフを念頭に置いているのだろうが、新型の新車を基準にすることが不適切だと知らないのだろうか。
電池容量が増えるEVが走り始める一方で、現状のEVは電池容量がどんどん減っていることに注目して対策するのが社会インフラとしての務めだと思う。
-----------------------
EVのバッテリー特性を理解していない担当者がEVのインフラ整備に関わっているとしたら問題だ。
電欠の危険がある区間への充電器の設置と、臨機応変な対応を可能にするための情報提供を依頼した回答として適切だとは思えない。
NEXCO中日本だと駒ヶ岳SA~梓川SA区間が危ない。
冬以外なら何とかなるが、暖房や曇り取りに電力を使う寒い時期はかなり厳しい。
さらに、バッテリーが劣化したEVだと、過去には通り抜けられたはずだったのに現状は困難だったりする。
NEXCO中日本に、EVが置かれた現状を報告し、対策を依頼した。
その返事が
「現時点で駒ケ岳SA~梓川SA間の急速充電器設置計画はございません。」
にべもない。
十分なバッテリー残量を確保するための目安に消費電力の掲示を進言したのだが、それについても
「EVの車両側の条件として、それぞれの車種で電費が異なりますので、どれだけの電池残量(充電量)があればいいといったものを一律的に掲示することは適切でないと考えています。
ユーザーそれぞれのニーズに応じて、お出かけ前に経路充電計画の立案をお願いしています。
その上で充電量が80%で次の給電可能エリアまでの間で電欠の可能性が予期されるのであれば、「おかわり充電」をするなど、ドライブの際の気象状況などによって臨機に対応されることをお薦めします。」
社としてできることをせずに、ユーザーにはできないことをやれと言う。
あきれた対応だ。
特に、コレ!
「ユーザーそれぞれのニーズに応じて、お出かけ前に経路充電計画の立案をお願いしています。」
お願いされた経験もないし、お願いする文面を見かけたこともない。
ICへ入る前に十分充電してくれというのは見かけたことはあるが
http://sapa.c-nexco.co.jp/guide/i-stop
コレ↓ができないから目安の消費電力を掲示しましょうと勧めているのに。
「充電量が80%で次の給電可能エリアまでの間で電欠の可能性が予期されるのであれば、「おかわり充電」をするなど、ドライブの際の気象状況などによって臨機に対応されることをお薦めします。」
・バッテリー温度が低いと80%まで充電することすらできない。
・電欠の可能性を予期することはほとんどのユーザーにはできない
・気象条件に臨機応変に対応するための情報がない
無理なことを要求してきました。
電費シミュレーターを有している特定のユーザーに対する回答だからこその無理難題なのかもしれないが。
最後に念押しもいただけない。
「EVの車両側の電池容量が拡大している事例もありますので、一概に電欠の蓋然性が高まっている状況にないとも考えています。」
30kWhリーフを念頭に置いているのだろうが、新型の新車を基準にすることが不適切だと知らないのだろうか。
電池容量が増えるEVが走り始める一方で、現状のEVは電池容量がどんどん減っていることに注目して対策するのが社会インフラとしての務めだと思う。
-----------------------
EVのバッテリー特性を理解していない担当者がEVのインフラ整備に関わっているとしたら問題だ。
電欠の危険がある区間への充電器の設置と、臨機応変な対応を可能にするための情報提供を依頼した回答として適切だとは思えない。
2016年02月01日
BMW i3がリーフを超える
昨円末にマイナーチェンジされて航続可能距離が伸びたリーフだが、EV市場における優位は近くマイナーチェンジされるBMW i3によって短命に終わる見通しだ。
30kWhバッテリーを搭載するリーフはEPAで172km(107マイル)走るが、BMW i3は193km(120マイル)とリーフよりも12%性能が上になる。
BMWの電気自動車「i3」、間もなくマイナーチェンジで航続距離が50%増しに Autoblog
さらに、今年末に発売予定の「ボルト」(シボレー)はEPA322km(200マイル)だ。
国内ではリーフがある程度支持されるかもしれないが、海外ではジリ貧だろう。
ところで、BMW i3のマイナーチェンジで目を引くところの一つが「BMWは現行オーナー向けに有償のアップグレードを提供する」だ。
恐らくバッテリーの更新を意味していると思われる。
BMWが新型バッテリーを現行車ユーザーに提供すれば、リーフも同じ土俵に上がらざるを得なくなる。
メーカーとしては大変だろうがユーザーには朗報だ。
BMWのアシストに期待します。
30kWhバッテリーを搭載するリーフはEPAで172km(107マイル)走るが、BMW i3は193km(120マイル)とリーフよりも12%性能が上になる。
BMWの電気自動車「i3」、間もなくマイナーチェンジで航続距離が50%増しに Autoblog
さらに、今年末に発売予定の「ボルト」(シボレー)はEPA322km(200マイル)だ。
国内ではリーフがある程度支持されるかもしれないが、海外ではジリ貧だろう。
ところで、BMW i3のマイナーチェンジで目を引くところの一つが「BMWは現行オーナー向けに有償のアップグレードを提供する」だ。
恐らくバッテリーの更新を意味していると思われる。
BMWが新型バッテリーを現行車ユーザーに提供すれば、リーフも同じ土俵に上がらざるを得なくなる。
メーカーとしては大変だろうがユーザーには朗報だ。
BMWのアシストに期待します。







