2008年08月21日
・祖母が生みの親の試験管ベビー
 子供を生む権利というのはあるのだろうか?
子供を生む権利というのはあるのだろうか?61歳の母親に自分の子供を産ませた、娘による代理出産が昨日のニュースで配信されました。
「諏訪マタニティークリニック」(長野県下諏訪町)の根津八紘院長は20日、不妊の娘のために61歳の女性が昨年、代理出産していたことを明らかにした。28日に福岡市で開く日本受精着床学会で発表する。国内での出産例としては、最高齢とみられる。
根津医師はこれまで、生まれつき子宮がないなど妊娠・出産ができない娘に代わり、実母が妊娠・出産する代理出産を4例実施したことを公表、このうちの1例にあたるという。=毎日新聞 8/20=
この件に関して、当事者の根津氏がHPでコメントしています。
「実母による代理出産」学会発表について
この中でもっとも気になったのが「自然界ではあり得なかった高齢妊娠・出産に関する様々な危険性は充分考えられます。」という記述。
自然界ではありえない人為的な生殖作業で子供を授かることが許されるのか。
昨日は、産科医療過誤事件で無罪判決が出た日でもあります。
産科医不足に拍車をかけた注目の事件でしたが、医師を無罪放免にしたからといって現状の改善につながるかどうかは不透明です。
ミスをしても無罪だからよしとするのではなく、医師がミスを謝罪し補償する患者との関係を築いてこそ、相互の信頼関係が保たれるのではないでしょうか。
医師も患者も、自分の権益や利益を主張するばかりでは疲弊してしまう。
さらに、産みたいからと権利だけを主張し自然の摂理を無視するところまで行ってしまっては、人間の強欲としか見えません。
子供を産みたい気持ちは理解できますが、『卵子と精子を足して胎盤があれば人間が作れる』とする体外受精が倫理上許されていないのも事実。(日本学術会議による代理出産を原則禁止するよう求める報告書)
人が出産し子供を育てるのは、義務でも権利でもない。
あくまでも地球に生きる生物の営みとしての自然の摂理にすぎない。
産む権利も産まない権利も、どちらもないのだから、産める人は産み育て、産めない人は産める人の手助けや、不幸にして生まれてきた命を救う手助けをすればいいと思う。
産む側の権利に翻弄されてないがしろにされる、産まれ来る子供の利益。
自然に授かったのではなく、人工的に製造された身であることを受け入れなければならない子供が哀れです。
2008年08月20日
・健康とは違う方向に精力的な検診
 昨日は、年に一回の定期健診の日。
昨日は、年に一回の定期健診の日。公民館では、駒ヶ根市の職員と長野県健康づくり事業団のスタッフが大忙しで健康診断に当たっていた。
検診を受けるには事前の準備も大変だ。
市から送られてきた書類は10枚以上。
全体をまとめた説明書がないので、すべての書類のすべての項目に目を通さなければならない。
年配の人には、かなり困難な作業だろうと思われます。
何かあったときの責任逃れのために「同意」を誓約させられる項目も各所にあり、世知辛い世の中になったことで役所も住民も相互に負担が増えている。
少し前までならもっと簡潔だった健診が、健康とは直結しない行政の責任を軽減する目的で、人的にも経済的にも負担が増えて、得しているのは健康で金儲けしている事業者だけ。
また、メタボが世の関心事となっているために、「ウエストが4cmも減っている。もう一回測らせてください。」と、至極慎重です。
昨年から胴回りを測定することになったらしいのですが、ウエストごときに、それほど過敏になる必要もないのではと思う。
タイミングよく、腹囲が国際的な統一基準の必須条件から外されることになったとのニュースが配信された。
毎日新聞クローズアップ2008:メタボ、国際基準統一へ おなか優先、日本だけに
腹囲測定をメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)診断の第一条件として、特定健診・保健指導(メタボ健診)しているのは日本だけだという。
訴訟リスクの低減に手間を増やし、国際基準から外れたメタボブームに気をとられ、市民の健康が二の次になっているような気がします。
2008年08月19日
・劉翔に見る中国の偽装金メダル
 昨日、北京の鳥の巣は中国人の呆然とする顔で埋め尽くされました。
昨日、北京の鳥の巣は中国人の呆然とする顔で埋め尽くされました。男子110メートル障害第1次予選で、国民的英雄のアテネ五輪金メダリストの劉翔(中国)が棄権したからです。
同競技は通常なら一日で一次予選と二次予選、翌日に準決勝と決勝を行うが、中国当局の指示で一日に一走のみとされています。
4日間、英雄の姿を世界中に見せつけるための暴挙でした。
しかし、当人がその暴挙によって潰れて、当局の思惑が外れてしまった。
一般の選手なら突然のアクシデントによる棄権は同情を誘うが、反日のスポークスマンとして活動していた劉翔ですから、「ざまあみろ」といったネットの書き込みが大勢を占めています。
ところが、母国中国でも「この脱走兵め」「意気地なし」「13億人を傷つけた。新記録だ」……、大手サイト掲示板に殺到する万単位の書き込みの多くが怒っている。
「逃げ劉」--四川大地震で生徒を放って校舎から逃げた教師と同じ呼び方がすぐに広がった。
今回の北京五輪で中国のメダル獲得数は躍進しているが、その影には金メダル一個に110億円の巨費が投じられているとの指摘がある。
北京理工大学の胡星斗教授(経済学)は米政府系の自由アジア放送(RFA)に対し、多くの先進国では五輪の金メダルは全国民の健康増進の中から生まれるが、中国の場合は「完全密閉式の練習」によると指摘。
金メダルを目指す練習のため子供が数年から十何年も家に帰れないのは残酷だとして、自国の五輪挙国体制を批判している。
さらに胡教授は、中国はメダルを狙う選手養成に多くの資金を投じる一方で、国民の健康のための投資は少なく、これでは「金メダル大国」とは言えるが、真の「スポーツ強国」とは言えないと分析している。
中国には今も貧困のため小学校に通えない子供がいるにもかかわらず、金メダルのための「財政の巨大な負担と浪費」が国民の教育や健康増進の機会を奪う結果になっているという。
五輪憲章には、「オリンピック・ムーブメントの目的は、いかなる差別をも伴うことなく、友情、連帯、フェアプレーの精神をもって相互に理解しあうオリンピック精神に基づいて行なわれるスポーツを通して青少年を教育することにより、平和でよりよい世界をつくることに貢献することにある。」と書かれている。
五輪憲章にことごとく反する北京五輪が終盤に差し掛かっている。
2008年08月18日
・墓参りと無差別殺人
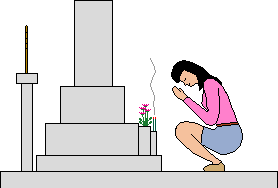 お盆が過ぎ、帰省先で先祖に感謝した方々が実生活に戻ってきました。
お盆が過ぎ、帰省先で先祖に感謝した方々が実生活に戻ってきました。一年で一番、「命」について考える機会だと思うのですが、お墓参りが命を紡ぎ続ける意識づけに役立っているのかな。
そんなことを思ったのは、昨日のNHK日曜討論を拝見してのこと。
秋葉原殺人事件をテーマに多彩な顔ぶれが問題の本質に迫って、途中から見始めたのですが見入ってしまいました。
「個を尊重する教育が30年前ほどから始まり、20年前から子供たちが変わった」
教育現場の変貌で、個人の権利が偏重され、人類が生きながらえるために個人が何をなすべきかがないがしろにされてきた。
人が生きる目的が、自己実現に置き換えられてしまい、本来の命の役割を見失ってしまったのだと思います。
今、自分が生きているのは、親から祖先にいたる過去の命の連携があってこそ。
今、自分がなすべきは、子孫がより良い環境で命をつないでいけるように努力すること。
自己実現は、他者である子孫の役に立つものでなければまったくの無意味。
本能で生きる昆虫には学ぶところが多い。
特に心酔するのがカマキリの雄です。
雌との交尾で次の命を作り出し、次の命の糧として交尾後には雌の餌となって自分の命を活かす。
究極の自己実現をここに見る。
浄土真宗のあるHPにお墓参りの本質を突いた記述を見つけました。
故人の好きだったお酒や食べ物などを供え、故人の霊に手を合わせて慰めることがお墓参りだと思っているとしたら、それは少し筋が違います。はっきり言って、お墓に先祖の霊が宿っているのではありません。固定的実体的な霊をそこに見ようとするのは、他ならぬ私自身の執着心がなせるわざで、実際的には、故人はお墓の中に眠っているわけではなく、また遺骨が故人なのではなく、すでにお浄土へ還られています。
それでは、お墓は何のためにあるのでしょうか。お墓は、先祖あるいは故人が必要とするからあるのではなく、私たちが先祖、故人を敬い讃えたいと思うから建てるのです。さらに言えば、かけがえのない命を私に伝えてくださったご先祖に感謝しつつ「その命を精一杯輝かせて生きてくれ」という私へのご先祖の願いを聞く場でもあります。また、遺骨を前にして諸行無常を味わうのもお墓でしょう。
次の世代の命が精一杯輝くように、今の私たちが一生懸命に生きる。
他者を幸せにすることが、自己を最も高めることにつながる。
他者を不幸せにすることは、自己を貶め(おとしめ)、他者の命を奪い去るのは、もっとも醜い行いであると自覚する。
こんな当たり前のことが忘れ去られて、自分のために生きているのだと錯覚する者が増えたことが、無差別殺人の背景にあるのではないかと思います。
2008年08月17日
・世界の共通認識となった偽装中国
 北京オリンピックの偽装が次々と明らかになり、スポーツマンシップに則ったフェアプレーの頂点を目指す場として見直しの機運が次期開催国の英国から発信され始めました。
北京オリンピックの偽装が次々と明らかになり、スポーツマンシップに則ったフェアプレーの頂点を目指す場として見直しの機運が次期開催国の英国から発信され始めました。次回夏季五輪を開催する英国で、北京五輪の運営に対する批判的な報道が目立っている。
「偽装五輪、どこから見ても見栄え良く設計」。こんな見出しを掲げたのは、13日付タイムズ紙。
口パク問題のほか、当局が組織した“ボランティア”応援団が競技場に送り込まれ、空席が目立つ応援席を埋めていると報じた。
派手な演出の開会式にロンドン五輪関係者が「太刀打ちできない」と漏らすほどだっただけに、その後の「花火の合成映像」や「口パクの少女の歌」の発覚で「中国異質論」が勢いを増した形だ。
フィナンシャル・タイムズ紙は社説で、偽装してまで“完ぺき”を目指す中国は「五輪は単なるゲームだと思い出すべきだ」と強調。デーリー・テレグラフ紙は、ロンドン五輪では「開会式でも競技でも健全さを取り戻そう」と主張した。(共同)
北京五輪組織委員会は15日、8日の五輪開会式で「中国の56民族を代表する」と紹介した子どもの多くが、少数民族の衣装を着ただけの漢族だったことを明らかにした。漢族は人口の92%を占める多数派。各民族の団結が漢族を主体に演出された。
一方、開会式の演出が、「中国文化を濃縮した表現とする」との中国共産党上層部の指示で、演出家の計画から大幅に変更されていたことが分かった。絵巻物の演出を担当した中国人画家、陳丹青氏が中国紙「南方週末」の最新号で証言した。
陳氏は「昨年初めに中南海(北京の要人居住区)の人が意見を言い、変更させられた」と語った。(毎日新聞)
中国国内では偽装五輪を肯定する意見が大半を占めていることから、中国という国家そのものが偽装で成り立っていると思ってもよさそうです。
五輪にふさわしいくない国で開催したことに問題があるのであって、中国の体質を今さら批判しても仕方がないとも言える。
違う見方をすれば、中国がニセモノ大国であることを今回の五輪で返上する機会として与えられたにもかかわらず、それができなかったことで中国は先進国の異端者としての地位がさらに強固になったと思います。
どちらにしても、国際標準のモラルを国家としても、民族としても持ち合わせていない中国の現実を世界中の人々が共通認識として得られた意義は小さくない。
こんな国が常任理事国になっている国連が世界の規範になれないのも当然といえる。
2008年08月16日
・せいぜい頑張った北京五輪折り返し

「まあ、頑張ってください。せいぜい頑張ってください」今月8日、北京五輪開会式を前に日本選手団を激励するため選手村を訪問した福田康夫首相のあいさつです。
「私はね、日本国民のためにメダルをいくつ取ってくれなきゃ困るなんてこと言いません。余計なプレッシャーかけちゃいけないと思って自制しているんです」
「今年は、みんな旅行にも行かないで、家でテレビの前で一生懸命見ようということのようだ。ガソリンが高いせいもちょっとあるんだけどね」
このせいぜい(精精)は、石原都知事も批判したように、「たかだか~」と見下した意味あいで使われることもあり、軽々しく使うと失礼になってしまうことがある。
福田首相のあいさつは、まことに軽々しいので「せいぜい」も『できるだけ。一生懸命。』の重い意味を持つようには聞こえてこない。
日本の柔道が期待はずれに終わったのが首相の挨拶のせいだとは思いませんが、どちらの意味でせいぜい頑張ったのかは柔道が日本の国技であるだけに気になります。
選手個人の努力には惜しみない賞賛を差し上げますが、競技に勝利する執念が他国に比べて抜きん出ていたかというとそうでもないように思われます。
それを物語ったのが100キロ超級で優勝した石井選手ではないでしょうか。
優勝直後のインタビューで、「決勝戦の戦いが自分の柔道。冒険をせずに完全に勝てばいい」と言った石井選手。
五輪代表選考会の一つ、昨年末の嘉納杯決勝でライバル井上康生と対戦した石井は、相手への指導1つの小差で勝った。
作戦勝ちだったが、周囲からは「汚い」「ずるい」と非難されたたが、それでも石井の信念はかたかった。
「柔道はルールのあるけんか。芸術性が大事なら採点競技をやればいい」。
かつての山下泰裕のように卓越した技能を持っているような選手は勝利に一本の美学を重ね合わせることも許されるだろうが、互角のライバルたちから勝ちを収めるには石井の言う「ルールの中で勝ちに徹する」姿勢は大事だと思います。
華麗に一本で勝てる選手がいつの時代にも、どの階級にも揃えられるほど日本の柔道人口は多くない。
フランスは日本の3倍もの柔道人口がいるらしい。
テレビで観戦するだけ、柔道もちょっとかじったことがあるだけの、ほとんど門外漢のたわごとですが、せいぜい頑張る方向性が日本の『柔道』と国際競技の『JUDO』で違ってきていると思います。
日本国内で、国技の美学に磨きをかけることと同時に、国際競技で日本の地位を保持することも求められる。
国際競技の母国としての重荷に押しつぶされることなく、この難題を克服して欲しいと思います。
だからこそ、まぎらわしい「せいぜい」などという表現ではなく、「力の限りを尽くして戦ってください」と国民の目線で挨拶できない福田首相の見下し目線が気になります。
石原都知事によると、開会式で元首クラスの最高指導者がそろっている中で、自国の選手が(入場して)来て、立って手を振らなかったのは、福田首相と北朝鮮の代表だけだった。
北朝鮮の代表と同じ目線で福田首相が国民を見下していることがハッキリした場面だと思います。
**関連記事
デイリースポーツonline/男の意地で「金」石井が守った/スポーツ
2008年08月15日
・村井県政2年は偽装と過去崇拝
 長野県の村井知事が建設を推し進めている穴あきダムに重大な欠陥が指摘されています。
長野県の村井知事が建設を推し進めている穴あきダムに重大な欠陥が指摘されています。県が7月と今月初めに実施した模型実験について、実験を見学した今本博健・京都大名誉教授(河川工学)は13日、県庁で会見し、「穴詰まりが発生しない条件で行われており、穴詰まりの懸念は解消されていない。決定的な欠陥がある」と述べた。その上で、専門家に広く公開して再度実施すべきだと主張した。
今本教授は、実験で用いられた土砂が、川底にたまったものを想定したため小さすぎたと指摘。「洪水が起きた際は、斜面から崩壊した岩石も流れ込む可能性があり、不適切だ」と話した。
実験の公開対象が県民や県議に限られていたことについても、「異なる見解を持つ専門家を全国から呼んで、県民の前で議論を公開すべきだ」と求めた。 =朝日新聞 8月14日=
実験は建設を推進させるための「偽装」の疑いがあります。
穴あきダムの機能に有利な条件で実験を行い、不利な条件は除外している。
実際の災害で発生するリスクではなく、限られた好条件の中で機能が確保されることの確認のみが行われた。
淺川ダムは、田中前知事の時には建設中止が前提で、村井県政に変わったら建設することが前提となった。
建設地の長野市長は、コンクリート屋なので私腹を肥やすためにも建設は大歓迎。
土建頼みの自民党から送り込まれた村井知事も、業界の利権のために建設に全力を挙げる。
一般住民の利益は蚊帳の外。
岩本教授は建設予定地で地すべりが起きることを地元住民らが懸念していることに関しては、「地すべりが起こらないという県の主張には根拠がない。もっと慎重にして欲しい」と話している。
河川工学の権威がこう言っているのだから、素人の県職員が反論するほうがおかしい。
やるべきことをやらないのは、やると都合が悪いからに他ならない。
後ろめたい思いがあるときに行政がとる対応です。
村井知事が長野県のトップになって、県の示す施策にごまかしが目立つようになってきました。
温暖化防止の計画も、その場しのぎで将来の展望がなくなってしまった。
金を集めて事業を起し、利権に報いることだけが目的の村井県政ですから当然です。
村井県政の2年を評価するとしたら「できることしかやらない」ことに徹した守りの政策くらいですね。
時々刻々と変化している日本の社会で取り残されていくことを恐れず、古き良き吉村県政の学び、踏襲したことを褒め称える守旧派の人たちに限られますが。
2年後の知事選に向けて、水面下での準備の進行が期待されます。
2008年08月14日
・命を救う泳ぎ方で子供を守る

12日正午前、伊那市中央の市民プールで、50メートルプールに駒ケ根市の男児(5)が沈んでいるのを監視員が見つけ、引き上げた。男児はすぐに意識を取り戻し、水を吐き出した。監視員が119番通報して伊那市内の病院に搬送。命に別条はなく、同日中に帰宅した。 =信濃毎日新聞=
幸い命にかかわる事故にならなかったが、発見が少しでも遅れれば重大事故になっていました。
母親と一緒に訪れていたそうですが、どうして幼児から目を離すんでしょうか。
子供が犠牲になる水の事故の多くが、親が目を離した「ホンの僅かな隙」に生じます。
水難事故の悲惨さを知らない親がほとんどだと思うので、気の配り方が不足していると思われます。
子供の頃、海岸が目の前にあったこともあり、『どざえもん』を見かけることは珍しくなかった。
どざえもんという言葉を知らない人もいるだろうが、実物はまさに白く体が膨れ上がり、見るも無残な死に様となる。
享保年間に色白で典型的なあんこ型体形で有名だった大相撲力士、成瀬川土左衛門にそっくりだったことからこの名がついたという。
毎日のように海で遊んでいたので自身でも水難事故を起こしています。
幼稚園児の頃、親の知らぬ間に浮き輪を持って泳ぎに出かけ、そのまま沖へ流されたところを、たまたま旅館から双眼鏡で海を眺めていた観光客が見つけ、漁船に救助されたことがあります。
双眼鏡で海を眺めている人がいた『奇跡』に助けられたのですが、親が防げたかというと、無理だったという思いがします。
家で遊んでいると思った我が子が、海で沖に流されてしまうとは予想もつかないですよね。
これは、黙って海に行った子供の頃の私が悪い。
冒頭のニュースは、親が子供を連れていったプールで起こった水難事故ですから、親が悪い。
水の事故の恐ろしさを知っていれば、子供を守ろうとする意識も違うでしょうが、日本の水泳に関する教育は『競泳の泳ぎ方』を教えるばかりで、水難事故を防ぐ視点が欠落している。
泳いでいて足がつったらどうしたらいいか。
足がつかない場所で疲れて泳げなくなったらどうするのか。
前者は、あわてずに水に潜り、足をマッサージしてから息継ぎをすればパニックに陥らない。
ところが、心がけがないと、何とかして浮き上がろうともがき、おぼれてしまう。
人の体は、浮こうと思えば沈み、潜ろうと思えば浮くものなのです。
足がつかない場所で疲れて泳げなくなったら、仰向けになって口がやっと出る程度にまで頭を沈め、ゆらゆらと水面に浮いた状態で体力の回復を待ちます。
体力を使わずに浮いていることができると知っていれば、溺れずにすみます。
水難事故を起こさないために、知っておきたい泳ぎのあれこれは下記のサイトが詳しいのでお勧めです。
いのちを救う泳ぎ方
**関連記事
・新潟の海岸で保育園児死亡
2008年08月13日
・大国に利用される北京五輪
 北京五輪の開会式が『偽装』で作られていたのは残念です。
北京五輪の開会式が『偽装』で作られていたのは残念です。中国らしいと言ってしまえばそれまでですが、人間の能力の限界に挑戦する場の演出をCGや口パクで彩るなど、目的のためなら手段を問わない。
「国家の利益のためだから」というのがその理由ですが、オリンピックは国家のために開催されるのではなく、選手のために国家が活躍の場を提供するのが筋。
完全に履き違えていますね。
また、平和の祭典のはずが、ロシアによるグルジア侵攻が五輪の競技開催と同時並行で行われています。
紛争があっても五輪開催中は停戦するのが近代国家の倫理だと思うのですが、ロシアは開催中に開戦するのですから前時代的共産国家の体質のままです。
中国といい、ロシアといい、五輪を蝕む共産国家が目立つ結果となる北京五輪。
ロシアの選手の表情が心なしか沈んでいるのはかわいそうだと思います。
自国の選手が胸を張って活躍できる環境を整えるのが国家の役割でしょう。
国家権力増強のために五輪を悪用する中国のやり方は論外ですが、選手が競っている外国選手の母国で大量殺戮の戦闘を行っているロシアは人道を語る権利すら持ちません。
アメリカだって、自国のテレビ放映に合わせて競泳の決勝を異例の午前中に変更させるなど、傍若無人が目立ちます。
大国の思惑に利用されても、必死に全力を尽くす選手たちのがんばりに声援を送りたいと思います。
2008年08月12日
・ゴミ処理から、資源自給への転換
 一昨日開催された、ごみ焼却場が安全な施設だと住民に知らせるための学習会。
一昨日開催された、ごみ焼却場が安全な施設だと住民に知らせるための学習会。具体的な危険も例に挙げて、危険な施設を安全に管理する方策の実際を示していたことは、安全神話を押し付ける行政の説明会とは一線を画していました。
講師の、住民への不安を取り除いてきた経験がよく発揮された良い講演だったと思います。
意味のあった学習会であることを前提にして、あえて苦言を呈したいと思います。
第一に、これからのゴミ処理体系として示された循環型社会とゴミとの関係があまりも不十分です。
ゴミ処理の現場からの見方なので仕方がない面もありますが、紹介された模式図は将来を展望したものではなく、現状の取り組みにとどまっています。
遅れている自治体からすればこれからのあり方を示されたと捉えるかもしれませんが、激変するであろう今後の5年後10年後を展望した資源循環の視点からは立ち遅れた内容でした。
ゴミを「減量」「再使用」「再資源化」の3Rで減らした後に焼却処分する考え方がこれからのあり方だとしましたが、現状の追認に過ぎません。
ゴミの組成から考えた資源としての世界的な需要の高まりからすると、こうした考え方では成り立たなくなります。
その典型的な例が日本のペットボトルリサイクルです。
自治体によって収集されたペットボトルを無料で引き取り、再資源化することを目指した日本のペットボトルリサイクルシステムは、ペット樹脂の国際的な価値高騰で入手が困難となり崩壊しています。
ゴミは公衆衛生の邪魔者だから排除するとの考え方が根底にあるままでは、ゴミの資源としての価値に気が付かず、取り扱いを誤ってゴミ資源利用後進国の汚名を返上できません。
ゴミはすべてが資源です。
資源小国の日本が、このほとんどを焼却して無効化してしまっているのはあまりにも『もったいない』
国策の間違いがここにはあるのですが、資源を買い入れ、価値を高めて海外に売り、その差益で資源を買い続けるとする日本の産業システムはまもなく破綻します。(すでに破綻の兆候が現れている)
国内はもとより、地域内で資源の循環をはかることで外部に資源を依存する割合を下げ自給率を上げる。
大量浪費が認められない地球温暖化防止からも、絶対に避けられない道筋です。
ごみ焼却の安全性を高めるための一番の取り組みは、ゴミの総量を減らすことです。
しかし、これまでにもゴミを減らそうとする努力してきましたが、その効果が目に見えて現れないのは、努力した本人に恩恵が直接返ってこないからです。
ゴミを徹底的に分別することでゴミが資源へと変化し、地域に資源として供給され、そこで生まれた利潤が供給者に還元されるシステムつくりが求められます。
ゴミの減量化を住民に押し付けるこれまでのやり方を見直し、消費者が地域内の資源の供給源となる新たな展開を目指すべきです。
駒ヶ根市長には、この提言を伝えてあります。
これなくして、2008年から12年の5年間でCO2のマイナス6%はあり得ません。
2020年のマイナス25%、2050年のマイナス50%を目指すためには、高効率社会を築き上げるほかに特効薬がありません。
国任せではない地方主権の地球環境対策として、一刻も早く体制を整え、先進地域として名乗りを上げることを上伊那全域の自治体に望みます。
家庭ごみ処理機に予算をつけた程度で満足しているようでは、「井の中の蛙、大海を知らず」の恥ずかしい田舎者です。
「できることをやる」これまでの消極的な姿勢から、やるべきことの可能性に挑戦する姿勢へと行政職員の意識を変えなければなりません。
市民協働のまちづくりとは、井の中で守りに入る公務員を荒海に引っ張り出すことから始まると思います。







