2011年04月04日
・レベル7で放射線汚染水を海に廃棄
放射能の危険が原発の外へ垂れ流しになる。
法律で定める濃度の約100倍の放射線汚染水が大量に海に捨てられます。
このニュースを目にした瞬間、背筋が凍りました。
政府や東電は「低レベル汚染水」と言ってますが、それが一万トンを超える量になれば総量としての放射性物質は膨大です。
集中廃棄物処理施設内にたまった水の放射性物質の濃度は、ヨウ素131で1立方センチメートル当たり6.3ベクレル、5号機で16ベクレル、6号機で20ベクレル。
集中廃棄物処理施設内の滞留水が約1万トン、5、6号機の地下水が合計1500トン。
単純計算で900億ベクレルという途方もない放射能が海を汚染します。
原子力安全・保安院は「(低レベル汚染水の放出は)最後に本当に追い詰められてこうなった」と他に打つ手がないことを認めています。
原発から漏れ出している超高濃度汚染水は数百万ベクレルなので、90リットルで900億ベクレルになるので、こちらを垂れ流し続けるよりはマシだということです。
禁じ手を使わなければ対処できなくなってしまったことの、深刻さをマスコミは国民に正確に伝えなければなりません。
海で拡散するから人体には影響のない濃度になると専門家と称する政府委託のスポークスマンはテレビで言い続けていますが、それらが信じるに値しないことを魚が示しています。
茨城・北茨城市の漁協が、専門機関に魚の放射線濃度の測定を依頼した結果、4月1日に採取したコウナゴから、1kgあたり4,080ベクレルの放射性ヨウ素を検出したという。
魚介類には放射性ヨウ素の暫定規制値はないが、その理由は海で拡散して薄まるから魚からは高濃度の放射能が検出されるはずがないという思い込みがあったからです。
原子力を安全に見せかけるための仕掛けは、すべて覆されました。
食物連鎖による生態濃縮が始まる前に、魚介類から高濃度の放射性物質が検出されたことは、今の状況がしばらく続いたらどうなるのかを示唆しています。
細野豪志首相補佐官は福島第一原発の放射性物質の漏出を食い止めるまでに「少なくとも数カ月」との見通しを示しています。
日本の近海が放射能汚染されるのを数ヶ月放置しなければならないのですよ。
ある意味、チェルノブイリを越えました。
IAEA(国際原子力機関)が定めた原発事故の大きさを表す国際評価尺度(INES)で、福島第一原子力発電所の事故はチェルノブイリと同じ「レベル7」に達しましたね。
レベル7は放射性物質の重大な外部放出を意味し、よう素131等価で数万テラベクレル相当以上の放射性物質の外部放出が認められた場合ですから。
**本日の発電量 75.1kwh
-第一発電所 31.8kwh
-第二発電所 43.3kwh
過去最大の発電量を更新しました。
法律で定める濃度の約100倍の放射線汚染水が大量に海に捨てられます。
このニュースを目にした瞬間、背筋が凍りました。
政府や東電は「低レベル汚染水」と言ってますが、それが一万トンを超える量になれば総量としての放射性物質は膨大です。
集中廃棄物処理施設内にたまった水の放射性物質の濃度は、ヨウ素131で1立方センチメートル当たり6.3ベクレル、5号機で16ベクレル、6号機で20ベクレル。
集中廃棄物処理施設内の滞留水が約1万トン、5、6号機の地下水が合計1500トン。
単純計算で900億ベクレルという途方もない放射能が海を汚染します。
原子力安全・保安院は「(低レベル汚染水の放出は)最後に本当に追い詰められてこうなった」と他に打つ手がないことを認めています。
原発から漏れ出している超高濃度汚染水は数百万ベクレルなので、90リットルで900億ベクレルになるので、こちらを垂れ流し続けるよりはマシだということです。
禁じ手を使わなければ対処できなくなってしまったことの、深刻さをマスコミは国民に正確に伝えなければなりません。
海で拡散するから人体には影響のない濃度になると専門家と称する政府委託のスポークスマンはテレビで言い続けていますが、それらが信じるに値しないことを魚が示しています。
茨城・北茨城市の漁協が、専門機関に魚の放射線濃度の測定を依頼した結果、4月1日に採取したコウナゴから、1kgあたり4,080ベクレルの放射性ヨウ素を検出したという。
魚介類には放射性ヨウ素の暫定規制値はないが、その理由は海で拡散して薄まるから魚からは高濃度の放射能が検出されるはずがないという思い込みがあったからです。
原子力を安全に見せかけるための仕掛けは、すべて覆されました。
食物連鎖による生態濃縮が始まる前に、魚介類から高濃度の放射性物質が検出されたことは、今の状況がしばらく続いたらどうなるのかを示唆しています。
細野豪志首相補佐官は福島第一原発の放射性物質の漏出を食い止めるまでに「少なくとも数カ月」との見通しを示しています。
日本の近海が放射能汚染されるのを数ヶ月放置しなければならないのですよ。
ある意味、チェルノブイリを越えました。
IAEA(国際原子力機関)が定めた原発事故の大きさを表す国際評価尺度(INES)で、福島第一原子力発電所の事故はチェルノブイリと同じ「レベル7」に達しましたね。
レベル7は放射性物質の重大な外部放出を意味し、よう素131等価で数万テラベクレル相当以上の放射性物質の外部放出が認められた場合ですから。
**本日の発電量 75.1kwh
-第一発電所 31.8kwh
-第二発電所 43.3kwh
過去最大の発電量を更新しました。
2011年04月04日
・農水産物の暫定基準値は維持 政府、解除ルール策定へ
厚生労働省は4日、薬事・食品衛生審議会の食品衛生分科会を開き、農水産物の放射性物質に関する食品衛生法の暫定基準値について「維持すべきだ」との意見を取りまとめた。同省は審議会の意見を踏まえ、現状の暫定基準値を確定。政府の原子力災害対策本部は出荷停止や摂取制限の解除ルールを策定する。
取りまとめでは、有識者でつくる内閣府の食品安全委員会が現基準の維持が適当との評価をまとめたほか、原子力安全委員会も同様の見解を示していることを指摘。
放射性物質の飛散が収束していないことなどを踏まえ、暫定基準値を維持するべきだとした。
また同省などに対し、国民の不安感を払拭(ふっしょく)するため、放射性物質の健康影響について分かりやすく情報提供するよう求めた。
暫定基準値は、福島第1原発の事故を受けて厚労省が急きょ設定した。一部の農産物が出荷停止となっている県からは、基準緩和や早期解除を求める声が強い。
政府は解除ルールに加え、県単位で実施している規制を地区単位に細分化することなどを検討している。 =2011/04/04 【共同通信】=
◇ ◇
当然ですが、安全基準が改悪されずにすみました。
農家の保護も大事ですが、そのために国民の生命を守る基準を安易に動かすことはあってはならないでしょう。
見直そうとしたこと事態が異常だと思います。
見直すべきは基準の運用方法です。
放射線予測システム SPEEDI(スピーディ)による高濃度汚染地域の特定と、これを基にしたモニタリング体制をしっかりと機能させ、危険度の高い場所と比較的低い場所の特定が必要です。
危険と安全でばっさりと切り分けると中間的な地域では影響が大きくなるので、危険度を国民が理解できるように丁寧に説明することが望まれます。
「ただちに健康に影響がない」などというお役所言葉を止めて、「寿命をどれほど短くします」とリアルに届ける工夫が欲しい。
例えば環境リスク学の評価なら、喫煙による全死因では数年から数十年という期間の余命が失われると報告されています。
寿命が何年か短くなってもタバコが吸いたいと思う人は、割り切って吸えばいいということになりますが、医療費は国全体の負担にかかってきますから個人のリスクとして割り切れません。
空から降ってくる放射性物質によって損失余命が何日だとか、何年だとか予測できるようになると、他の生活環境リスクと比較して自分にとって危険なのかどうか判断がつけやすくなります。
アメリカの論文ですが、1979年に「「リスク・カタログ」が発表されています。
これによると自然放射能による損失余命は9日です。
違法薬物の使用が18日、飲酒が130日、左利きが3285日など、多角的にリスク評価されています。
日本ではリスク評価が正しく認識されていないので、潜在的な恐怖感が安全基準をゆがめているといわれます。
しかし、科学者の理論ではリスクが低くても、人心に与える社会的影響を加味すると損失余命だけで割り切れないこともあるので、あくまでも判断材の一つとして提示してもらいたいと思います。
仮に、摂取制限になった野菜を一年食べ続けた場合の損失余命が10日だとすると、一日食べたくらいでは40分の寿命短縮に相当することになります。
タバコを一箱吸った人の損失余命が110分なので、体に悪いことをしているんだなと感覚的に捉えられます。
※感覚的に捉えるための仮定ですから、誤解しないように。
ちなみにアメリカ人でコーヒーを飲む人の損失余命は6日だそうです。
日常生活の中に環境リスクは散在して一つ一つ意識していませんが、神経質になると生きていくのが難しくなりますね。
環境リスクの指標を精神的にも安心できるように改良してくれると、無用な風評被害が防げるようになるのではないでしょうか。
取りまとめでは、有識者でつくる内閣府の食品安全委員会が現基準の維持が適当との評価をまとめたほか、原子力安全委員会も同様の見解を示していることを指摘。
放射性物質の飛散が収束していないことなどを踏まえ、暫定基準値を維持するべきだとした。
また同省などに対し、国民の不安感を払拭(ふっしょく)するため、放射性物質の健康影響について分かりやすく情報提供するよう求めた。
暫定基準値は、福島第1原発の事故を受けて厚労省が急きょ設定した。一部の農産物が出荷停止となっている県からは、基準緩和や早期解除を求める声が強い。
政府は解除ルールに加え、県単位で実施している規制を地区単位に細分化することなどを検討している。 =2011/04/04 【共同通信】=
◇ ◇
当然ですが、安全基準が改悪されずにすみました。
農家の保護も大事ですが、そのために国民の生命を守る基準を安易に動かすことはあってはならないでしょう。
見直そうとしたこと事態が異常だと思います。
見直すべきは基準の運用方法です。
放射線予測システム SPEEDI(スピーディ)による高濃度汚染地域の特定と、これを基にしたモニタリング体制をしっかりと機能させ、危険度の高い場所と比較的低い場所の特定が必要です。
危険と安全でばっさりと切り分けると中間的な地域では影響が大きくなるので、危険度を国民が理解できるように丁寧に説明することが望まれます。
「ただちに健康に影響がない」などというお役所言葉を止めて、「寿命をどれほど短くします」とリアルに届ける工夫が欲しい。
例えば環境リスク学の評価なら、喫煙による全死因では数年から数十年という期間の余命が失われると報告されています。
寿命が何年か短くなってもタバコが吸いたいと思う人は、割り切って吸えばいいということになりますが、医療費は国全体の負担にかかってきますから個人のリスクとして割り切れません。
空から降ってくる放射性物質によって損失余命が何日だとか、何年だとか予測できるようになると、他の生活環境リスクと比較して自分にとって危険なのかどうか判断がつけやすくなります。
アメリカの論文ですが、1979年に「「リスク・カタログ」が発表されています。
これによると自然放射能による損失余命は9日です。
違法薬物の使用が18日、飲酒が130日、左利きが3285日など、多角的にリスク評価されています。
日本ではリスク評価が正しく認識されていないので、潜在的な恐怖感が安全基準をゆがめているといわれます。
しかし、科学者の理論ではリスクが低くても、人心に与える社会的影響を加味すると損失余命だけで割り切れないこともあるので、あくまでも判断材の一つとして提示してもらいたいと思います。
仮に、摂取制限になった野菜を一年食べ続けた場合の損失余命が10日だとすると、一日食べたくらいでは40分の寿命短縮に相当することになります。
タバコを一箱吸った人の損失余命が110分なので、体に悪いことをしているんだなと感覚的に捉えられます。
※感覚的に捉えるための仮定ですから、誤解しないように。
ちなみにアメリカ人でコーヒーを飲む人の損失余命は6日だそうです。
日常生活の中に環境リスクは散在して一つ一つ意識していませんが、神経質になると生きていくのが難しくなりますね。
環境リスクの指標を精神的にも安心できるように改良してくれると、無用な風評被害が防げるようになるのではないでしょうか。
2011年04月04日
・新しい地方選挙スタイル 3
誰でも地方議員になれるようにといっても、無分別に面白半分の立候補者が乱立されても困ります。
議会で政治家として活躍しなくてはならないので、選挙でもその片鱗を示すことが求められます。
この意味で、地元の名士や実力者が地域の総意を得て立候補に至る瀬踏み行為は存在価値が認められる場合もあります。
国会に目を移すと、政党の代表選挙に立候補するには一定数以上の推薦人が必要になります。
推薦人の人数が適当かどうかは別にして、ある程度の支持者を得られない程度の政治家の資質では、政党の代表に立候補する資格がないという決まりです。
これは一理あると思うので、候補者の質をある一定以上に保つためには検討する必要があると思います。
供託金(市議会だと30万円)が、一定の歯止めをかけるためにあるのでしょうが、町村議員だと義務付けられていません。
駒ヶ根市のように、対外的には『市』ですが、実情は『町』程度の自治体なら、供託金の対象にならなくてもいいのではないかな。
一歩譲って、供託金を納めるか、一定数以上の推薦人を集めるなどの選択肢が用意されるというもの良さそうです。
売名行為を防止するのが供託金の主な趣旨のようですが、小さな地方自治体の議会選挙に立候補したからといっても大した話題にはなりません。
しかし、地方選挙のハードルを下げて、誰でも立候補できて、多方面に主張を届けられるようになると悪用する人が出てくることも考えられます。
有能な人材発掘というメリットと、遊び半分が入り込むかもしれないというデメリットを比較してみると、前者のためにまずはやってみて、デメリット対策は後からでもいいような気がします。
遊び半分の候補者が当選する可能性は、無投票でもない限り低いと思われるからです。
無投票になったら遊び半分が当選してしまうじゃないかという心配性の方が出てくるかもしれませんが、立候補のハードルが下がればやってみようと思う意欲のある人は必ずいるものです。
自分の住む自治体に誇りを持っていれば、無用な心配だと思えるのではないでしょうか。
たくさん立候補しすぎて広報に支障ができるくらい政治に関心が高まれば、その自治体の活性化は大変に期待できるということです。
議会で政治家として活躍しなくてはならないので、選挙でもその片鱗を示すことが求められます。
この意味で、地元の名士や実力者が地域の総意を得て立候補に至る瀬踏み行為は存在価値が認められる場合もあります。
国会に目を移すと、政党の代表選挙に立候補するには一定数以上の推薦人が必要になります。
推薦人の人数が適当かどうかは別にして、ある程度の支持者を得られない程度の政治家の資質では、政党の代表に立候補する資格がないという決まりです。
これは一理あると思うので、候補者の質をある一定以上に保つためには検討する必要があると思います。
供託金(市議会だと30万円)が、一定の歯止めをかけるためにあるのでしょうが、町村議員だと義務付けられていません。
駒ヶ根市のように、対外的には『市』ですが、実情は『町』程度の自治体なら、供託金の対象にならなくてもいいのではないかな。
一歩譲って、供託金を納めるか、一定数以上の推薦人を集めるなどの選択肢が用意されるというもの良さそうです。
売名行為を防止するのが供託金の主な趣旨のようですが、小さな地方自治体の議会選挙に立候補したからといっても大した話題にはなりません。
しかし、地方選挙のハードルを下げて、誰でも立候補できて、多方面に主張を届けられるようになると悪用する人が出てくることも考えられます。
有能な人材発掘というメリットと、遊び半分が入り込むかもしれないというデメリットを比較してみると、前者のためにまずはやってみて、デメリット対策は後からでもいいような気がします。
遊び半分の候補者が当選する可能性は、無投票でもない限り低いと思われるからです。
無投票になったら遊び半分が当選してしまうじゃないかという心配性の方が出てくるかもしれませんが、立候補のハードルが下がればやってみようと思う意欲のある人は必ずいるものです。
自分の住む自治体に誇りを持っていれば、無用な心配だと思えるのではないでしょうか。
たくさん立候補しすぎて広報に支障ができるくらい政治に関心が高まれば、その自治体の活性化は大変に期待できるということです。
2011年04月03日
・政治家は選挙に強いが危機管理は素人
福島県産のシイタケから規制値を超える放射性物質が検出されました。
放射性ヨウ素が1キログラム当たり3100ベクレル(暫定規制値は同2000ベクレル)、セシウムが同890ベクレル(同500ベクレル)でした。
キノコ類で規制値を上回ったのは初めてですが、キノコは国の出荷規制の対象になっていないので、県から出荷自粛を求められた農家のもの以外が市場で流通しています。
厚生労働省によると、キノコ類はセシウムを吸収しやすいとされるが、放射性ヨウ素も検出されており、露地栽培で付着したのではとみているという。
すでに摂取制限を経ている野菜で明らかになっていますが、ハウス栽培だからといって放射線の被害を避けることはできないようです。
ハウス内を換気する際に、放射性物質が浮遊する空気をハウスに取り込んでしまうからです。
福島第一原発の20kmから30kmでは屋内退避とされていますが、ハウス栽培と同様に開口部を目張りした密閉性の高い構造物に隔離されている場合を除いて、家の中にいることが放射能の危険から身を守ることには必ずしもなっていないようです。
最近の住宅なら強制的に24時間換気されているし、キッチンで換気扇を回せば大量の外気が流入します。
一般的な住宅では、何もしなくても一時間に住宅の容積の半分に当たる空気が入れ替わっているとみなされます。
屋内退避は、気休めの応急対策の位置付けてあるとの指摘が専門家から出ているのもなるほどです。
退避処置と安全性が機能していない実態を放置してきた政府がやっと改善に向けて「検討」を始めるようです。
枝野幸男官房長官は3日の記者会見で、福島第一原発の事故で避難や屋内退避を求める地域について、周辺の放射線量などの分析結果によっては見直す可能性を示しました。
避難や屋内退避について「一定の長期化は避けられない」と述べた上で「大気中や土壌の放射線量などのデータが積み重なっており、これを踏まえてさらに精緻(せいち)な対応ができるよう準備を進めている」と語っています。
福島第一原発からの距離と放射能汚染のリスクは、必ずしも比例していないことは、先ごろようやく公開されたSPEEDI(スピーディ)」と呼ばれる予測システムの解析結果を見れば明らかです。
風向きで被害地域が変わり、雨が降るタイミングで放射線濃度に違いが生じる。
予測が難しいのは納得できますが、平均的な気象状況から『より危険な地域』は絞り込めるはずです。
行政の使命は人民の安全確保なので、危険な地域から優先的に退避させることをもっと早くやっておくべきでした。
非科学的な同心円で避難地域を区分し続けたために、危険な地域を『安全』と偽らなければならず、危険性が比較的低い地域に『危険』というレッテルを貼ってしまった。
民主党の政治主導がもたらした人災です。
政治家の最も得意とするところは選挙であって、国民の安全管理ではありません。
危機管理の素人に過ぎない政治家が陣頭指揮を執れば、被害の拡大を未然に防ぐことができないのは容易に理解できます。
政府が責任感を持って国難に挑もうとする意欲は評価しますが、政治家の能力の及ぶところではないので、危機管理に精通した官僚や民間の助力を得て、素人にも分かりやすく状況分析と対応策の選択肢が示された段階で「政治決断」することに専念するべきだと思います。
折りしも、今は選挙の真っ最中です。
優れた政治家を選ぶことが求められているんですが、実態は選挙に強い候補者が議員になります。
政治家の本分は選挙にあると常々力説している小沢一郎の言葉は、真実なんです。
**本日の発電量 54.9kwh
-第一発電所 22.1kwh
-第二発電所 32.8kwh

にほんブログ村
放射性ヨウ素が1キログラム当たり3100ベクレル(暫定規制値は同2000ベクレル)、セシウムが同890ベクレル(同500ベクレル)でした。
キノコ類で規制値を上回ったのは初めてですが、キノコは国の出荷規制の対象になっていないので、県から出荷自粛を求められた農家のもの以外が市場で流通しています。
厚生労働省によると、キノコ類はセシウムを吸収しやすいとされるが、放射性ヨウ素も検出されており、露地栽培で付着したのではとみているという。
すでに摂取制限を経ている野菜で明らかになっていますが、ハウス栽培だからといって放射線の被害を避けることはできないようです。
ハウス内を換気する際に、放射性物質が浮遊する空気をハウスに取り込んでしまうからです。
福島第一原発の20kmから30kmでは屋内退避とされていますが、ハウス栽培と同様に開口部を目張りした密閉性の高い構造物に隔離されている場合を除いて、家の中にいることが放射能の危険から身を守ることには必ずしもなっていないようです。
最近の住宅なら強制的に24時間換気されているし、キッチンで換気扇を回せば大量の外気が流入します。
一般的な住宅では、何もしなくても一時間に住宅の容積の半分に当たる空気が入れ替わっているとみなされます。
屋内退避は、気休めの応急対策の位置付けてあるとの指摘が専門家から出ているのもなるほどです。
退避処置と安全性が機能していない実態を放置してきた政府がやっと改善に向けて「検討」を始めるようです。
枝野幸男官房長官は3日の記者会見で、福島第一原発の事故で避難や屋内退避を求める地域について、周辺の放射線量などの分析結果によっては見直す可能性を示しました。
避難や屋内退避について「一定の長期化は避けられない」と述べた上で「大気中や土壌の放射線量などのデータが積み重なっており、これを踏まえてさらに精緻(せいち)な対応ができるよう準備を進めている」と語っています。
福島第一原発からの距離と放射能汚染のリスクは、必ずしも比例していないことは、先ごろようやく公開されたSPEEDI(スピーディ)」と呼ばれる予測システムの解析結果を見れば明らかです。
風向きで被害地域が変わり、雨が降るタイミングで放射線濃度に違いが生じる。
予測が難しいのは納得できますが、平均的な気象状況から『より危険な地域』は絞り込めるはずです。
行政の使命は人民の安全確保なので、危険な地域から優先的に退避させることをもっと早くやっておくべきでした。
非科学的な同心円で避難地域を区分し続けたために、危険な地域を『安全』と偽らなければならず、危険性が比較的低い地域に『危険』というレッテルを貼ってしまった。
民主党の政治主導がもたらした人災です。
政治家の最も得意とするところは選挙であって、国民の安全管理ではありません。
危機管理の素人に過ぎない政治家が陣頭指揮を執れば、被害の拡大を未然に防ぐことができないのは容易に理解できます。
政府が責任感を持って国難に挑もうとする意欲は評価しますが、政治家の能力の及ぶところではないので、危機管理に精通した官僚や民間の助力を得て、素人にも分かりやすく状況分析と対応策の選択肢が示された段階で「政治決断」することに専念するべきだと思います。
折りしも、今は選挙の真っ最中です。
優れた政治家を選ぶことが求められているんですが、実態は選挙に強い候補者が議員になります。
政治家の本分は選挙にあると常々力説している小沢一郎の言葉は、真実なんです。
**本日の発電量 54.9kwh
-第一発電所 22.1kwh
-第二発電所 32.8kwh
にほんブログ村
2011年04月03日
・新しい地方選挙スタイル 2
多額の選挙資金の存在が地方議会への新たな人材の参入を阻んでいます。
費用をかけなければ選挙に出られないわけではありませんが、資金力が得票に結びつく度合いが非常に高いので、実際の選挙では素手で戦っても当選できる可能性は非常に少ない。
公職選挙法の制限事項を眺めていると、底辺にあるのは、金持ちの候補者による豊富な資金に任せた派手な選挙を押さえ込むことにあるように見えます。
選挙には金を使うのが前提として捉えられていて、一定の選挙資金が当然の出費になってしまっています。
発想を180度転換してみてはどうだろうか。
選挙に立候補する者には公共の広報媒体ができる限り協力し、個人の資金で広報活動に取り組まなくても有権者への情報伝達に不足がないようにするのがいい。
金持ちなら、これらに加えて既成の選挙戦術を取り入れるかもしれないが、有権者から「やり過ぎ」とバッシングを受けるような雰囲気が出来上がれば上々です。
このためには、公共放送であるNHKをはじめとして、テレビ、新聞、ラジオが重要な役割を果たします。
議員を選択するということが社会基盤の向上につながる公共事業だという意識をもって、情報媒体の義務として取り組むことが必要です。
個人のパフォーマンスが当落を決める現在の選挙制度に対して、報道機関として積極的に変革を求めるくらいの高い意識があってもいいはずだと思います。
有権者にも意識変革が求められます。
地元の名士や実力者が議員になるものだという既成概念や、地域の利益代表だから地元の了承なしには立候補させないといった狭い了見では、優れた人材を議会に送り込むことができません。
そもそも、議員に優れた資質を求めているのかどうかも疑問ですから、自治体を良くも悪くもするのが議会だという問題意識を持ってもらいましょう。
誤解されないように断っておきますが、地元の名士や実力者が政治の資質に乏しいといっているのではありません。
さらに優れた人材が他にもいるのではないかという想像力を働かしてもらいたいのです。
特に、若手の有能な人材がその辺にごろごろしているはずはなく、多くの場合は民間企業でバリバリと働いています。
地盤も看板もカバンも持たない、優れた資質を秘めた人材が一般企業のサラリーマンの中にいたとしても、現在の選挙制度ではリスクなしに一歩を踏み出すことは不可能に近い。
だからこそ、リスクを限りなく少なくして、サラリーマンの職にありながら議員になれるとしたら、地方議会への人材流入の可能性が飛躍的に向上します。
サラリーマンに限らず、25歳以上なら家庭の主婦や学生でも議員になれるハードルが思いっきり下がる。
子育て世代の母親が席巻する託児所付きの地方議会が誕生するかもしれません。
ワクワクしませんか?
費用をかけなければ選挙に出られないわけではありませんが、資金力が得票に結びつく度合いが非常に高いので、実際の選挙では素手で戦っても当選できる可能性は非常に少ない。
公職選挙法の制限事項を眺めていると、底辺にあるのは、金持ちの候補者による豊富な資金に任せた派手な選挙を押さえ込むことにあるように見えます。
選挙には金を使うのが前提として捉えられていて、一定の選挙資金が当然の出費になってしまっています。
発想を180度転換してみてはどうだろうか。
選挙に立候補する者には公共の広報媒体ができる限り協力し、個人の資金で広報活動に取り組まなくても有権者への情報伝達に不足がないようにするのがいい。
金持ちなら、これらに加えて既成の選挙戦術を取り入れるかもしれないが、有権者から「やり過ぎ」とバッシングを受けるような雰囲気が出来上がれば上々です。
このためには、公共放送であるNHKをはじめとして、テレビ、新聞、ラジオが重要な役割を果たします。
議員を選択するということが社会基盤の向上につながる公共事業だという意識をもって、情報媒体の義務として取り組むことが必要です。
個人のパフォーマンスが当落を決める現在の選挙制度に対して、報道機関として積極的に変革を求めるくらいの高い意識があってもいいはずだと思います。
有権者にも意識変革が求められます。
地元の名士や実力者が議員になるものだという既成概念や、地域の利益代表だから地元の了承なしには立候補させないといった狭い了見では、優れた人材を議会に送り込むことができません。
そもそも、議員に優れた資質を求めているのかどうかも疑問ですから、自治体を良くも悪くもするのが議会だという問題意識を持ってもらいましょう。
誤解されないように断っておきますが、地元の名士や実力者が政治の資質に乏しいといっているのではありません。
さらに優れた人材が他にもいるのではないかという想像力を働かしてもらいたいのです。
特に、若手の有能な人材がその辺にごろごろしているはずはなく、多くの場合は民間企業でバリバリと働いています。
地盤も看板もカバンも持たない、優れた資質を秘めた人材が一般企業のサラリーマンの中にいたとしても、現在の選挙制度ではリスクなしに一歩を踏み出すことは不可能に近い。
だからこそ、リスクを限りなく少なくして、サラリーマンの職にありながら議員になれるとしたら、地方議会への人材流入の可能性が飛躍的に向上します。
サラリーマンに限らず、25歳以上なら家庭の主婦や学生でも議員になれるハードルが思いっきり下がる。
子育て世代の母親が席巻する託児所付きの地方議会が誕生するかもしれません。
ワクワクしませんか?
2011年04月02日
・新しい地方選挙スタイル
志と、議員の資質があれば誰でも市議会議員に立候補できる環境を整えるためには、高いハードルがあります。
一般的な議員選挙で常套手段とされる選挙戦術は、どれも大金が必要なものばかりです。
事前活動
・街頭にポスターを散りばめる
・広報ビラをばら撒く
・多勢を動員した集会を開催する
・広い駐車場を完備した選挙事務所を賃借する
選挙期間
・街宣車と伴走車を連ねてウグイス嬢を使って候補者名を連呼する
・全域に電話を掛けまくる
・大量のハガキを送付する
・出陣式、総決起集会を大規模に派手に演出する
・広告代理店に依頼して新聞広告を出す
すべて公職選挙法で認められた選挙(政治)活動なので多額の選挙資金を用意できる候補者にとっては変える必要を感じていないでしょう。
また、政党の全面的支援を受ける候補者も税金から資金が流れ込むし、政党の看板で献金が集まるので、金にものを言わせる選挙で相手を圧倒することが有効な選挙戦術になります。
地道な市民活動やミニ集会、ネットを使った情報発信などでは、実際の選挙を勝ち抜くのは厳しいのが現状です。
一般庶民が立候補しようと思っても、これらの代替策は持ち得ないことがほとんどだと思います。
現状では、3バン(地盤、看板、カバン)を持っていなければ絶対的に不利な状況にあります。
今のままでは旧態依然とした地方議会を変えることは難しいので、選挙のあり方を抜本的に変えることを提案していかなくてはなりません。
地方議会を劇的に変えるための地方選挙のあり方について提案していきます。
まず第一に、公的広報の充実です。
現状は、選挙期間中に配布される『選挙公報』が唯一、公的に認められています。
これに加えて、あらゆる機会に市民(有権者)が候補者からのメッセージを受け取ることができる環境を整備したいですね。
一例として、役所や公民館に専用のパソコンとモニターを設置し、候補者の動画を映します。垂れ流しではなく選択できる画面が用意されていると効率がいい。
フリーがよいか、インタビュー形式で決められた設問に答えるのがいいか、スタイルはいろいろと考えられます。
必要なことは、誰でも、いつでも、どこでも、知りたいときに手軽に候補者を知ることができるような環境整備です。
駒ヶ根市には半ば公設のケーブルテレビ放送があるので、ほぼ常時、候補者の映像を流し続けることができます。
選挙公報と同時に候補者メッセージの放送番組表を各家庭に配布して、関心を持った候補者の顔と声をテレビを通じて確認することができます。
有線放送を使って告知すれば、さらに利用者が増えます。
知事や国政選挙になると『政見放送』がありますが、非常に堅苦しく、候補者もいつもの姿を見せられないし、有権者の視聴率も高くありません。
地方議員にも政見放送があってもいいんじゃないでしょうか。
少なくともローカルのケーブルテレビが存在する自治体は、すぐにでも取り入れられるはずです。
**本日の発電量 39.8kwh
-第一発電所 17.3kwh
-第二発電所 22.4kwh
一般的な議員選挙で常套手段とされる選挙戦術は、どれも大金が必要なものばかりです。
事前活動
・街頭にポスターを散りばめる
・広報ビラをばら撒く
・多勢を動員した集会を開催する
・広い駐車場を完備した選挙事務所を賃借する
選挙期間
・街宣車と伴走車を連ねてウグイス嬢を使って候補者名を連呼する
・全域に電話を掛けまくる
・大量のハガキを送付する
・出陣式、総決起集会を大規模に派手に演出する
・広告代理店に依頼して新聞広告を出す
すべて公職選挙法で認められた選挙(政治)活動なので多額の選挙資金を用意できる候補者にとっては変える必要を感じていないでしょう。
また、政党の全面的支援を受ける候補者も税金から資金が流れ込むし、政党の看板で献金が集まるので、金にものを言わせる選挙で相手を圧倒することが有効な選挙戦術になります。
地道な市民活動やミニ集会、ネットを使った情報発信などでは、実際の選挙を勝ち抜くのは厳しいのが現状です。
一般庶民が立候補しようと思っても、これらの代替策は持ち得ないことがほとんどだと思います。
現状では、3バン(地盤、看板、カバン)を持っていなければ絶対的に不利な状況にあります。
今のままでは旧態依然とした地方議会を変えることは難しいので、選挙のあり方を抜本的に変えることを提案していかなくてはなりません。
地方議会を劇的に変えるための地方選挙のあり方について提案していきます。
まず第一に、公的広報の充実です。
現状は、選挙期間中に配布される『選挙公報』が唯一、公的に認められています。
これに加えて、あらゆる機会に市民(有権者)が候補者からのメッセージを受け取ることができる環境を整備したいですね。
一例として、役所や公民館に専用のパソコンとモニターを設置し、候補者の動画を映します。垂れ流しではなく選択できる画面が用意されていると効率がいい。
フリーがよいか、インタビュー形式で決められた設問に答えるのがいいか、スタイルはいろいろと考えられます。
必要なことは、誰でも、いつでも、どこでも、知りたいときに手軽に候補者を知ることができるような環境整備です。
駒ヶ根市には半ば公設のケーブルテレビ放送があるので、ほぼ常時、候補者の映像を流し続けることができます。
選挙公報と同時に候補者メッセージの放送番組表を各家庭に配布して、関心を持った候補者の顔と声をテレビを通じて確認することができます。
有線放送を使って告知すれば、さらに利用者が増えます。
知事や国政選挙になると『政見放送』がありますが、非常に堅苦しく、候補者もいつもの姿を見せられないし、有権者の視聴率も高くありません。
地方議員にも政見放送があってもいいんじゃないでしょうか。
少なくともローカルのケーブルテレビが存在する自治体は、すぐにでも取り入れられるはずです。
**本日の発電量 39.8kwh
-第一発電所 17.3kwh
-第二発電所 22.4kwh
2011年04月02日
・市議会議員選挙の手続き 立候補受付前
駒ヶ根市議選の期間中は、ブログの更新ができません。
これまでに市民の皆さんにお示ししてきた資料をまとめましたので、ご参照ください。
●決意
市議会に市民目線への改革を求めたい。
課題は、地盤(組織)、看板(後ろ盾)、カバン(資金)の、いわゆる三バンを引き継ぐ者が議員になるところにある。
変えよう。
優れた政治センスや高い志を持つ普通のサラリーマンや主婦が議員になれる仕組みが求められている。
夜間や休日に議会を開催すれば仕事を続けながら議員活動ができる。
所得に応じた議員報酬に改め、高所得者はボランティアで議員を務めることを目標に改革を実行する。
●立候補者一覧(順不同、敬称略)
市会議員の選挙に立候補するには、いろいろと手続きが必要です。
選挙管理委員会に出向いて、立候補説明を受けてから必要な書類一式を渡されます。
一通りの説明を受けますが、初めてのことですからすべて飲み込むにはかなりの時間が必要です。
既成の選挙活動はまったくやらない予定ですが、公設掲示板にはポスターを貼らなければなりません。
義務ではないんですが、与えられた枠に何も貼っていないと誰が立候補したのか分からないので、有権者への最低限の告知のためにはポスター掲示は欠かせません。
写真やポスターの構成はデジカメと画像処理ソフトがあればそれなりに作成できますが、印刷は本業に頼みます。
公費で負担していただけるのですが、そのための書類もかなりの量です。
幸い、一昨年の衆院選でお世話になった印刷会社が、ポスターの印刷から書類の作成まで快く引き受けてくれたので助かりました。
人のつながりというのは、本当にありがたいと思いました。
市議会以上の選挙になると「供託金」を納めなければなりません。
市議会議員の場合は30万円ですが、選挙で一定の得票(駒ヶ根しだと100票くらい)を得るか、無投票だと返金されます。
法務局というところに行って書類を作ってもらい、八十二銀行伊那支店にある日本銀行の窓口で支払います。
以下は、私はやりませんが既成の選挙では必須です。
候補者名の連呼をしたい人は【遊説カー】を作って警察署でお墨付きをもらいます。
いわゆる電話作戦で有権者に電話をかけまくる場合は、電話機と電話要員に加えて電話番号リストを用意します。
個人情報の保護が重視されるようになってからは、新たなリストを手に入れるのが大変なようですが、多選を経ている候補者は膨大な個人情報をストックしているようです。
有権者のリストが必要なものに選挙はがきもありますが、ほとんどが紙ごみになるのでもったいないです。しかし、ハガキが来ないことに腹を立てる選挙通がいるので、無駄でも送ることが止められない候補者がほとんどです。
ハガキの印刷代は候補者の実費負担ですが、郵送料は公費負担です。
選挙ビラは市議会議員選挙では公布が認められていませんが、後援会通信や部内資料という名目で大量に印刷されてポスティング(個別配布)されることが一般的です。
出陣式や総決起集会で大勢の支援者を動員して気勢を上げるためには、会場を賃借したり飾ったりするための用意がいります。
趣旨によって選挙管理委員会に届け出ておくことも必要です。
選挙運動員を雇うのは合法ですが、人数や報酬に限りがあります。ボランティアと称して関係企業の社員を動員することは寄付行為に抵触するんですが、当たり前のようにやられています。
これらの選挙ツールは、選挙費用が多額になる主因なので、私の選挙ではすべてやりません。
立候補書類の事前審査というのが告示日の二週間前くらいに実施されます。
申請書類の一式を前もって点検してもらう機会です。
立候補当日に書類の不備が見つかると対応が大変なので、分かる範囲で書き込んでいって、後は教えてもらいます。
これまでに市民の皆さんにお示ししてきた資料をまとめましたので、ご参照ください。
●決意
市議会に市民目線への改革を求めたい。
課題は、地盤(組織)、看板(後ろ盾)、カバン(資金)の、いわゆる三バンを引き継ぐ者が議員になるところにある。
変えよう。
優れた政治センスや高い志を持つ普通のサラリーマンや主婦が議員になれる仕組みが求められている。
夜間や休日に議会を開催すれば仕事を続けながら議員活動ができる。
所得に応じた議員報酬に改め、高所得者はボランティアで議員を務めることを目標に改革を実行する。
◇ ◇ ◇ ◇
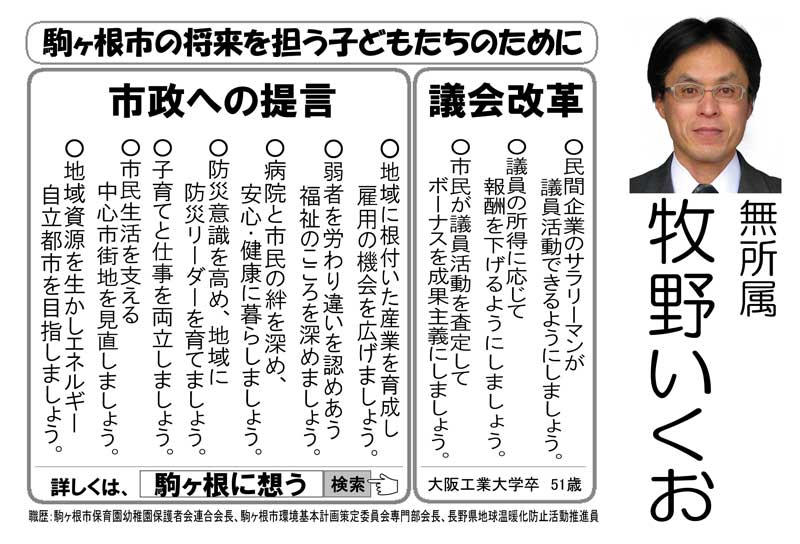
◇ ◇ ◇ ◇
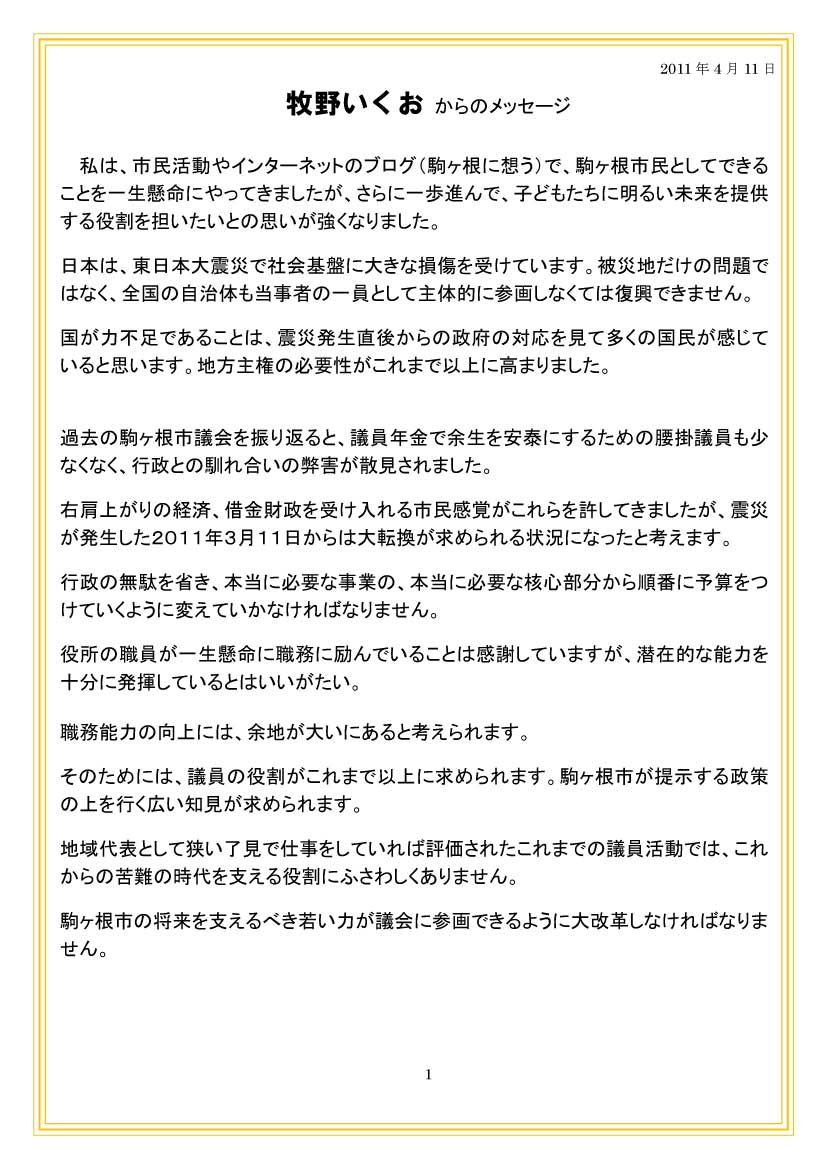
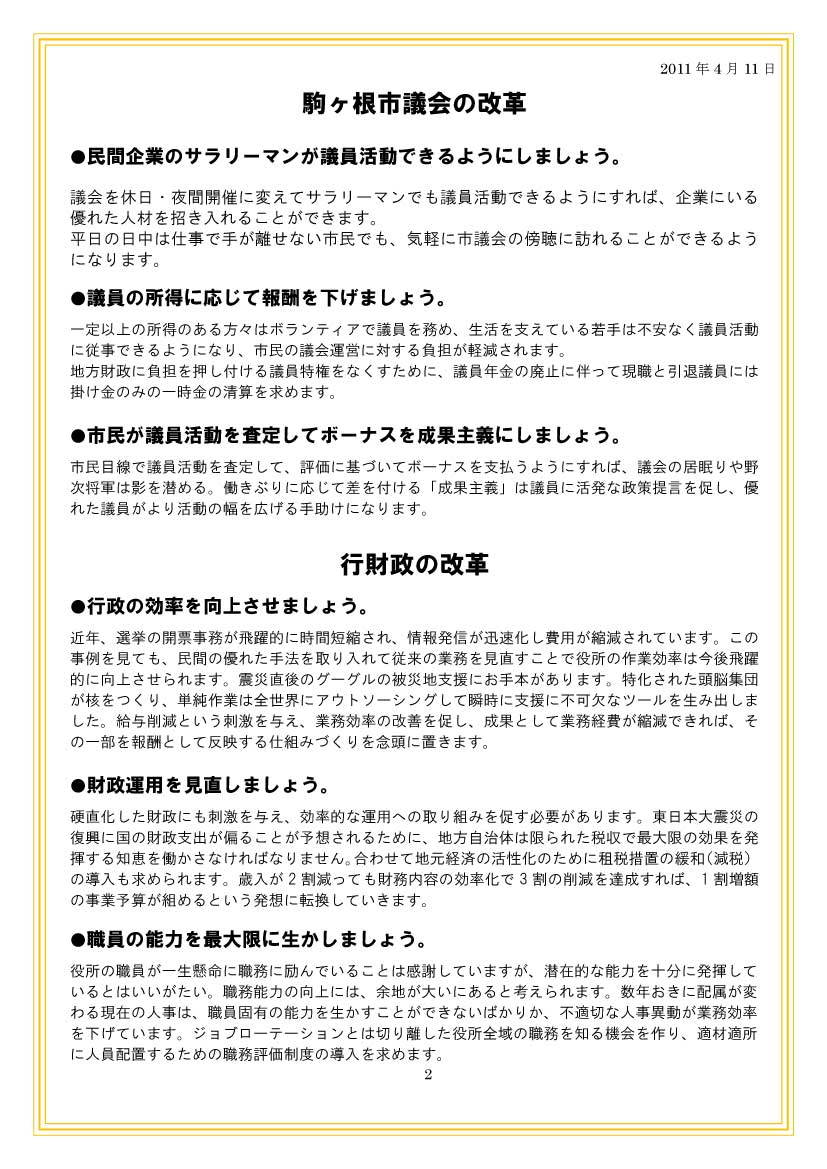
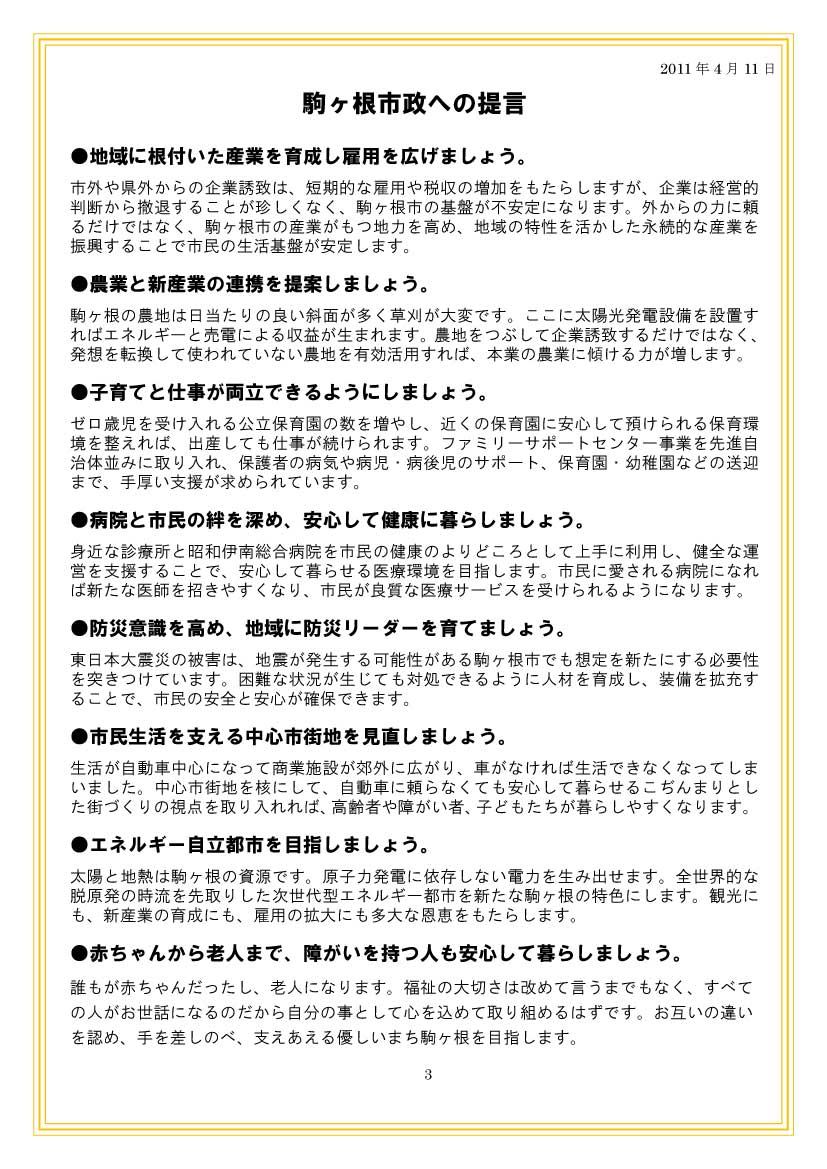
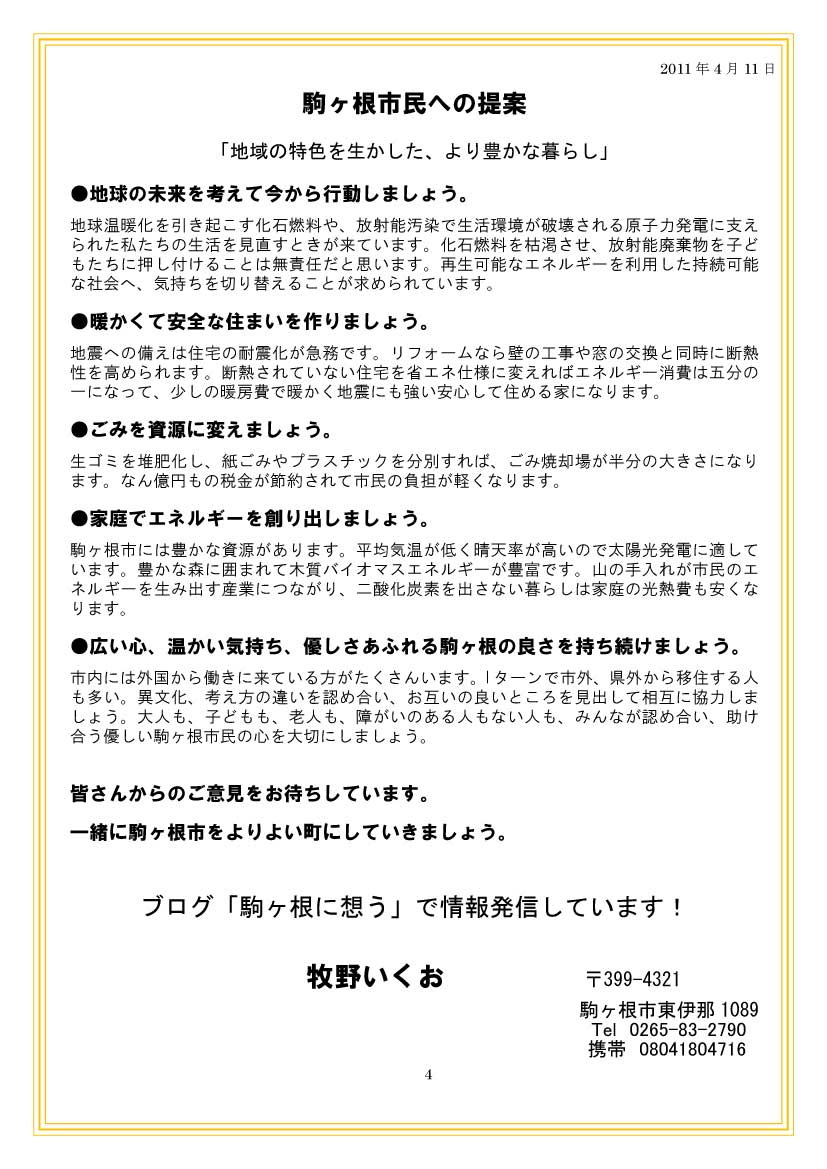
駒ヶ根市をより良い町、暮らしやすい町にしたいと思って行動してきた足跡です。
市民の目線で情報を集め、将来を担う子どもたちに、より良い駒ヶ根を残したいと思ってきました。
一部ですが参考にしていただきまして、私の駒ヶ根市議会議員として目指す方向性を確認してください。
●立候補者一覧(順不同、敬称略)
| 候補者名 | よみ | 政党 | 地区 |
| 牧野 郁生 | まきのいくお | 無所属 | 東伊那 |
| 阿竹 麗 | あたけうらら | 無所属 | 福岡 |
| 伊東 正人 | いとうまさと | 無所属 | 東伊那 |
| 岩崎 康男 | いわさきやすお | 無所属 | 町二区 |
| 塩沢 京子 | しおざわきょうこ | 無所属 | 上穂町 |
| 竹村 誉 | たけむらほまれ | 共産党 | 中沢 |
| 三原 一高 | みはらかずたか | 無所属 | 福岡 |
| 長谷部 清人 | はせべきよと | 無所属 | 上穂町 |
| 下平 順一 | しもだいらじゅんいち | 無所属 | 北割二 |
| 坂本 裕彦 | さかもとやすひこ | 共産党 | 福岡 |
| 宮沢 勝人 | みやざわかつと | 無所属 | 上赤須 |
| 坂井 昌平 | さかいしょうへい | 無所属 | 中沢 |
| 小林 敏夫 | こばやしとしお | 無所属 | 南割 |
| 菅沼 孝夫 | すがぬまたかお | 無所属 | 北割一 |
| 加治木 今 | かじきいま | 無所属 | 町四区 |
| 竹内 正寛 | たけうちまさひろ | 公明党 | 町三区 |
| 中坪 宏明 | なかつぼひろあき | 無所属 | 下平 |
市会議員の選挙に立候補するには、いろいろと手続きが必要です。
選挙管理委員会に出向いて、立候補説明を受けてから必要な書類一式を渡されます。
一通りの説明を受けますが、初めてのことですからすべて飲み込むにはかなりの時間が必要です。
既成の選挙活動はまったくやらない予定ですが、公設掲示板にはポスターを貼らなければなりません。
義務ではないんですが、与えられた枠に何も貼っていないと誰が立候補したのか分からないので、有権者への最低限の告知のためにはポスター掲示は欠かせません。
写真やポスターの構成はデジカメと画像処理ソフトがあればそれなりに作成できますが、印刷は本業に頼みます。
公費で負担していただけるのですが、そのための書類もかなりの量です。
幸い、一昨年の衆院選でお世話になった印刷会社が、ポスターの印刷から書類の作成まで快く引き受けてくれたので助かりました。
人のつながりというのは、本当にありがたいと思いました。
市議会以上の選挙になると「供託金」を納めなければなりません。
市議会議員の場合は30万円ですが、選挙で一定の得票(駒ヶ根しだと100票くらい)を得るか、無投票だと返金されます。
法務局というところに行って書類を作ってもらい、八十二銀行伊那支店にある日本銀行の窓口で支払います。
以下は、私はやりませんが既成の選挙では必須です。
候補者名の連呼をしたい人は【遊説カー】を作って警察署でお墨付きをもらいます。
いわゆる電話作戦で有権者に電話をかけまくる場合は、電話機と電話要員に加えて電話番号リストを用意します。
個人情報の保護が重視されるようになってからは、新たなリストを手に入れるのが大変なようですが、多選を経ている候補者は膨大な個人情報をストックしているようです。
有権者のリストが必要なものに選挙はがきもありますが、ほとんどが紙ごみになるのでもったいないです。しかし、ハガキが来ないことに腹を立てる選挙通がいるので、無駄でも送ることが止められない候補者がほとんどです。
ハガキの印刷代は候補者の実費負担ですが、郵送料は公費負担です。
選挙ビラは市議会議員選挙では公布が認められていませんが、後援会通信や部内資料という名目で大量に印刷されてポスティング(個別配布)されることが一般的です。
出陣式や総決起集会で大勢の支援者を動員して気勢を上げるためには、会場を賃借したり飾ったりするための用意がいります。
趣旨によって選挙管理委員会に届け出ておくことも必要です。
選挙運動員を雇うのは合法ですが、人数や報酬に限りがあります。ボランティアと称して関係企業の社員を動員することは寄付行為に抵触するんですが、当たり前のようにやられています。
これらの選挙ツールは、選挙費用が多額になる主因なので、私の選挙ではすべてやりません。
立候補書類の事前審査というのが告示日の二週間前くらいに実施されます。
申請書類の一式を前もって点検してもらう機会です。
立候補当日に書類の不備が見つかると対応が大変なので、分かる範囲で書き込んでいって、後は教えてもらいます。
2011年04月01日
・3月の太陽光発電の実績
3月の太陽光発電の実績をまとめます。
***総発電量 1607.7kwh
***第一発電所(南南西、30.8度、4.995kw)
発電量 702.8 kwh
モジュール容量あたり 140.7 kwh/kw
日最大発電量 30.7 kwh
日平均発電量 22.7 kwh
月平均発電効率 11.7% ※1
***第二発電所(西南西、16.7度、7.03kw)
発電量 904.8 kwh
モジュール容量あたり 128.7kwh/kw
日最大発電量 39.6 kwh
日平均発電量 29.2 kwh
月平均発電効率 12.2% ※1
※1: 月平均発電効率は、モジュール面積1平方メートルあたりの月間発電量を、月の傾斜面日射量で除した比率。明らかな異常値ならびに、日発電率と平均との差が標準偏差の二倍を超える日のデータは除外しました。
日射量が増加するにつれて発電量が増加し、パワコンの容量を超えることが多くなりました。パワコンの容量以上の発電はカットされるので結果として発電効率が低下しています。
積雪により発電できなかった日も二日ありました。
今日の太陽光発電量 72.8 kwh
第一発電所 31.1 kwh
第二発電所 41.7 kwh
一日の発電量が過去最大を記録しました。

にほんブログ村
***総発電量 1607.7kwh
***第一発電所(南南西、30.8度、4.995kw)
発電量 702.8 kwh
モジュール容量あたり 140.7 kwh/kw
日最大発電量 30.7 kwh
日平均発電量 22.7 kwh
月平均発電効率 11.7% ※1
***第二発電所(西南西、16.7度、7.03kw)
発電量 904.8 kwh
モジュール容量あたり 128.7kwh/kw
日最大発電量 39.6 kwh
日平均発電量 29.2 kwh
月平均発電効率 12.2% ※1
※1: 月平均発電効率は、モジュール面積1平方メートルあたりの月間発電量を、月の傾斜面日射量で除した比率。明らかな異常値ならびに、日発電率と平均との差が標準偏差の二倍を超える日のデータは除外しました。
日射量が増加するにつれて発電量が増加し、パワコンの容量を超えることが多くなりました。パワコンの容量以上の発電はカットされるので結果として発電効率が低下しています。
積雪により発電できなかった日も二日ありました。
今日の太陽光発電量 72.8 kwh
第一発電所 31.1 kwh
第二発電所 41.7 kwh
一日の発電量が過去最大を記録しました。
にほんブログ村
2011年04月01日
・避難所では母乳を与えましょう
東日本を襲った大震災と大津波で被災して、避難所での生活が長期化している乳児が少なくないと思います。
避難所ではインフルエンザなど感染症の流行が懸念されているので、特に乳児や高齢者らは感染が深刻な症状を招きかねません。
予防のために乳児には母乳を与えることが薦められています。
「日本母乳の会」の役員で小児科医の堀内勁(たけし)氏は、母親の血液からできる母乳にはリンパ球などの白血球が多く殺菌力があり、感染症予防に役立つ-として母乳を奨励しています。
乳首から直接吸わせることで安心感を与えるだけではなく、母親にもオキシトシンというホルモンが分泌され、心の安定につながるという効果も期待されます。
乳児だけでなく、震災のショックで“赤ちゃん返り”した幼児についても、「4歳くらいまでなら、母乳がでない場合でもおっぱいを吸わせてほしい。震災直後の今、少しでも不安を解消することが後の心の安定につながる」という。
被災地では母乳が出にくくなった母親も増えており、同会は「根気よく吸わせ続ければ必ず回復する。母乳を出すためにも周囲の人は母親に優先的に食事を回してほしい」と訴えています。
一方、粉ミルクで授乳している乳児には、使い捨ての紙コップの利用が奨励されています。
避難所では、消毒が必要な哺乳瓶の衛生管理が難しく、災害時は使い捨ての紙コップを利用するのが一番安全だからです。
紙コップを使った授乳方法の注意点は、
(1)赤ちゃんの手が紙コップにぶつからないようにタオルで赤ちゃんを包む
(2)赤ちゃんを縦抱きにする
(3)紙コップ内に少なくとも半分以上の乳汁を入れる
(4)赤ちゃんの口元で紙コップを少し傾け、2、3滴を目安に流し込む
さらに、3割以上はこぼれるので、多めの乳汁を用意する。コップを下唇に軽くのせ、上唇が乳汁に触れるようにするのがいい-ということです。
また、避難所で水道水が手に入らず、ペットボトルのミネラルウオーターを使う場合は注意が必要です。
カルシウムやマグネシウムといったミネラル成分は赤ちゃんの腎臓に負担をかけてしまうからです。
50~60程度の硬度の低いものが最適ですが、硬度100程度のものでも、10分ほどぐらぐら沸騰させればミネラル分が低下するので調乳に使えるようですから、乳幼児と一緒に避難されている方は十分にご配慮ねがいます。
避難所ではインフルエンザなど感染症の流行が懸念されているので、特に乳児や高齢者らは感染が深刻な症状を招きかねません。
予防のために乳児には母乳を与えることが薦められています。
「日本母乳の会」の役員で小児科医の堀内勁(たけし)氏は、母親の血液からできる母乳にはリンパ球などの白血球が多く殺菌力があり、感染症予防に役立つ-として母乳を奨励しています。
乳首から直接吸わせることで安心感を与えるだけではなく、母親にもオキシトシンというホルモンが分泌され、心の安定につながるという効果も期待されます。
乳児だけでなく、震災のショックで“赤ちゃん返り”した幼児についても、「4歳くらいまでなら、母乳がでない場合でもおっぱいを吸わせてほしい。震災直後の今、少しでも不安を解消することが後の心の安定につながる」という。
被災地では母乳が出にくくなった母親も増えており、同会は「根気よく吸わせ続ければ必ず回復する。母乳を出すためにも周囲の人は母親に優先的に食事を回してほしい」と訴えています。
一方、粉ミルクで授乳している乳児には、使い捨ての紙コップの利用が奨励されています。
避難所では、消毒が必要な哺乳瓶の衛生管理が難しく、災害時は使い捨ての紙コップを利用するのが一番安全だからです。
紙コップを使った授乳方法の注意点は、
(1)赤ちゃんの手が紙コップにぶつからないようにタオルで赤ちゃんを包む
(2)赤ちゃんを縦抱きにする
(3)紙コップ内に少なくとも半分以上の乳汁を入れる
(4)赤ちゃんの口元で紙コップを少し傾け、2、3滴を目安に流し込む
さらに、3割以上はこぼれるので、多めの乳汁を用意する。コップを下唇に軽くのせ、上唇が乳汁に触れるようにするのがいい-ということです。
また、避難所で水道水が手に入らず、ペットボトルのミネラルウオーターを使う場合は注意が必要です。
カルシウムやマグネシウムといったミネラル成分は赤ちゃんの腎臓に負担をかけてしまうからです。
50~60程度の硬度の低いものが最適ですが、硬度100程度のものでも、10分ほどぐらぐら沸騰させればミネラル分が低下するので調乳に使えるようですから、乳幼児と一緒に避難されている方は十分にご配慮ねがいます。
2011年04月01日
・専門家の使命は市民の安全よりも原発を守る
東京電力の福島第一原発事故で、最も恐れていたことの一つが現実になりました。
地下水の放射能汚染です。
トレンチに貯まった大量の水から、高濃度の放射線が観測されたときに、地下水に造詣のある人の多くが恐怖を感じたと思います。
さらに、プラントの現場に精通していれば、『トレンチ』という構造物がどれほど簡易に作られているかも知っているので、その時点で地下水が危ないことは関係者なら知っていて当然です。
拡散がある程度予測できる空中飛散と違って、地下水は水脈の多くが未知なので、どこにどれだけ被害が広がるのかまったく予想できません。
リスクがあまりにも大きいので、東電も情報を小出しにすることが精一杯の自衛手段だったと思います。
地下水は目に見えないし、通常の生活では接する機会も少ないので、存在を意識することはほとんどないと思います。
駒ヶ根市を例にとると、とうとうと流れる天竜川よりも大量の水脈が天竜川の東側に存在するのではないかと言われています。
目に見える流れよりも大きな水が地下で動いていることがあるといいます。
地下水は地上からの放射能汚染に強いと思われていましたが、水脈を介した拡散には手の打ちようがありません。
この期に及んでもテレビでは東京電力から多額の補助金をもらっている専門家が「飲んでも食べても大丈夫」「避難地域は広げなくてもいい」と楽観的なコメントを発し続けています。
今朝は東京工業大学の松本義久准教授が、「宇宙ステーションの放射線のレベルに比べればぜんぜん少ない」と『安全性』を強調していました。
事故が起きる前までは、原子力発電所が生活環境に与える影響は、「自然放射線による線量(年間世界平均2.4ミリシーベルト)よりもはるかに低い」が、安全性を訴える決まり文句でした。
それが、放射能汚染が深刻になってくるとCTスキャンに格上げされ、さらに危機的な状況に陥ると宇宙ステーションの被ばくを引き合いにしなければ安全性が説明できなくなってしまいました。
彼らは原子力発電の安全性を社会に訴えるのが使命なんだとつくづく実感させられます。
では、市民の安全を守るのは誰なのかというと、地方自治体や国でしょう。
原子力から受ける恩恵を優先して、市民の安全が軽んじられてきた過去を猛省する必要があります。
原子力の専門家が安全性を打ち出しても、住民を守るべき自治体は『想定外』の危険を前提に、最悪の事態に対処することを念頭に置くべきです。
原子力発電所の事故がもたらす甚大な社会的な被害に備えるには、巨額の基盤整備が不可欠になります。
発電電源として社会経済的に成り立たなくなるのは目に見えているので、エネルギー消費量の総量抑制が求められると同時に、次世代エネルギーと考えられていた技術の前倒しが急務です。
駒ヶ根市議会議員になろうと決意したのは、地方自治体の住民を守る意識が希薄だったのは議会に危機感が欠けていただと思うからです。
次世代エネルギーの普及に率先して取り組んできた経験を生かすときが来たという使命感があるからです。
震災に直面して多くの人が「自分には何ができるだろう?」と自問したと思います。
私にできることは、激変する社会に対応できるように市議会に働きかけることと、自治体に次世代エネルギーへの対応を促す役割だと思いました。
自分でなければできないことで貢献することが、自分にできる最善の行いだと思います。
**市民は安全だが東大は危険?
事故直後、東大の中では文書が回り、「換気を止めること、ドラフト(化学実験などで使う空気が漏れない装置で、これを使うと外気が研究室に入る)」を停止するよう命令があった。
武田邦彦 (中部大学) 原発 緊急の緊急(42) 海の汚染より
地下水の放射能汚染です。
トレンチに貯まった大量の水から、高濃度の放射線が観測されたときに、地下水に造詣のある人の多くが恐怖を感じたと思います。
さらに、プラントの現場に精通していれば、『トレンチ』という構造物がどれほど簡易に作られているかも知っているので、その時点で地下水が危ないことは関係者なら知っていて当然です。
拡散がある程度予測できる空中飛散と違って、地下水は水脈の多くが未知なので、どこにどれだけ被害が広がるのかまったく予想できません。
リスクがあまりにも大きいので、東電も情報を小出しにすることが精一杯の自衛手段だったと思います。
地下水は目に見えないし、通常の生活では接する機会も少ないので、存在を意識することはほとんどないと思います。
駒ヶ根市を例にとると、とうとうと流れる天竜川よりも大量の水脈が天竜川の東側に存在するのではないかと言われています。
目に見える流れよりも大きな水が地下で動いていることがあるといいます。
地下水は地上からの放射能汚染に強いと思われていましたが、水脈を介した拡散には手の打ちようがありません。
この期に及んでもテレビでは東京電力から多額の補助金をもらっている専門家が「飲んでも食べても大丈夫」「避難地域は広げなくてもいい」と楽観的なコメントを発し続けています。
今朝は東京工業大学の松本義久准教授が、「宇宙ステーションの放射線のレベルに比べればぜんぜん少ない」と『安全性』を強調していました。
事故が起きる前までは、原子力発電所が生活環境に与える影響は、「自然放射線による線量(年間世界平均2.4ミリシーベルト)よりもはるかに低い」が、安全性を訴える決まり文句でした。
それが、放射能汚染が深刻になってくるとCTスキャンに格上げされ、さらに危機的な状況に陥ると宇宙ステーションの被ばくを引き合いにしなければ安全性が説明できなくなってしまいました。
彼らは原子力発電の安全性を社会に訴えるのが使命なんだとつくづく実感させられます。
では、市民の安全を守るのは誰なのかというと、地方自治体や国でしょう。
原子力から受ける恩恵を優先して、市民の安全が軽んじられてきた過去を猛省する必要があります。
原子力の専門家が安全性を打ち出しても、住民を守るべき自治体は『想定外』の危険を前提に、最悪の事態に対処することを念頭に置くべきです。
原子力発電所の事故がもたらす甚大な社会的な被害に備えるには、巨額の基盤整備が不可欠になります。
発電電源として社会経済的に成り立たなくなるのは目に見えているので、エネルギー消費量の総量抑制が求められると同時に、次世代エネルギーと考えられていた技術の前倒しが急務です。
駒ヶ根市議会議員になろうと決意したのは、地方自治体の住民を守る意識が希薄だったのは議会に危機感が欠けていただと思うからです。
次世代エネルギーの普及に率先して取り組んできた経験を生かすときが来たという使命感があるからです。
震災に直面して多くの人が「自分には何ができるだろう?」と自問したと思います。
私にできることは、激変する社会に対応できるように市議会に働きかけることと、自治体に次世代エネルギーへの対応を促す役割だと思いました。
自分でなければできないことで貢献することが、自分にできる最善の行いだと思います。
**市民は安全だが東大は危険?
事故直後、東大の中では文書が回り、「換気を止めること、ドラフト(化学実験などで使う空気が漏れない装置で、これを使うと外気が研究室に入る)」を停止するよう命令があった。
武田邦彦 (中部大学) 原発 緊急の緊急(42) 海の汚染より







