2009年05月20日
・下水道をやめて33億節減、飯田市
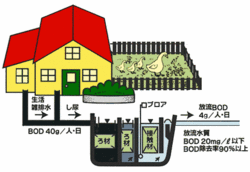 飯田市が下水道事業の見直しに着手しました。
飯田市が下水道事業の見直しに着手しました。下水道管を延々と敷設するこれまでのやり方をやめて、離れた場所は合併浄化槽で処理する合理的な方針転換です。
日本全国で下水道が完備されつつありますが、本来の目的は衛生状態の向上にあったものが、いつの間にか土木・建設としての事業規模を目的としたものにすり替えられてしまいました。
駒ヶ根市を例に挙げると、環境リスク学の権威である中西準子氏に依頼して、下水道施設の効果的な事業案を数十年前に計画しています。
集約されていて下水管網が効果的に配置できる地域と、離散していて合併浄化槽を単独で配置した方が有効な地域が明確に分離されました。
しかし、実現された計画は、どこまでも下水管でつなぐでたらめなものに換えられてしまいました。
なぜかというと、下水管を敷設すると道路掘り下げ、埋め戻すという単純で高収益な土木事業が発生するからです。
人家が離れている田舎ほど穴掘りの延長が無意味に長くなります。
土建屋にはおいしいの一言です。
飯田市では遅ればせながら無意味な穴掘りをやめることで33億円の事業費が圧縮されます。
地方の自治体で計画終了間際に見直しただけでこれだけの削減効果があるんですから、日本全国で計画当初からの無駄は天文学的な金額になると予想されます。
少なくとも20年ほど前から、下水道や集落排水事業は住宅密集地に限って採用するべきで、それ以外は小集落単位や個別単位の浄化槽対応が合理的であると専門家が訴えていました。
これを無視したのが土木利権に後押しされた国であります。
快適な生活を夢見ている市民には、下水道は何の抵抗もなく受け入れられる。
多少の負担は伴っても水洗便所を手に入れたいと願う大多数の庶民の願いに支えられて、下水道事業は闇に触れられぬままに終焉を迎えようとしています。
作ることが目的ですから、今後の維持管理と水質浄化のコストバランスなどは当初から考慮されていません。
本当に必要な下水処理場は多額の維持費を投じてでも永続させることが求められますが、意味もなく作られた施設は廃止されるところがすくなからず出てくると思われます。
下水道普及率が90%を越えたあたりから作るものには、そういった可能性が高いものが含まれます。
下水処理場が本当に必要なのか。
下水が完備していなくても流域の水質が保たれている場所に作られた、説得力のない施設が駒ヶ根市にもあります。
流域ごとに自然浄化力と排水の汚濁度をバランスよく考慮して、無駄な下水処理場をこれ以上増やさないことが求められていると思います。





