2010年10月06日
・太陽光発電の電圧抑制の実態
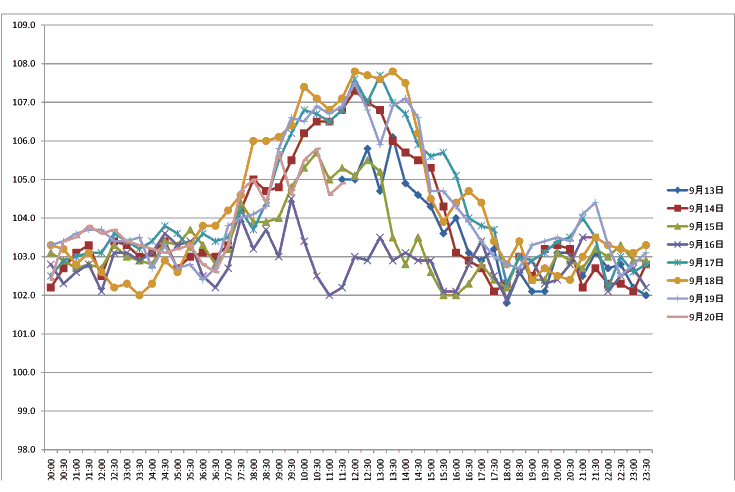
太陽光発電システムで電圧抑制が発生する状況が判明しました。
中部電力で測定した電圧変化データを入手しました。
明らかに107Vを超えてますね。
法令供給電圧は、低圧の場合101Vプラスマイナス6Vです。
107Vを超えてはならないのです。
データーの解析を終えた中部電力の担当者からは、「柱上トランスのタップで調整して5V下げます」と、連絡が入りました。
5V下がれば、97V~103Vの範囲で推移することになり、パワコンで電圧抑制が発生することはなくなります。
屋内のコンセント電圧は109Vを超えることもあったので、電気製品への影響も侮れない状況でした。
安心して太陽光発電できる状況になります。
電圧抑制でどの程度の発電ロスが生じていたのかは調べようがありません。
中電のデーターから類推すると、107Vを超えた時間帯は原則としてパワコンは抑制機能が働いて売電できません。
ピークで4時間ほどです。
該当時間の発電実績からすると30kwhが電圧抑制によって喪失していた計算になります。
約1500円ですね。
一週間に一回の割合で、同程度の電圧抑制が生じていたと仮定すると、年間で7万~8万円の損失の可能性があります。
太陽光発電を設置されている方は、休日の昼間に、パワコンの瞬間発電量がおかしな動きをしていないか、確かめた方がいいですよ。
テスターがあれば、発電量がピークの頃に、コンセントの電圧を測ってもましょう。
107Vを超えていれば、電圧抑制がかかっていると思っていい。
おかしいと思ったら、太陽光発電設備の工事会社に相談しましょう。
ユーザーが申し立てをしなければ、電力会社は何もしてくれませんからね。





