2007年07月06日
・田中前長野知事だけの新党日本へ
 長野県の前知事、田中康夫氏が党首を務める新党日本では、荒井広幸参院議員と滝実衆院議が離党を表明しました。
長野県の前知事、田中康夫氏が党首を務める新党日本では、荒井広幸参院議員と滝実衆院議が離党を表明しました。両氏は田中代表の党運営に不満の意を示し、5日の役員会で同党を解党するよう求めたものの同代表に拒否されたため、一方的に「解党」を宣言して退席しましたが、解党宣言は参院選後の与党との連携を視野に入れたものとみられています。
田中氏はこの後、党本部で記者会見し、「解党は有権者への冒涜で受け入れられない」と述べ、両氏の対応を批判したうえで離党届も受け取っていないとした。
また、参院選比例区で議席獲得を目指す方針は「いささかの揺るぎもない」と述べている。
荒井氏、滝氏も国会内で記者会見し、荒井氏は自民党復党について、「今のところない」とする一方で、「将来について今の段階で発言できる状況にはない」と含みも持たせた。
二人の離党による直接の影響は、政党助成金でしょう。
新党日本が2006年に受けていた政党助成金は一億6千万円だが、これがゼロになってしまうからです。
参院選で最低一人が当選し、さらに有効投票数の2%を獲得すれば政党助成金の受給資格が得られますが、世論調査では比例代表で新党日本に投票するとの答えは0.3%にとどまっている状況からすると、あり得ない。
新党日本は平成17年9月、郵政民営化に反対した「造反組」議員を中心に結成された、いわば掃き溜め政党でした。
結党時にいた3名の衆院議員は、小林興起氏と青山丘氏が国民新党へ移籍し同党から参院選比例区出馬。
滝実氏は離党して今後無所属へ。
参議院議員は、荒井広幸が離党して今後無所属へ。
途中で国民新党から移籍してきた長谷川憲正にいたっては、国民新党へ再移籍しています。
彼らは郵政民営化への反乱で自民党を追い出されましたが、政治家の質としては根っからの自民党ですから、田中康夫氏と行動を共にすることは初めから無理がありました。
新党日本の評価が低かったのは、これら元自民党のごみ議員の掃き溜めだったからですが、ごみが排出されたことで、政党として本来の姿を目指せるのではないかと思います。
2007年07月05日
・村井知事が兼業市議にお墨付き
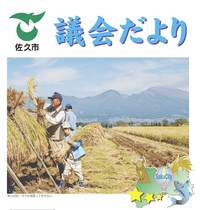 市議会議員でありながら佐久市から工事を請け負っていた井上元市議が失職していた問題で、長野県の村井知事は失職を不当とする裁決を下しました。
市議会議員でありながら佐久市から工事を請け負っていた井上元市議が失職していた問題で、長野県の村井知事は失職を不当とする裁決を下しました。失職の原因は、同市議が役員を務める塗装会社が、佐久市から32%の請負業務があり、地方自治法の兼業禁止規定によって処罰されていました。
ところが、村井知事は、随意契約分を除外して請負比率を計算上引き下げ、過去の最高裁の判例の数字を引き合いに、この業者を救いました。
さらに、売り上げに家賃収入まで含めて分母を大きくし、請負比率が小さくなるように細工した計算に基づくもので、知事側の業者を救うための工夫が随所にみられます。
本来の処罰は、主要業務に占める比率であって、家賃収入が塗装業者の主要業務とする判断はおかしい。
また、随意契約そのものが、行政と業者の馴れ合い体質に起因しているのだから、加算して当然であって、除外する理由が判らない。
佐久市議会の対応が注目されますが、村井知事が不当な兼業をごり押ししてまで業者を守ろうとする理由がどこにあるのでしょうか。 続きを読む
2007年07月04日
・電動アシスト自転車でCO2削減
 電動アシスト自転車を買いました。
電動アシスト自転車を買いました。公共交通機関が貧弱な駒ヶ根市民としては、自動車が生活に不可欠なことは避けがたい現実なのですが、近場の移動なら自転車で代替できるはずです。
しかし、南北は良しとしても市内を東西に移動するのはアップダウンがきつくて、気軽に自転車に乗って出かけようとは思いません。
そこで、少しばかり電気の力を借りて楽に走れる電動アシスト自転車を選択しました。
これまでにも近場の移動はオートバイだったので、自動車に比べればCO2排出量は1/3程度でしたが、化石燃料の利用効率としてはまだまだ低いので、「さらに削減するためには自転車だ」と思い切りました。
坂の上り下りが連続する駒ヶ根の地形に適した機種として、走行中に充電できるサンヨーのエナクルを選択しました。
定価が83800円と高価な買い物ですが、ネット通販に大量に出回っているので、最安値を探したところ、送料込みでも55400円と34%offで買えました。
早速、使い始めたところ、半分程度は自分の脚力で走らなければならないので、楽チンとは言えないまでも、ママチャリだと押さなければ上がれない坂道でもモーターのアシストのおかげで走りきれました。
バッテリーの容量は、最大で56kmの走行距離とされていますが、駒ヶ根市内だと15km程度で空になってしまうので、市外へ足を伸ばすことはできません。
使い始めて困ったのが、バッテリーが中途半端に減っているときにどうするか。
ニッケル水素電池の特性で、残量があるところに充電するとメモリー効果といって充電容量が小さくなってしまいます。
だからといって、リフレッシュ充電ばかりしていては、エネルギーの無駄遣いに加えて充電時間が、ものすごく長くなってしまう。
結局、さらに1万4千円出費して、バッテリーを2本交互に使うことにしました。
重いバッテリー(1.6kg)を持ち歩くのは大変ですが、バッテリー残量が中途半端なときには、帰り道の上り坂でバッテリーが切れしまって押して歩くよりはましです。
ランニングコストの点では、バッテリーの使用可能期間と価格を考慮すれば、バイクとそれほど違わないようです。
しかし、エネルギー消費量は格段に低減できるのと、足に軽い負荷でトレーニング効果があることも考え合わせれば、体を含めが環境に良い乗り物だと思います。
2007年07月03日
・伊那市民不在の用地選定
 6月29日、伊那市役所でごみ焼却施設の用地選定委員会が開催されました。
6月29日、伊那市役所でごみ焼却施設の用地選定委員会が開催されました。これに先立って、ごみ問題の講演会があり、ごみ処理の現状が語られると共に、処理施設建設の問題点も指摘されました。
この中で力説されたのは、住民参加と情報公開です。
行政に求められるこの二点の重要性は、あらためて言うまでもないはずですが、伊那市においては敢えて釘を指しておく必要があったのだとあとでわかりました。
用地選定委員会を傍聴した伊那市民の話を総合すると、引き続き市役所会議室で行われた用地選定委員会では、事務局である伊那市と伊那市議会が委員会の主導権を握り、市民の声を押しつぶしてしまったからです。
極めつけは、委員長選出の場面。
事務局はあらかじめ下打ち合わせをして、都合の良い人選の根回しがしてあります。
しかし、委員の中から立候補の申し出があり慌てました。
すかさず、市長の指示と議員からの声で「先に提案があったのは立候補ではないから、話し合いで選出する」と押し切ってしまいました。
これだけを見ても、この委員会が市民の意見を反映させるものではなく、「市民が参加した形」を作り出すためだけのものであることが裏付けられました。
一般的な市民参加型の委員会では、委員長を選任しようとしても立候補が出ることはあまりないので、次善の策として事務局が推薦したり、仮の選考部会で適当な人選をすることはあります。
しかし、あくまでも立候補や推薦がなかった場合のことであって、名乗りが上がった場合は、そちらが優先するのは当然です。
「委員長は委員の互選」と設置要綱に明記されているのですから、市長が指図して密室の談合に持ち込むのは本末転倒です。
その後の話し合いも、発言のほとんどは事務局と市議に偏り、市民の声は封殺された状態が続きました。
傍聴していた伊那市民は、いつものこととはいえ、市民不在の市民参加に脱力感で一杯になったそうです。
さらに問題なのは、「決定方法が多数決による」と念を押されたことです。
委員の1/3は市議で、残りのほとんども市長が委嘱した身内です。
市民の声が反映される委員構成とは程遠い状態での多数決による採決が、どのような結果をもたらすかは分かりきっています。
マスコミもこれらの実態を明らかにする姿勢を持ち合わせない状況では、伊那市長の意向に沿った用地選定となるのは既定路線だと思われます。
2007年07月02日
・伐採のカラマツで小学生が重傷
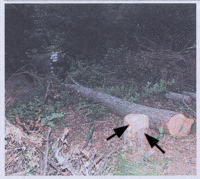 一日、上田市の雑木林で、伐採したカラマツが見学していた小学生に当たり、重傷を負う事故が発生しました。
一日、上田市の雑木林で、伐採したカラマツが見学していた小学生に当たり、重傷を負う事故が発生しました。信濃毎日新聞に伐採した現場の写真が掲載されています。
事故現場がどの程度保存されているのかはわかりませんが、写真から判断すると、伐採した男性は重大な過失をしていると考えられます。
**「つる」がない
画像をクリックすると拡大しますが、切断面の矢印で示した部分に、本来なら「つる」と呼ばれるものがなければなりません。
つるとは、伐採した木が倒れる時に蝶番の役割を果たし、狙った方向と違う方向に倒れないようにする大事な役割があります。
しかし、画像で見る限りでは、切り株にも、伐採された丸太の切断面にもつるの厚みが確認できません。
考えられるのは、追い口を切り込む際に、行き過ぎてつるとして残すべき部分まで切りすぎてしまったかも。
こうなると、受け口の方向に倒そうと考えていても、支持を失った木は重さや風の力の方向に自由に倒れてしまいます。
**受け口がない
画像の右側の矢印には、本来なら受け口が開口していなければならない。
受け口とは、伐採した木を倒す方向に倒れやすくするための三角形の切り込みです。
ツルが支点となって、受け口の角度までは伐採した木はスムースに倒れるはずです。
受け口の角度を使い切ると、ツルが破断しますが、その時には、木はほとんど倒れる寸前です。
写真をよく見ると、受け口を切り込んだ線が見えるので、受け口を切ったものの、取り除くべき三角形の木片を残したままで、追い口の切断に取り掛かった疑いがあります。
受け口で切り捨てられた三角の木片は、完全に切り離されていれば、追い口の切断で木が倒れると同時に排出されるかもしれませんが、通常ならそんなことはしません。
もし、受け口の開口を確認せずに、追い口を切り込んだとすれば、まったくの初心者か、腕を過信した経験者のどちらかだと思います。
報道によれば、伐採した男性の職業は造園業となっていますが、一般の人の感覚からすると「造園」=「木を伐る」と思われがちですが、庭師でも樹木の伐採に精通している職人は多くはありません。
知り合いのベテラン庭師が、60cmほどのクリの伐採ができないから、私に頼んできたこともあるくらいで、伐採の技術を持っていない庭師がいても不思議ではない。
今回の事故現場の写真を見ると造園業の男性は、チェーンソーが使えて木を切ることもできるが、伐採の基本が身についていなかったのではないかとの疑いが濃い。
大勢の小学生が見学している現場だったのなら、伐採方向にロープで引いておく安全対策は不可欠だったはずです。
木の伐採で命を落とす人の多くは、木の切り方は知っていても、伐り方を知らない場合が多いと思います。
事故に遭われた小学生の命が助かっただけでも幸いでしたが、事故を起こした男性がいくつもの過失を犯した罪は厳しく問われるべきだと思います。
2007年07月01日
・不都合な真実を見て

昨晩、子供たちと一緒に「不都合な真実」を見てきました。
駒ヶ根の文化会館で6月29日~7月1日の3日間、放映されています。
夜7時からの上映だったので、末の娘の就寝時間と重なって、本人は半分眠りについていましたが、読めない漢字の字幕と悪戦苦闘しながらも、映画が伝えようとしたメッセージの一部分は感じたようです。
中学の娘は、始めて知る地球温暖化の現実に驚きを隠せませんでしたが、これまでに学んできた海外青年協力隊での活動や学校などでの啓蒙学習の成果と考え合わせて、知識として断片化していたものの全体像を把握できたと喜んでいました。
映画は米国の温暖化防止対策の遅れを訴えることに比重が置かれていたのですが、日本だってそんなに優れた取り組みをしているわけではないので、対岸の火事とのん気に構えているわけには行きません。
私が最も感銘したのは、世界各国でスライド講座を開催する準備段階で、聴衆が温暖化防止の活動に取り組む障害となっている「意識」を調査し、その意識を取り除くことに重点をおいて構成していた点です。
温暖化防止対策をやっていない、遅れている人々に「ダメだな」と本音を言っては反発を受けて話しを聞いてもらえなくなります。
必要なのは、現実を直視させることではなく、現実を直視するのに障害となっている意識に気がつかせることなんだと、あらためて考えさせられました。
今後の温暖化防止への記事に、何とかして意識障害を取り除く要素を取り入れる方法がないものかと、これから常に考えたいと思います。






